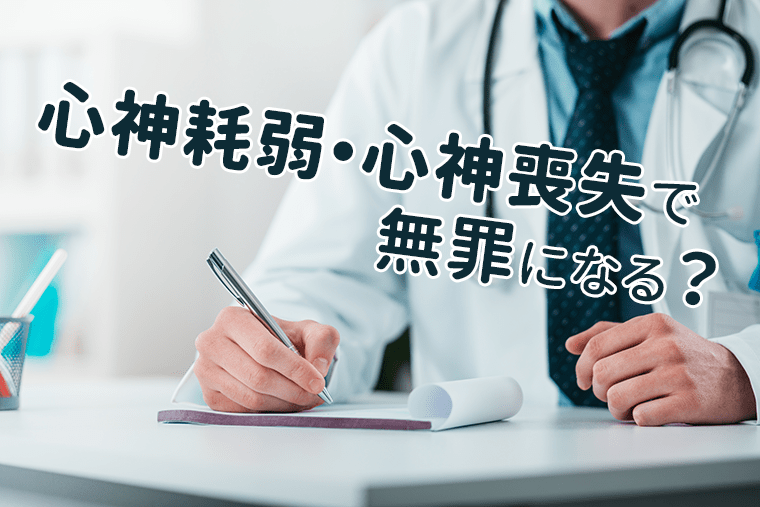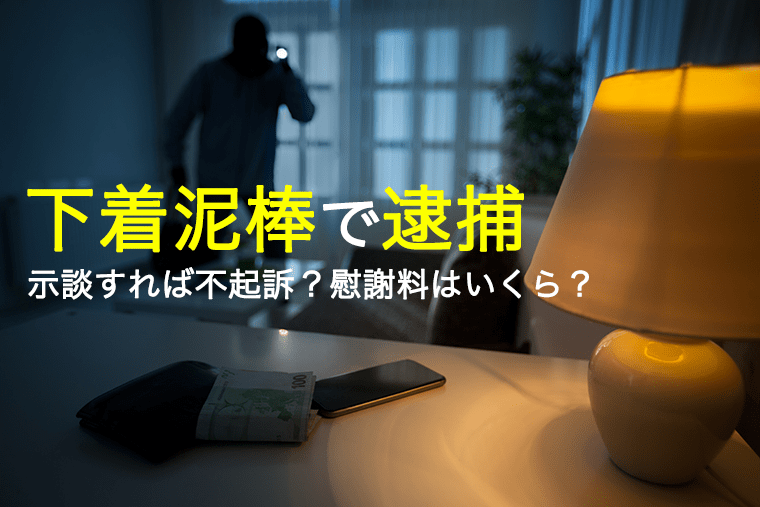ピック病で万引き!?認知症の方の刑事弁護と裁判判例

【この記事を読んでわかる事】
- 人格が変わる、犯罪を起こすようになる「ピック病」とは?
- ピック病(認知症)の人が刑事事件を起こした場合の刑罰はどうなる?
- 心神喪失、心神耗弱の場合、弁護士はどのような弁護活動をしてくれる?
皆さんは「ピック病」という認知症をご存知でしょうか。
ピック病は、「前頭側頭型認知症」の別名で、ある日突然怒りっぽくなったり、人格形成が変わってしまったりすると言われています。また、社会的なルールに従わなくなるため、暴力事件、セクハラ(痴漢)、万引き、他人の家に侵入する(不法侵入)などの反社会的な問題行動を躊躇なく取ることが増えるとも言われています。
では、ピック病が原因で犯罪を起こしてしまったときはどうなるのでしょうか。「心神喪失・心神耗弱で無罪となるのか」「家族が責任を取るのか」不安に思うご家族の方も多いと思われます。
以下においては、前頭側頭型認知症(ピック病)と、その刑事弁護などについて解説します。
1.ピック病の症状|なぜ万引きする?
ピック病(前頭側頭型認知症)は、前頭葉と側頭葉が強く委縮するために特異な症状を引き起こす進行性の認知症です。
若年性アルツハイマー病と同じく、40~60代と比較的若い世代が発症する「初老期認知症」の代表的疾患です。
ピック病は、アルツハイマー型認知症のような物忘れ(記憶障害)や時間・場所・人の状況の認識ができなくなる症状(見当識障害)が表れず、外見上は全く問題がないように見えますので、認知症だと気づかれにくいと言われています。
しかし、人の行動を決定する司令塔の前頭葉と、言葉の理解や判断、感情などをコントロールする側頭葉がうまく機能せず、本能の赴くままに行動する傾向があり、対人的・社会的なトラブルを引き起こしやすいとされています。
ピック病の特徴的な症状は「人格の変化」です。ピック病では、怒りっぽくなったり、他人を思いやる気持ちがなくなったり、善悪の判断をつけることができなくなります。
その結果、暴力や万引き、痴漢などの反社会的な行動を躊躇なく取ることになります。
ピック病の特徴的な症状としては、下記のような症状が挙げられます。
- 人格障害(温和だった人が怒りっぽくなったり、粗暴になったりするなど、今まで見られなかったような人格になります)
- 時刻表的行動(散歩や食事、入浴などの行為を毎日決まった時間に行います)
- 常同行動(徘徊ではなく同じコースをひたすら歩く「周徊」、紙に同じ文字を書き続ける「同語の反復書字」、絶えず膝を手でこすり続けたり、手をパチパチと叩いたりする、というような同じ行為を繰り返します)
- 反響言語(相手の言葉をそのままオウム返しに応えます)
- 病識の欠如(病初期より病気の自覚が欠如しています)
- 無関心(周囲の出来事に無関心になったり、身だしなみに気を使わず不潔になったりします)
- 反社会的行為(暴力、万引き、無銭飲食、痴漢、放尿、交通違反、他人の家に勝手にあがるなど、本能や気分の赴くまま振舞いますが、反省したり説明したりできず、同じ行為を繰り返します)
- 自発性・意欲の低下(家事、入浴、散髪、歯みがき、着替えをしなくなったり、新聞や雑誌を読まなくなったり、質問に対して真剣に答えず、すぐに「分からない」などと即答するようになります)
- 易刺激性(相手のしぐさ、表情の真似をしたり、目に見える看板や張り紙を大声で読んだりします)
- 食行動の異常(食欲の増加がみられ、チョコレートやジュースなど甘いものを毎日多量に飲食するようになります)
高齢者が、今までとは明らかに違う、上記のような問題行動を取るようになったら、ピック病という認知症のひとつの病気である可能性があるでしょう。
2.ピック病の責任能力と刑事弁護・家族の対策
では、ピック病の人が犯罪を犯した場合、責任能力はどう問われるのでしょうか?家族はどう対応するべきなのでしょうか?
(1) 被疑者段階の場合
弁護士が、被疑者との接見や家族からの情報の中で「ピック病の影響により被疑者が犯行に及んだ可能性がある」と考えた場合には、犯行当時、責任能力がない(心神喪失)ないし限定責任能力である(心神耗弱)ことを理由に、不起訴処分、あるいはその他の情状を考慮した起訴猶予処分を主張することになります。
そして、その前提として、弁護士は、被疑者がピック病に罹患していたことやその影響により犯行に及んだ可能性を示す証拠を収集したり、文献や裁判例の調査に加え、被疑者の具体的な病状について、精神科医と相談したりしながら、弁護方針を検討していくことになります。
(2) 精神鑑定の請求(鑑定書の取得)
被告人が、ピック病の影響により犯行に及んだと疑われる場合には、弁護士としては、その旨の主張をするとともに、精神鑑定の請求をすることになります。
そして、心神喪失又は心神耗弱を認めてもらえるように弁護活動を行います。
精神の障害があると鑑定された場合、その鑑定意見を前提に、量刑事情として、ピック病が犯行に与えた影響を主張することになります。
一方、精神鑑定の結果が望むものでなかった場合、鑑定内容の信用性を争うことになりますので、精神科医に対する反対尋問を効果的に行うための準備が必要になります。
また、裁判の推移によっては、弁護士の方から、再鑑定の請求、被告人に有利となる精神科医の証人申請や意見書の提出を検討すべきことになります。
(3) 再犯防止策の主張
残念なことに、ピック病の有効な治療手段は見つかっていません。
しかし、家族が監督を行い、再犯を防止する姿勢を示す(買い物は一人で行かせない、施設へ入所させる等)ことも、量刑に関する情状として大切なことになります。
3.ピック病の人が罪を犯した場合の裁判例
最後に、ピック病、あるいはその疑いがあると思わしき被疑者が万引きを犯した場合、過去にどのような判決が下されたのか、いくつか判例をご紹介します。
(1) 心神喪失事例
○大阪地判平29.3.22(LEX/DB文献番号25546119)
【事案の概要】
被告人(当時70歳)が、直近前科(万引き窃盗)の懲役刑の執行猶予期間中に、商店街の店舗において漬物2点(被害額500円)を両手でつかみ、代金を払わないまま自転車に乗って走り去ったという事案です。
なお、被告人は、本件犯行前に中等度ないし軽度の認知症と診断されており、直近前科の判決後も、家族が知る限りでも3回食料品を万引きして店員に見つかり、家族が買取りをして事件化されずに済んでいました。
被告人の犯行時の責任能力について、検察官は完全責任能力を主張したのに対し、弁護人は、被告人は中等度から重度の前頭側頭葉型認知症(ピック病)により買い物をして帰宅するという過去の習慣化された行動の一環としてなされたものであって心神喪失の状態にあったと主張しました。
【判決】
鑑定書に依拠して、被告人は一見店主と分かる人物の目前で犯行に及ぶという万引き犯人として不自然な行動に及んでいることなどから、
「本件当日の被告人の行動は、認知症の影響を考慮しないと合理的な説明ができず、同認知症が発症した可能性のある時期以前の被告人には本件のような万引き等の問題行動はみられず、発症の前後で明らかな懸隔が認められることも併せみると、本件当時の被告人につき、事理弁識能力ないし行動制御能力が著しく減弱していたのはもとより、これらの能力を欠いていた疑いは合理的に否定できない」
と判示して、被告人に無罪を言い渡しました(求刑・懲役10月)。
(2) 心神耗弱事例
○横浜地判平27.10.15(LLI/DB判例番号L07050713)
【事案の概要】
被告人が、万引き(被害点数32点、被害額4,798円)をしたという事案です。
被告人は、犯行時、前頭側頭型認知症(ピック病)に罹患していました。
【判決】
鑑定結果を前提に、被告人は本件犯行当時、善悪の判断は可能であり、事理弁識能力は著しく減退してはいなかったと認められるとしましたが、行動制御能力については、
「被告人の安定した経済状況等からすれば、認知症の影響により物を欲しいという欲求のためにその手段として窃盗という行動に至る過程については、やや飛躍があるといわざるを得ず、被告人が前頭側頭型認知症のため欲求を自制することが困難な状態になっていたということを考慮して初めて合理的な説明が可能といえる」とし、「本件犯行当時、被告人の行動制御能力が完全に失われていたということまではいうことができず、著しく減退していたものと認めるのが相当である」
と判示して、被告人に懲役8月執行猶予2年を言い渡しました(求刑・懲役1年)。
(3) 完全責任能力事例
○大阪高判平26.3.18(LLI/DB判例番号L06920124)
【事案の概要】
被告人が、窃盗罪で執行猶予期間中に、スーパーマーケットで食料品4点を万引きしたという事案です。
原審が懲役7月の実刑に処したのに対し、被告人が控訴したものです。
【判決】
被告人は前頭側頭型認知症(ピック病)に罹患していた点を量刑上被告人に有利に考慮するのが相当であること、本件発覚後は、被告人の再発防止のための環境や監護体制が格段に整っていることなどを理由として、
「原判決の量刑は、刑の執行を再度猶予しなかった点において、重すぎるといわざるを得ない」
と判示して、被告人に懲役10月保護観察付執行猶予4年を言い渡しました(求刑・懲役10月)。
○東京高判平27.11.10(LLI/DB判例番号L07020584)
【事案の概要】
被告人(当時68歳)が、万引きの前科で執行猶予期間中に、スーパーマーケットで菓子1箱(600円相当)を手にしたかと思うと、すぐに手提げバッグの中に入れて窃取したという事案です。
被告人は、懲役7月の実刑に処した原判決の量刑は重すぎて不当であるとして控訴しました。
高裁において取り調べた精神科医の意見書では、被告人には前頭側頭型認知症が示唆され、これらの疾病性が本件犯行に影響を及ぼしているとされましたが、原判決時においては、被告人に病識がなく家族も気づいていませんでした。
【判決】
「本件犯行は、前頭側頭型認知症による疾病性に影響され、行動制御能力がある程度低下していた下で行われたものと考えられる。このような犯行の態様や結果、疾病性の影響からすれば、執行猶予中の同種犯行であるから、直ちに実刑が避けられないとみるべきではなく、・・・、その情状に特に酌量すべきものがあると認められる」
と判示して原判決を破棄し、被告人に懲役7月保護観察付執行猶予4年を言い渡しました。
(4) その他
○高松高判平28.6.21(高等裁判所刑事裁判速報集平成28年293頁)
【事案の概要】
被告人が、万引き(被害点数4点、被害額1,160円)をしたという事案です。
弁護人が依頼した専門医が意見書において、「被告人は、犯行当時、前頭側頭型認知症に罹患し、弁識制御能力をほぼ喪失していたか、著しく障害されていた可能性があり、責任能力の有無及び程度を明らかにするためには、正式な精神鑑定の必要がある」旨を述べていたにもかかわらず、原審は、鑑定請求を却下して実施せず、あるいはそれに準ずる方法によって精神医学上の専門的見解を求めませんでした。
【判決】
原審が、鑑定請求を却下して実施せず、あるいはそれに準ずる方法によって精神医学上の専門的見解を求めなかった訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、原判決を破棄・差し戻しました。
4.まとめ
刑事事件は自分とは無関係だと思っていても、ピック病になった家族が、ふとした時に罪を犯してしまう可能性は0ではありません。
ピック病による万引き事件でも、ご家族の方が正しく監督を行い、再犯を防止する姿勢を示すことで、不起訴となる可能性や、執行猶予がつく可能性は十分にあります。
刑事事件の解決は、実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。