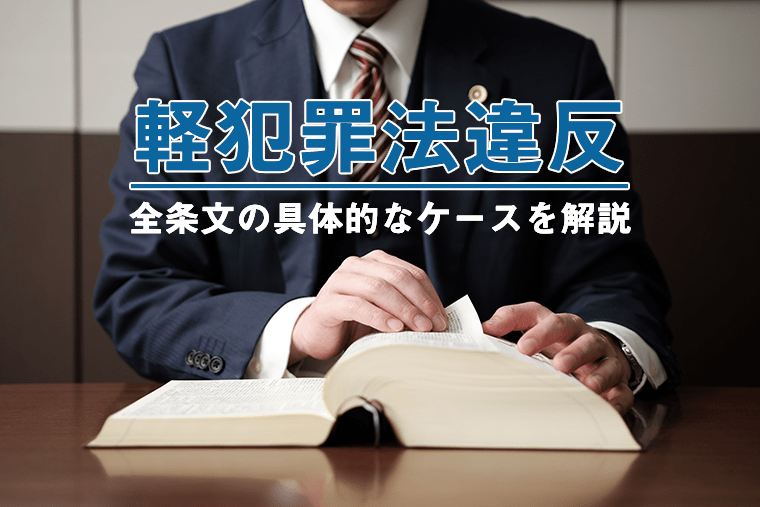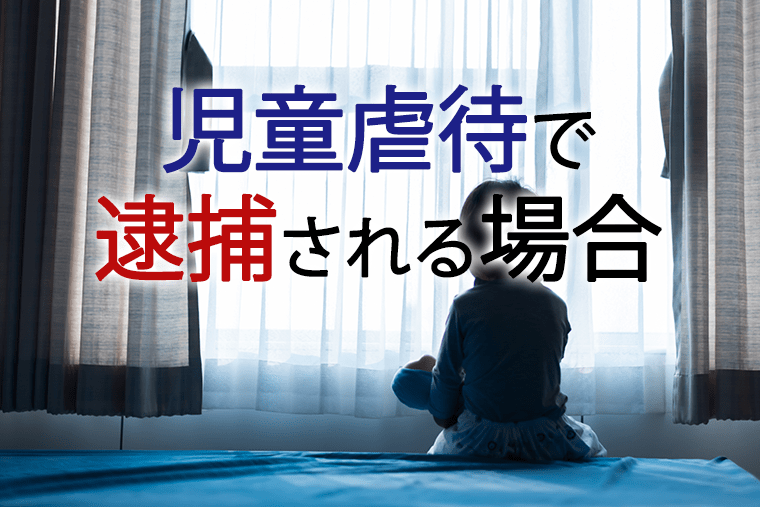日本における死刑制度|死刑のある犯罪とは?廃止するべき?

死刑が求刑されるような重大事件の報道は頻繁に起こります。
また、2018年7月にはオウム真理教事件の死刑囚13人の死刑執行が相次いで行われ、大きなニュースとなりました。
今回は、日本において死刑が適用されるケースやその基準(何人殺すと死刑になるのか?等)などに触れると共に、よくある勘違い(「1人を殺しただけでは死刑にはならない」「死刑囚が再審請求をしていると死刑を執行できない」など)についても解説します。
ニュースの報道内容をより深く読み解くための基礎知識として一読いただければと思います。
1.現行の死刑制度の内容
日本において、果たしていつから死刑という公的な制度が設けられたのかは不明です。
しかし、鎌倉政権の有名な「御成敗式目」でも、殺人は死刑か流罪として財産も没収するとされていたそうです。
また、戦国時代の死刑は苛烈を極め、磔(はりつけ)、逆磔、串刺し、鋸挽き、牛裂き、車裂き、火あぶり、釜煎り、簀巻きなどがありました。
江戸時代には法令が整備されましたが、相変わらず、磔、鋸挽き、火あぶり、獄門など、残酷な死刑が残ったままでした(「江戸の刑罰」石井良助著・中公新書29頁参照)。
激動の明治維新を迎えて、死刑制度の内容も目まぐるしい改正を繰り返しますが、旧刑法(1882年)によって死刑の方法は絞首刑だけと定められました。
そして、旧刑法は、1907年に現行の刑法に改正され、今日に至っています。
では、現在の死刑制度の内容を見てみましょう。
(1) 死刑になる犯罪
現在、法定刑に死刑のある犯罪は、刑法犯の12種類と特別法犯の6種類(計18種)です(2023年12月時点)。
①刑法犯(12種類)
刑法で死刑が法定刑に定められているのは、次の12種類の犯罪です。
- 内乱罪(77条第1項)
- 外患誘致罪(81条)
- 外患援助罪(82条)
- 現住建造物等放火罪(108条)
- 激発物破裂罪(117条1項)
- 現住建造物等浸害罪(119条)
- 汽車転覆等致死罪(126条3項)
- 往来危険汽車転覆等罪(127条)
- 水道毒物等混入致死罪(146条)
- 殺人罪(199条)
- 強盗致死罪(240条)
- 強盗強制性交等致死罪(241条3項)
あまり耳慣れない罪名も多いと思いますので、一例をあげて説明します。
内乱罪とは、平たく言えば暴動によって国家権力を奪取することで、武力で内閣や国家を制圧するようなイメージです。革命や国家転覆のことです。
外患誘致罪は、外国と通じて日本に戦争を仕掛けさせたケースで、つまり国家反逆罪です。外患誘致罪は、法定刑が死刑しかありません。
それ以外にも、電車や船舶を転覆、沈没させたり、飲料水の上水道に毒を入れたりと、大勢の生命に関わりうる極めて危険な犯罪に死刑が定められています。
②特別法犯(6種類)
刑法以外の特別法で、死刑が法定刑に定められているのは、次6種類の犯罪です。
こちらも、ハイジャックや人質など、いわゆる物騒な犯罪ばかりです。
- 爆発物使用罪(爆発物取締罰則、第1条)
- 決闘殺人罪(決闘罪ニ関スル件、第3条)
- 航空機強取等致死罪(航空機の強取等の処罰に関する法律、第2条)
- 人質殺害罪(人質による強要行為等の処罰に関する法律、第4条)
- 組織的な殺人罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、第3条1項3号)
(2) 死刑が適用されるケース(永山基準)
死刑を適用するべきかどうかを判断する基準としては、有名な「永山基準」と言われるものがあります。
これは1968(昭和43)年、当時19歳であった永山則夫元死刑囚が、短期間に4名を射殺した連続殺人事件において、無期懲役とした東京高裁判決を破棄した際に最高裁が示した考え方です。
整理すると、以下のとおりです。
【考慮要素・情状】
(1)犯行の罪質
(2)犯行の動機
(3)犯行の態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性
(4)結果の重大性ことに殺害された被害者の数
(5)遺族の被害感情
(6)社会的影響
(7)犯人の年齢
(8)前科
(9)犯行後の情状等
(これら9つの)各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される(最高昭和58年7月8日判決)。
この永山基準の「ことに殺害された被害者の数」という言い回しから、「1人を殺しただけでは死刑にはならない」という話が一般に信じられるようになってしまいました。
しかし、これは誤解です。
法務省総合研究所が1996(平成8)年にまとめた「凶悪重大事犯の実態及び量刑に関する研究」によれば、この永山基準の最高裁判決後、1996(平成8)年までの間に、被害者が1人の殺人事件の14%、強盗殺人事件の3%で死刑判決が出ているとされています※。
もちろん、被害者が1名よりも複数名のほうが死刑判決となりやすいことは事実ですが、被害者が1人だから死刑にならないというわけではありません。
※「死刑の基準 永山裁判が遺したもの」堀川惠子著・日本評論社305頁
2.死刑執行の手続きと流れ
(1) 執行決定前の手続
死刑判決が確定すると、裁判所から検察庁へ判決謄本と公判記録が送付されます。
たとえば最高裁で死刑判決が確定すると東京高等検察庁に送付され、これを受けて、その検察庁の長(検事長又は検事正)が「死刑執行に関する上申書」を法務大臣に提出します。
上申書が提出されると、法務省は記録を取り寄せ、刑事局の局付検事(平たく言うと、若手で優秀と評価されている検事)が担当者となり記録を検討します。死刑執行停止、再審、非常上告といった死刑を執行すべきでない事由や判決の誤りの有無を精査します。
そのうえで、「死刑執行起案書」を作成し、法務省内の決済に回します。
死刑執行起案書は、刑事局を皮切りに、矯正局、保護局で、合計11名の決済官の決済を受けます。刑事局に戻った死刑執行起案書は、「死刑執行命令書」と名称を変えて、いよいよ法務大臣官房に回されます。そこで4名の決済官の決済を受けた後に、法務大臣に提出されます。
このように、死刑判決を執行するための書類が法務大臣のもとに届くまでに、上に挙げただけで16名の人間から審査・決済を受けています。
死刑執行命令書を受け取った法務大臣は、公判記録を熟読したうえで、死刑を執行するかどうかを判断します。
※参考「ビギナーズ刑事政策・第2版」守山正外編著
(2) 執行決定後の手続
法務大臣が死刑執行を決断したら、死刑執行命令書にサインをします。
これにより、法務大臣の死刑執行命令(刑事訴訟法475条1項)が発せられたことになり、5日以内に死刑を執行しなくてはなりません(同476条)。5日以内としたのは、刑事施設が準備をする都合のためです。
ここで、最初に「死刑執行に関する上申書」を提出した担当検察庁の長が「死刑執行指揮書」を作成し、以後はこの指示書にしたがって死刑が執行されます。
(3) 死刑執行方法
死刑囚には、当日、いよいよ執行されるときまで、死刑が執行されることは知らされません。
1970年代までは、拘置所長の判断で執行の数日前に本人に告知し、死刑囚仲間がお別れ会を開いたケースもあったとのことですが、告知を受けた死刑囚が自殺をした事件があり、以後、全国の拘置所で当日告知が徹底されたそうです。
執行当日は、朝、独房に刑務官がやってきて、本日、死刑が執行されることを告知され、そのまま刑場の控室まで連行されます。約1時間の猶予を与えられ、その間に遺書を書いたり、タバコを吸ったりすることが許されます。教誨師(きょうかいし。僧侶、神主、神父、牧師のこと)と最後の会話をし、祈りを捧げたりする時間でもあります。
死刑を行う場所は、「刑事施設内」です(刑法11条、刑事収容法178条1項)。そして、刑場に入るには検察官又は刑事施設長の許可が必要です(刑事訴訟法477条2項)。
これは一見当たり前のような定めですが、江戸時代まで行われていた公開処刑を否定したもので、密行主義といいます。
死刑は、「絞首」で執行します(刑法11条)。
絞首刑だけになった理由について、旧刑法の起草にかかわったフランス法学者ボアソナードは、「斬首と違って身体と首がバラバラにならず、親族が遺体を引き取るときも悲哀の感情が軽くなる」からと述べたそうです(※「死刑」読売新聞社会部・中央公論新社30頁)。
目隠しと手錠をされて、刑場の中心にある約1メートル四方の踏み板の上に立ち、足を縛られた後に直径3センチほどのロープを首にかけられます。
刑場の外には3〜5個の「執行ボタン」が設置されており、そのうちひとつが踏み板と連動しています。どのボタンが連動したボタンなのかはボタンを押す刑務官には秘密にされています。
合図とともに、刑務官3〜5人が一斉にボタンを押すと、踏み板が外れて死刑囚の体が落下します。
踏み板の下には高さ4メートルの空間があり、落下の衝撃と自重で死刑囚の頚椎は骨折しますので、瞬時に意識がなくなり苦痛はないとされています。
なお、死刑の執行は、日曜日、土曜日、祝日、12月29日から1月3日は行わないこととされています(刑事収容法178条1項)。
(4) 執行後の手続
医師が脈と聴診器で心停止を確認します。平均15分程度で心臓が停止するそうです。
なお、心停止で死亡が確認されてから、さらに5分間経過してからでないと首のロープを解くことはできません(刑事収容法179条)。
5分を経過したら、刑務官らが遺体をおろしてやり、きれいに清拭したうえで白装束に着替えさせ、別室で簡単な葬儀を行います。
死刑執行には、検察官、検察事務官、刑事施設の長ら又はその代理人が立会い、ガラス板で仕切られた別室から死刑が執行される様子を確認します(刑事訴訟法477条)。
検察事務官は、報告書(執行始末書)を作成し、検察官と刑事施設の長が署名、押印します(同478条)。
3.死刑が執行できないケース
法務大臣は、死刑判決確定の日から6ヶ月以内に死刑の執行を命令しなくてはならないとされています(刑事訴訟法475条2項)。あまり長期にわたって死の恐怖にさらさないようにすることが、6ヶ月以内とした本来の趣旨でした。
ただし、この6ヶ月には次の期間は含まれないとされています(同項但し書き)。
- 上訴権回復の請求がされその手続が終了するまでの期間
- 再審の請求がされその手続が終了するまでの期間
- 非常上告がされその手続が終了するまでの期間
- 恩赦の申し出、出願がされその手続が終了するまでの期間
- 共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間
また、死刑囚が心神喪失状態であるとき、死刑囚の女性が妊娠しているときには、法務大臣の命令で死刑執行を停止しなくてはなりません(刑事訴訟法479条1項、2項)。心神喪失から回復し、女子は出産した後には死刑を執行することができます(同3項)。
心神喪失中の者に執行できない理由は、刑罰の意味を理解できないものに対する刑罰の執行は無意味だからと言われています(しかし、ここは議論のあるところだと思います)。
妊娠中に死刑を執行できないのは、もちろん、お腹の子どもには罪はないからです。
4.死刑存置論と廃止論
ご承知の方も少なくないでしょうが、死刑については、廃止論(反対論)と存置論(賛成論)の深刻な対立があります。
【廃止論】
- 国家が殺人を犯罪としておきながら、犯人の生命を奪うことは矛盾である(法哲学的観点)
- 死刑には犯罪に対する威嚇力はない
- 死刑は「残虐な刑罰」を禁じる憲法36条に違反する
- 死刑でなくとも仮釈放のない終身刑であれば犯人の再度の犯罪を完全に防止できる
- 誤判を完全になくすことができない以上、取り返しのつかない死刑は認めるべきでない
【存置論】
- 殺人を犯した者には、その生命で償わせることが国民感情に合致している(応報的観点)
- 死刑には犯罪に対する威嚇力がある
- 凶悪犯は死刑によって社会から完全に隔離する必要がある
死刑に「犯罪に対する威嚇力があるかないか」については、それを裏付ける実証データがないままです。
他方、誤判の可能性を否定できないことは事実です。死刑には取り返しがつかない危険があります。
日本では、5年に1度ほどの頻度で「基本的法制度に関する世論調査」が行われており、そこで死刑制度の存廃についても触れられています。
直近では、令和元年11月に調査が行われており、そこでの回答は以下のようになっています。
- 「死刑は廃止すべきである」9.0%
- 「死刑もやむを得ない」80.8%
- 「わからない・一概に言えない」10.2%
「死刑もやむを得ない」との回答が80%を超えており、このことから、日本においては死刑存置論が根強いとの主張がなされています。
ちなみに、世界的にみると、2022年12月現在の死刑存置国は55カ国、死刑廃止国(全ての犯罪に対して廃止)は112カ国となっています。
また、経済協力開発機構加盟国(34か国)のうち、死刑を存置して いるのは日本・韓国・米国の3か国だけです。
世界の流れは死刑廃止にむかっていることは事実であるようです。
とはいえ、死刑を廃止した国でも、その後もたびたび死刑復活運動が起きているといいます。
死刑の廃止と存置については、永遠に続く論争なのかもしれません。