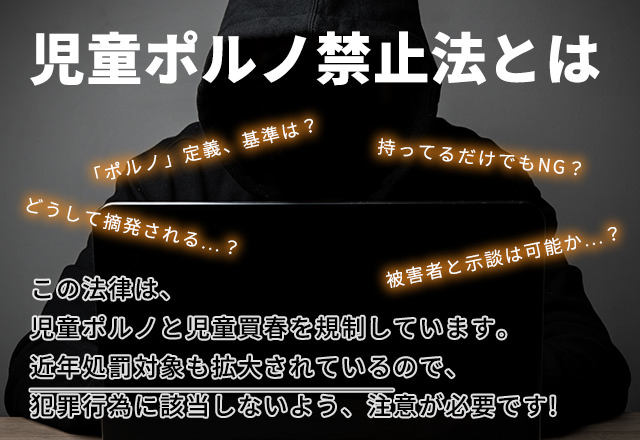児童買春に強い弁護士|弁護士に依頼する場合と依頼しない場合の違い

近年、性犯罪に対しては特に厳しい目が向けられています。そのため、児童買春等をした場合も以前より厳格な処分がされる可能性があります。
児童買春をしてしまった場合、迅速な対応をしなければ、初犯の場合であっても懲役刑になるなど取り返しのつかないことになってしまいます。
ここでは、児童買春の罪、児童買春が発覚した場合の流れ、弁護士に依頼すべき理由等について解説します。
1.児童買春とは?
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されています。
児童買春とは、児童やその保護者に金銭などの対価を与える又はその約束をして、児童に性的な行為(性交や性交類似行為、自己の性器を触らせる行為を含む)をすることをいいます。児童とは、18歳未満の者をいい、男子女子を問いません。
例えば、16歳の女子に1万円を渡し性器を触る、性交をするなどの行為は児童買春に該当します。また、金銭だけでなくバッグやネックレス等も対価にあたりますので、これらを渡して性的な行為をしたケースも児童買春となります。
児童買春をした者の罰則は、5年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金刑となっています。
では、対価を与えたり、その約束をしていなければ、18歳未満との性行為は自由なのかと言えば、そうではありません。
まず、13歳以上18歳未満の被害者に対して暴行脅迫を用いて性交等を行った場合、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立します(旧強制性交等罪・強制わいせつ罪)。
被害者が13歳未満の場合は、暴行・脅迫がなく、被害者の同意を得ていても不同意性交等罪や不同意わいせつ罪となります。法定刑は6月以上10年以下の懲役刑です。
さらに、18歳未満の被害者との性交等は、暴行・脅迫や同意の有無を問わず、各自治体が定めている「淫行条例」に違反する場合があります。
例えば「東京都青少年の健全な育成に関する条例」は、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と定め、違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
このように18歳未満との性行為は、相手の年齢によって、様々な法律に抵触して、刑事罰を受ける危険性があることを十分に認識しておくべきです。
2.児童買春が発覚したらどうなる?
被害児童が補導された際に警察に売春について供述したり、児童の行動を不審に思った保護者が相談したりすることで、児童買春が発覚するケースがあります。
この場合、児童買春をした者は逮捕される可能性があります。
捜査機関により逮捕された被疑者は、警察署に連行され取調べを受けます。その後、被疑者の身柄は証拠と共に検察官に送致されます。
被疑者を受け取った検察官は、被疑者の勾留を裁判官に請求するか否かを判断します。勾留請求が裁判官によって認められると、被疑者は10日間〜20日間に及び身体拘束され継続捜査を受けます。
検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか否かを判断します。
(勾留されずに在宅事件となった場合は期間の制限はありませんが、やはり起訴するか否かを判断するための捜査が行われます。)
起訴された場合、被告人は刑事裁判を受けることになります。裁判で有罪判決となった場合、懲役刑であれば執行猶予がつかない限り、刑務所行きとなります。
なお、起訴されたとしても、略式起訴ならば罰金刑となり公判は開かれません。しかし、罰金刑でも前科となります。
3.児童買春をした場合の刑事弁護|被害者との示談
(1) 示談の重要性
上記の説明から分かるように、児童買春の罪を犯した方は、捜査機関に逮捕・勾留等の身体拘束をされてしまう可能性があります。
当然のことながら、身体拘束の期間中は通常の生活は行うことができません。そのため、会社に児童買春の事実が発覚して懲戒処分を受けることも考えられます。
また、検察官は十分な証拠を準備した上で起訴をしますので、起訴処分となってしまった場合には無罪判決はほとんどなく、ほぼ確実に有罪判決となって前科がついてしまいます。前科が付くと、就職・再就職活動で不利になるなどの事態になってしまいます。
そこで、これらの事態を避けるためには、被害者と示談することが非常に重要です。示談をすることで、捜査機関が逮捕・勾留を控えたり、不起訴処分となったりする可能性を少しでも高める必要があります。
また、仮に起訴されたとしても、示談を成立させていれば、公開の法廷に出廷することなく書類上の手続だけで罰金刑を受ける「略式手続(略式裁判)」に留まる可能性が高くなります。
検察官が裁判所に略式手続を求めることを「略式起訴」といいますが、2019(令和元)年では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事件で起訴された1971人のうち、1485人が略式起訴でした。
確かに、正式起訴をされた者も486人(約25%)もいました。4人に1人が公開の法廷で裁判を受けることになったのです。
法廷で裁かれることになれば、裁判は誰でも傍聴できますし、裁判所では児童買春という罪名とともに、被告人の氏名が貼り出されます。つまり、児童買春の事実は公開されてしまうので、報道されるリスクも著しく高くなります。
よって、できる限り正式起訴を避けるためにも、示談成立に注力するべきなのです。
(2) 示談交渉を弁護士に依頼すべき理由
近年は、性犯罪、特に年少者に対する性犯罪に対する検察の姿勢は厳しさを増しており、簡単には不起訴となりません。
例えば、2019(令和元)年では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事件は、総数5674人のうち、不起訴(起訴猶予)となったのは430人であり、わずか約7.57%です(※)。
※検察統計「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」2019年
しかし、被害者との示談交渉が成功すれば、略式起訴に留まる可能性はぐっと高くなります。
示談を考えている方は、自ら示談をするのではなく、弁護士に示談交渉を担当してもらうべきです。
まず、弁護士でない限り、示談の方法や、合意内容に何を織り込むかべきといったことが分からないためです。
例えば、知識がないと、①示談金を分割払いとする合意をしてしまうケース、②宥恕文言(※)が記載されていない示談書を作成してしまうケースがあります。
※宥恕文言:宥恕(ゆうじょ)とは「許す」の意味で、「寛大な処分を求めます」、「処罰は望みません」などの記載です。
①は、検察官が処分を決める段階で示談金が完済されておらず、今後、支払われる保証もないので、示談の効果は限定的です。
②は、被害者の処罰感情がなくなったり、低下したりした事実が現れておらず、事案によっては、「示談金を受け取っても宥恕はできない」という強い処罰感情の証左となってしまう危険もあります。
次に、犯罪の当事者同士の示談は非常に困難であるためです。
そもそも、警察官、検察官は被疑者に被害者の連絡先を教えないのが通常です。そのため、事実上、被疑者単独では示談できません。
弁護士に示談を依頼すれば、警察官、検察官は被害者の意向を確認し、被疑者に連絡先を教えないことを条件に、弁護士に限り示談のために連絡先を教えてくれます。
また、児童買春事件で示談を行うのは、未成年者である被害者本人ではなく、被害者の家族(保護者)ですが、保護者は被疑者に相当の怒りを持っていることが通常ですので、交渉を拒否されるか、交渉には応じてくれても、中身がなかなかまとまらないといった事になります。
このような中で示談交渉をのんびりやっていた結果、検察官が起訴の判断を下してしまい、手遅れとなってしまうといったことがありえます。
他方、弁護士に依頼すれば、保護者の方も弁護士を信頼して示談交渉に臨んでくれるケースが多く、迅速な示談成立の可能性が高くなります。
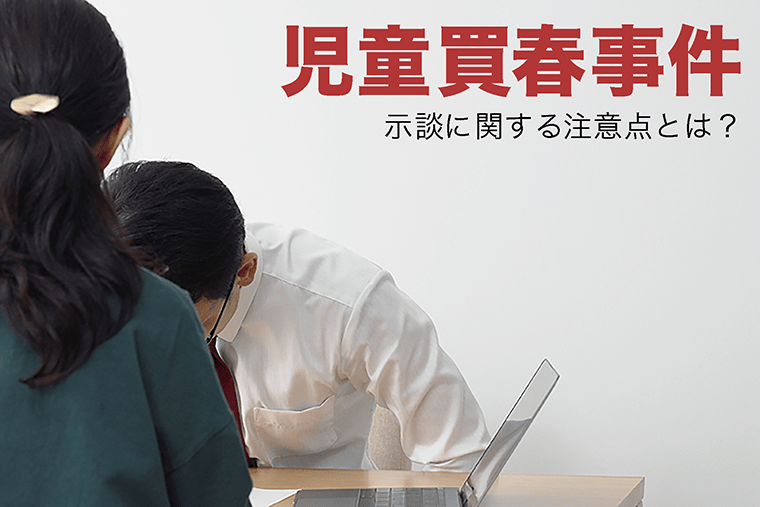
[参考記事]
児童買春事件における示談の注意点と弁護士の役割
4.児童買春に強い弁護士の選び方
弁護士にも得意分野、専門的に扱っている分野がありますから、まずは、刑事事件を得意とし、専門的に扱っている弁護士に依頼することを考えるべきです。
その中でも、児童買春事件を担当したことがある弁護士なら、より心強いでしょう。
児童買春罪は、被害児童の心身に悪影響を与える重大犯罪です。もし児童買春をしてしまったら、これを反省し再犯防止に努める必要があります。
共に、被害児童や保護者にしっかり謝罪し、示談を成立させることも重要です。
さらに、自らの今後についても考える必要があります。身体拘束された場合や起訴された場合の精神的負担は計り知れません。これらを回避する早期釈放のためにも、一日でも早く弁護活動を弁護士に依頼するべきです。
児童買春に限らず、刑事事件を犯してしまった方は、刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。