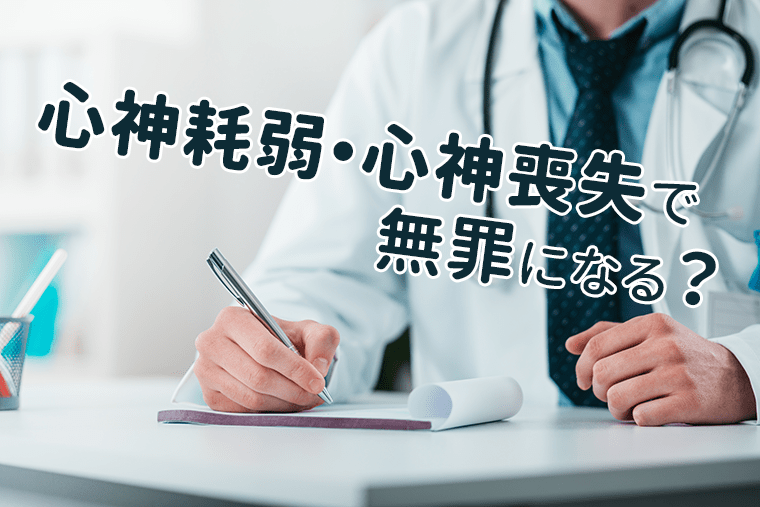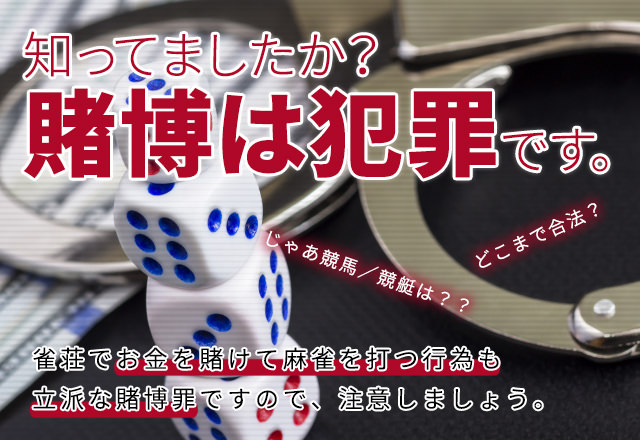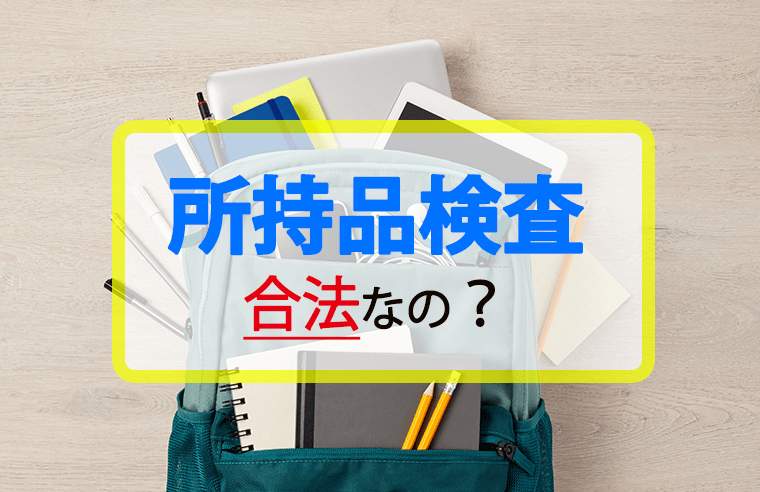2018年6月施行の日本型司法取引-メリット・デメリット・課題を解説
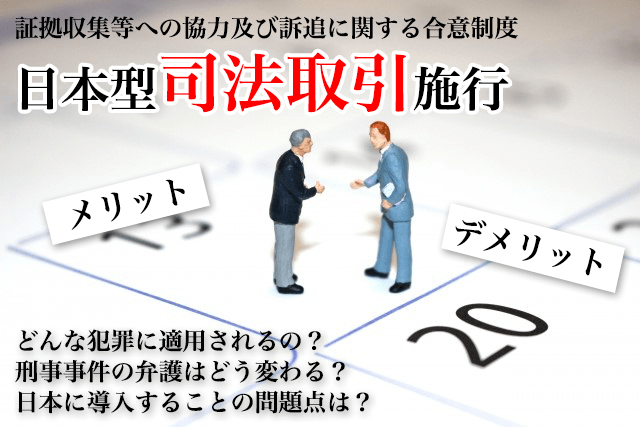
改正刑事訴訟法の「司法取引」制度が、2018(平成30)年6月1日から施行されています。
容疑者が重要な供述などにより捜査・裁判に協力することで刑の減免を受ける司法取引は、欧米諸国で広く採用されています。
では、日本で導入された「司法取引」制度とは具体的にどのようなもので、この制度を導入したことで何かメリットはあるのでしょうか。
1.司法取引制度の概要と目的
「司法取引」制度は、2016(平成28)年の刑事訴訟法改正により、捜査・公判協力型の協議・合意制度として新たに導入されたものです。
目的は、被疑者の取り調べと供述調書への過度の依存を改め、取り調べ以外の方法で供述証拠等を獲得するためとされています。
「司法取引」制度は、刑事訴訟法350条の2以下で以下のように定められています。
特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪(刑事訴訟法350条の2第2項各号の「特定犯罪」)について、検察官と被疑者・被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者・被告人が、共犯者等他人の刑事事件の解明に資する供述をし、証拠を提出するなどの協力行為を行い、検察官がその協力行為の見返りに、被疑者・被告人に有利に考慮して、これを不起訴にしたり、軽い罪で起訴したり、軽い求刑をするなどを内容とする「合意」をすることができるとし、このような両当事者間の協議・合意を通じて、他人の犯罪行為の訴追・処罰に必要な供述証拠等を獲得しようとするもの
司法取引は、「特定犯罪に係る他人の刑事事件」に関連性のある自己の刑事事件について行われます(法350条の2第1項)。
「他人」とは、合意の主体である被疑者・被告人の共犯者や対向犯関係にある者が典型ですが、法人も「他人」となり得ます。
企業犯罪や組織犯罪においては、事案の解明を図るため末端の実行者など組織内部の者から供述を得ることが必要不可欠な場合があります。司法取引はこれを可能にするのです。
したがって、司法取引として想定されるのは、企業犯罪や組織犯罪において、末端の者の犯罪に刑の減免を約束して、組織上層部の犯罪についての供述を求めるケースということになるでしょう。
2.司法取引の内容
司法取引制度は、検察官に「他人の刑事事件を供述して自己の刑事責任を減免してもらう」ことになりますので、一般国民の正義感にそぐわない面があります。
しかし、それが許される背景には、個人責任よりも悪を懲らしめるという社会的責任の方が優るからといえましょう。
では、そのような司法取引の具体的な内容を見ていきます。
(1) 被疑者の減刑の内容
司法取引では、他人の刑事事件の捜査への「協力」が必須です。
最終的に裁判所が関与し、協力・合意者(被疑者または被告人であり、司法取引者)には下記のような特典を与える、という内容の合意をすることができます(法350条の2第1項2号)。
- 不起訴処分になる
- 公訴が取り消される
- 軽い罪で起訴される
- 起訴後に、軽い罪に変更される
- 軽い求刑がなされる
- 即決裁判という簡易な手続で処理される
- 略式命令という罰金又は科料で処理される
なお、合意が成立しなかったときは、被疑者・被告人が協議において他人の刑事事件についてした供述は証拠とすることができません。
(2) 弁護人の同意が必要
被疑者が司法取引に関する合意をするには、その弁護人の同意がなければなりません(法350条の3第1項)。
この合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により行います。
また、この合意をするために必要な「協議」は、原則として、検察官と被疑者・被告人及びその弁護人との間で行います。
被疑者・被告人は、刑の減免を考えるあまり、率先してより大きな特典をもらおうとしてくる可能性があります。
このため、協議の開始から合意の成立・不成立まで、弁護人の関与を義務付けています。
つまり、被疑者・被告人は先に弁護人と相談し、供述するかどうか決めることになります。
(3) 合意の違反(虚偽の供述など)の刑罰
合意の当事者は、相手方当事者が合意に違反したとき(またはその他一定の場合)には、合意から離脱することができます(法350条の10第1項)。
つまり、合意の当事者(被疑者・被告人)の供述が虚偽であったことを被疑者・被告人自身が認めた場合や、真実でないことがその後の捜査等によって客観的に明らかになった場合には、相手方当事者(検察官)は、司法取引を破棄することが考えられます。
また、合意の当事者(検察官)が合意に違反して公訴権を行使したときは、裁判所は判決で当該公訴を棄却しなければなりません(法350条13の第1項)。
合意をした者が捜査機関に対し虚偽の供述をし、又は偽造・変造の証拠を提出したときは、犯罪として処罰の対象とし、法定刑を「5以下の懲役」という相当重いものとしています。
(これが、司法取引に信用性を確保する唯一の方法となっています。)
また、協力者が虚偽供述等をした場合は処罰を恐れて供述等を覆せなくなってきますので、裁判確定前に虚偽を自白した場合には刑の減免を認めて虚偽供述等の抑止と巻込みの未然防止が図られています(法350条の15)。
3.司法取引の対象とされる犯罪
司法取引の対象とされる犯罪は、この制度を用いる必要性が高く、利用に適しており、かつ、被害者をはじめとする国民の理解が得られやすいという観点から、特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪に限定されています。(※裁判員裁判対象事件は対象となりません。)
また、死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる犯罪は除外され(法350条の2第2項柱書)、身体及び精神的被害を伴う犯罪については、司法取引によって刑の減免を認めることは適当でないと考えられています。
(1) 法に明記されている犯罪
- 刑法の一定の犯罪(贈収賄、詐欺など)
- 組織的犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)
- 覚せい剤取締法、銃刀法などの薬物銃器犯罪
(2) 政令で新たに規定された主な財政経済犯罪
- 租税に関する法律違反(脱税など)
- 独占禁止法違反(談合、価格カルテルなど)
- 金融商品取引法違反(粉飾決算、インサイダー取引など)
- 特許法違反(特許権侵害など)
- 貸金業法違反(無登録営業など)
- 不正競争防止法違反(営業秘密侵害など)
- 破産法違反(詐欺破産など)
- 会社法違反(特別背任など)
4.司法取引のメリット・デメリットと問題点
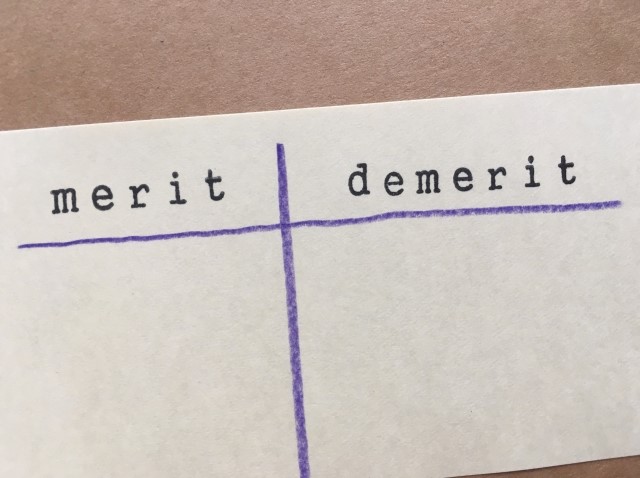
(1) メリット
- 他人の犯罪に関する動機などの証拠が不十分な場合、確実な証拠を持っている者の供述を得ると、他人の犯罪の発見が高められ、より重要な犯罪の捜査に役立つ情報が得られます。
- 捜査機関が他人の犯罪を聞き出すことが容易になり、組織的犯罪等の解明に威力を発揮することが期待できます。
- 密行性の高い組織的犯罪等について、首謀者や背後者などのような真に処罰すべき者を処罰することができるようになります。
- 企業が関係する財政経済犯罪の捜査にも適用され、社員の刑事処分の軽減等と引き換えに供述を引き出し、上層部や企業自体の刑事責任を追及することが可能となります。
- 供述者の協力が得られますから、事件の迅速な処理を図ることができます。捜査費用・裁判費用の面だけでなく、時間と労力の節約になります。
- 他人が自己の犯罪を供述するかもしれないということが心配になりますので、企業の経営者や事業主としては、これまでよりも一層租税犯罪(無申告、所得隠し、現金隠し、二重帳簿の作成、申告漏れ)などの撲滅や早期発見に向けて、コンプライアンス態勢を強化するようになります。
(2) デメリット
- 虚偽供述の可能性による冤罪が危惧されます。
- 被疑者・被告人が重罰を避けるため、あるいは自分の罪を軽くするために司法取引を行い、関係のない他人を巻き込んだり犯罪の役割の軽い者に罪をなすりつけるように偽証したりする可能性があります。
- 司法取引を行った被疑者・被告人は、虚偽供述罪を問われるのを避けるために、公判廷においても虚偽を貫こうとする動機が働くことが懸念されます。
- 被疑者・被告人が取調べから逃れたいため、虚偽の自白をする危険があります。
- 司法取引が多用されると、検察官の取調べは、他人の刑事事件を供述する者の捜査に集中することになり、客観的証拠の収集に基づく捜査がなおざりにならないか懸念されます。
- 被疑者・被告人は、刑の減免の特典を受けたいがため、捜査機関の誘惑に抗しきれず、黙秘権が侵害されるおそれがあります。
(3) 問題点
- 協力行為と減免行為とのバランスが問題になります。検察官との司法取引が自己に有利なのか不利なのかはっきりせず、捜査機関が多大な利益を得ながら、協力者に何の利益もないことがあり得ます。被疑者・被告人が、不利益を受ける可能性があると判断すれば、検察官からの見返りを意識して、事実を過大に供述することも考えられます。
- 自己の刑の減免が可能なら、とにかく取引しようとして、検察官と協議に入る被疑者・被告人が多くなることが予想されます。
- 末端の者の行為が軽微な犯罪であった場合でも、有力な情報を持っているとなれば、検察官は、司法取引に関心を持ち、これが高じると、精緻な捜査をせず、他人の自白に頼ろうとして、軽微な犯罪で逮捕し、刑の減免を慫慂することが危惧されます。
- 「司法取引を使えば、犯罪をしても罪が軽くなるから、犯罪を実行しよう」と思う人が増えて、犯罪が増加してしまう危険性が懸念されます。
- 刑を軽くしたいと考える末端の者が、あえて関連性を持たせようして虚偽供述をする可能性も出てきます。また、諸悪の根源は断つべしという正義感を持つ検察官がいますと、虚偽の供述を疑わなくなってしまうことも懸念されます。
5.まとめ
「司法取引」制度は、併せて導入される「刑事免責制度」(法157条の2・157条の3)とともに、取調べによる供述獲得に代わる新たな立証手段として、今後の運用が注目されます。
(参考:刑事免責制度について|日本における趣旨と概要)
しかし、2023年時点で適用された事件は「司法取引」が適用された事件は3件に止まり、今後の社会にどう根付いていくのかが注目されています。
刑事事件で逮捕され、起訴されそう・起訴されてしまったという方は、お早めに刑事事件に強い泉総合法律事務所の弁護士に相談してください。