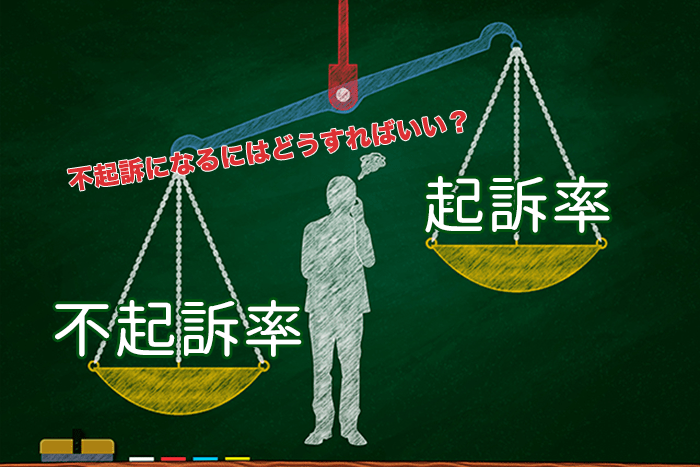日本の刑事裁判の起訴後有罪率99.9%は本当?検察の捜査力について

有罪率が極めて高いことは、我が国(日本)の刑事裁判の大きな特徴です。
2021年の司法統計年報によれば、第1審における有罪率は約96.3%に達しており、無罪は0.2%です(その他3.5%)。
このように、日本の刑事裁判は、約99.9%の有罪率を誇るものとして、時に「精密司法」と呼ばれます。
以下においては、日本における起訴率、検察の捜査能力、刑事裁判の現状などに触れながら、日本の有罪率はなぜ上記のように99.9%と高いのか、また、果たして冤罪はないのかについて、その理由を探っていきます。
1.日本の起訴率・有罪率の現状
少し前のデータですが、検察官の事件処理状況によれば、事件処理137万1,637人のうち、起訴されたのが27万1,459人(27.1%)、不起訴処分が73万9,937人(53.9%)となっています(残りは家裁送致等となっています。法務省刑事局「平成27年の検察事務の概況」)。
上記の統計から分かるのは、そもそも刑事犯罪を犯した被疑者が起訴されて裁判にまでなる刑事事件は3割未満であり、5割強の事件は不起訴になっていることです。
よって、「刑事事件で逮捕されたら99.9%有罪になる!」というわけではなく、半数以上が不起訴となり前科もついていないのです。
これは、日本の検察官が有罪が確実な事件を選んで起訴しているからです。
だからこそ、有罪率は99.9%と非常に高くなっているといえます。
2.刑事裁判の現状
(1) 検察の捜査能力
大多数の事件については、まず警察によって捜査が行われた上で事件が検察官に送致され、検察官は、警察による捜査の不十分と思われる点を補充し、また不適正と思われる点を補正するなどの目的で、更に必要な捜査を行った上で起訴・不起訴の処分を決します。
(しかし、大規模な脱税・会社法違反・贈収賄のように、複雑な法律問題を含み、あるいは政治にかかわる事件については、警察を通さず検察官が主体となって捜査が行われることがあります。)
検察官は、上述のとおり、有罪が確実な事件を選んで起訴しているのが実態といえます。証拠をよく見て、法律的な問題点を検討し、過去の裁判例も調べて、有罪が間違いないという事件に限って起訴するという手堅さがうかがわれます。
しかし、「見方を変えれば、起訴できるのに、捜査能力の低下と決裁官の自信のなさから、やむを得ず不起訴処分としているケースもある」と指摘する検察OBの方もいます(粂原研二元検察官(現弁護士):無罪事件に学ぶ捜査機関の劣化[元現場派検事からの伝言]―捜査能力の低下と決裁)。
とはいえ、現実には「精密起訴」であることに変わりがなく、確実な証拠があった上で起訴されるため、起訴されたら無罪を勝ち取ることは難しいというのが実態です(もちろん、否認事件で無罪判決が得られる可能性も0ではありません)。
(2) 冤罪はどれくらい発生するのか?
無罪とされるべきであるのに有罪判決を受けたままでいる人々は、実際にはどのくらい存在するのでしょうか。
このことは、次の諸点を考えますと、かなり存在するように思われます。
まず、裁判官が特に慎重な態度で取り組んだはずの死刑・長期懲役刑の事件ですら、後日に新証拠が発見されて再審無罪になったケースがかなりあります。
(このような重罪事件では、人は必死になって冤罪を訴えますが、軽罪事件ではそのような訴えをしない人が多いでしょう。)
また、重罪事件では再審が開始された経過を見ますと、「偶々真犯人が名乗り出た」「特別に熱心な弁護人や支援者などの協力があった」「有利な新しい鑑定が出現した」というような多分に偶然的・幸運な要因に依存している場合がほとんどでした。しかし、軽罪事件はいうまでもなく重罪事件であってもそのような要因には滅多に恵まれないため、冤罪を晴らすことができないでいる人々は決して稀ではないように思われます。
そして、現実的にも、罰金や執行猶予で終わった場合、裁判では時間と費用がかかるため、更に上訴してまで争うのを諦めてしまう人もいるといわれています。
また、司法統計年報によれば、無罪率は、昭和40年代後半が約0.6%(有罪率約99.4%)であったのが、昭和63年には0.12%(有罪率99.88%)であり、平成26年頃も同程度となっています。
このような無罪率低迷の陰には、かなりの数の冤罪者が存在するように思われます。
そして、裁判官による無罪の言い渡し率に顕著な差異があることは、従来から指摘されているところです。
ここで、裁判官が裁判に臨む姿勢や気持ちの持ち方に関し、著名な木谷明元裁判官の考え方を紹介することにします。
木谷元裁判官は「自分が裁判長を任されるようになった段階では、『被告人の言い分を十分に聴く』、『その弁解を粗末にしない』、『真実は誰にもわからないが被告人だけは知っている。』だから、『事件の真相は法廷で被告人が言っているとおりなのではないか』という頭で、検察官提出の証拠を徹底的に分析し、『少しでも疑問があれば積極的に証拠調べを行う』という方針で裁判をするようになった。そして、そういう方針で審理をしてみると、当初まさかと思った弁解が本当らしく思われてきて無罪判決に至る、という事例がいくつも出てきた。」旨述べています(「法律家の仕事は面白いか」青山法務研究論集第7号[2013年〔平成25年〕]59頁)。
さらに、木谷元裁判官は、刑事裁判官は「起訴された以上被告人は有罪である、被告人は法廷では罪を免れようとして嘘をつくが、捜査官は嘘をつかないと思い込んでいる『頑迷な迷信型』」、「よくよく考えてきっちり自分の考えを断行する『熟慮・断行型』」、「迷信型ではないが、時に被告人の弁解が真実ではないかと考えるのですが、決断力が弱い、優柔不断で、あちこち様子を窺っているうちに、決断できなくなって、結局検察官の意見通りに判決する『優柔不断・右顧左眄(うこさべん)型』」の3つのタイプに分類できるとし、「頑迷な迷信型」が約3割、木谷元裁判官自身を含む「熟慮・断行型」が約1割、「優柔不断・右顧左眄型」が残りの約6割と考えている旨述べています(同論集67頁~68頁)。
木谷元裁判官の言を借りれば、冤罪を減らすために、有罪率を支える裁判官側の意識改革も必要といえましょう。
3.逮捕~裁判までの流れ
最後に、刑事事件で逮捕されてから、有罪・無罪を決める刑事裁判になるまでの流れをご紹介します。
有罪を避けるためにも、逮捕されてしまったのならば、なるべく早い段階で弁護士へ刑事弁護を依頼しましょう。
(1) 刑事手続の流れ
刑事事件で逮捕された被疑者は、通常、逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。
検察官は、「証拠隠滅の恐れがある」「逃亡の恐れがある」などの事情があれば、被疑者を受け取ってから24時間以内に裁判官に対しより長期の身体拘束を求める勾留の請求をします。(被疑者は逮捕から勾留の請求まで、最大72時間拘束されて自由を制限されます)。
裁判官は、検察官から勾留の請求があると「勾留質問」を行って、その当否を審査します。
通常は、被疑者が罪を犯した疑いがあり、住居不定である、証隠滅のおそれ又は逃亡の恐れがあるなどの事情があり、捜査を進める上で身柄の拘束が必要と認められるならば、被疑者の勾留を認めます。
なお、勾留期間は原則10日間ですが、事案が複雑、共犯事件、証拠収集が困難など、やむを得ない場合には更に10日間以内の延長が認められることもあります。
そして、検察官は、捜査の結果を踏まえ、通常、勾留満期(最大20日間)までに、被疑者を不起訴処分にするか、起訴するかを決めます。
起訴(公訴提起)された場合は裁判(あるいは略式裁判)となりますが、その結果としては、罰金・執行猶予付・保護観察付執行猶予・実刑・無罪といった判決が考えられます。
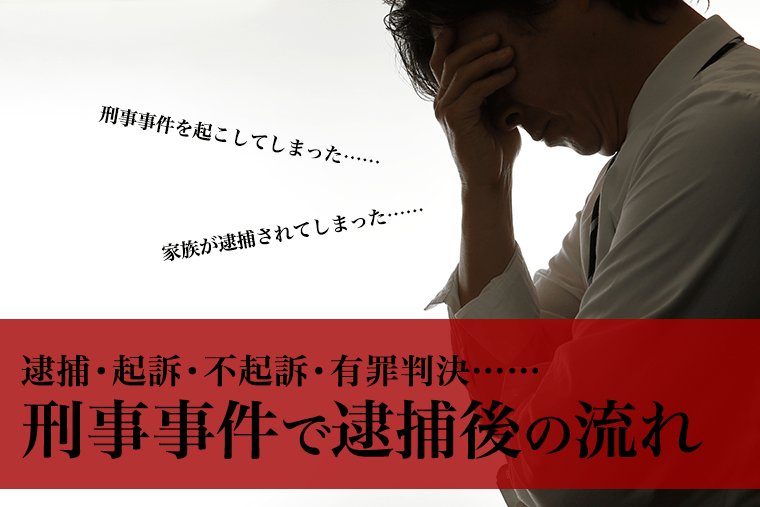
[参考記事]
逮捕から起訴・不起訴の決定までの流れ
(2) 検察官の起訴・不起訴決定の基準
検察官は、起訴・不起訴の決定に当たり、その判断の基準とすべき事項として、刑訴法は「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を掲げています。これらにより訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(=不起訴にできる)と定めています(248条)。
その判断の基準とすべき事項は、大別すると、①犯人に関する事項、②犯罪自体に関する事項、③犯罪後の情況に関する事項の3種になります。
具体的に見てみますと、以下の通りです。
- ①犯人に関する事項:素行、性癖、知的能力、生活史、健康状態、前科・前歴の有無、犯行時及び現在の年齢、家庭環境、職業、交友関係など、広い意味で犯人の性格・年齢・環境に含まれる事項
- ②犯罪自体に関する事項:法定刑の軽重、被害の大小、加重減軽事由の有無、共犯の有無、犯行の動機、方法、犯罪による利得の程度、被害者との関係、犯罪の社会的影響など、いわゆる犯罪の軽重及び情状に当たる事項
- ③犯罪後の情況に関する事項:改悛の情の有無、被害の回復や謝罪の努力、示談の成否、時間の経過、社会情況の推移、法令の改廃、犯人の生活状況、身許引受人の有無など、まさに犯罪後の情況に関する事項
検察官は、これら諸般の事情を考慮して、起訴か起訴猶予かを決定することになります。
しかし、これらすべてが考慮されるわけではありません。罪種によって重点の置き所が異なってきます。
例えば、窃盗・詐欺などの財産犯では、犯行の手口、被害額、犯行の回数、動機、被害弁償の有無。傷害などの人身犯では、傷害の部位・程度、犯行の態様・凶器の有無、被害者側の誘発の有無、被害者の宥恕の有無など、これらの要素を中心に訴追の要否が決せられているといわれています。
そして、事案によっては、被害者との示談の成否が起訴・不起訴の決め手になるといえます。

[参考記事]
刑事事件の示談の意義・効果、流れ、タイミング、費用などを解説
4.刑事事件を起こしてしまったら早めの弁護依頼を
我が国の刑事裁判の有罪率が高いのは、一般論としては、確実に有罪となるような事件のみ起訴され、後は不起訴となるよう事件がふるいにかけられているためといえます。
そうは言っても、現実問題としては、裁判になり前科がつかないように、刑事事件を起こしてしまった場合は早めに刑事事件に精通している弁護士に相談するべきでしょう。
刑事事件で逮捕されて困っているという方やそのご家族は、刑事事件の弁護経験が豊富な泉総合法律事務所に是非一度ご相談ください。