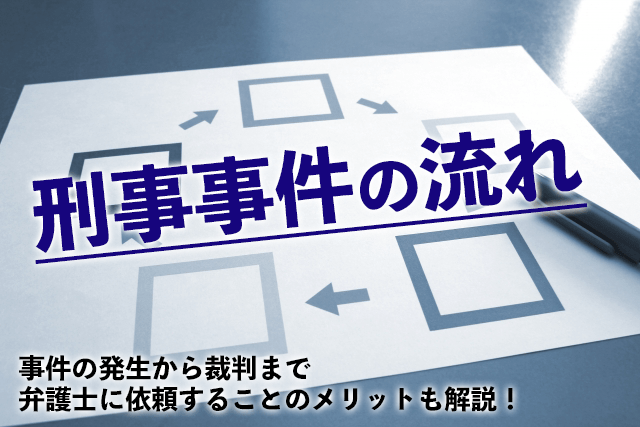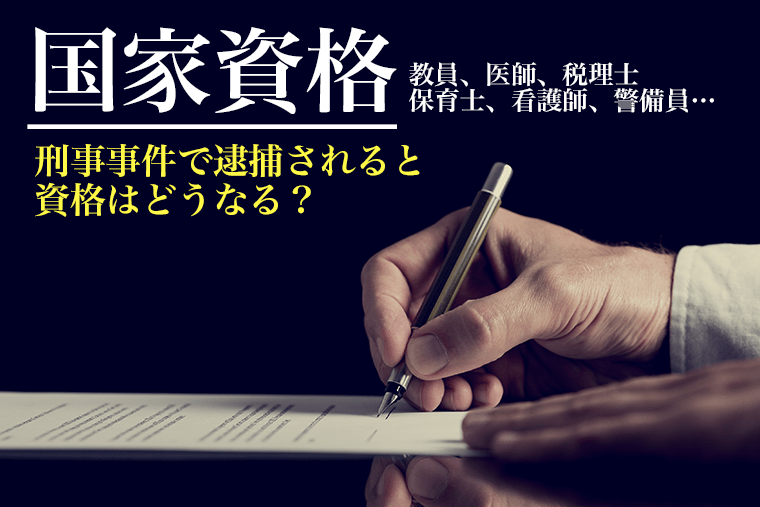略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い

刑事事件で検察官に起訴される場合に、「略式命令請求」が行われる場合があります。
この請求を受けた裁判所は、「略式手続」という書面により簡略化された裁判手続を行ったうえ、「略式命令」で罰金・科料の刑を下します。
すなわち、「略式起訴」とは、正式な裁判という手続きを省略する起訴手続きで、これを受けた被疑者は100万円以下の罰金または科料の刑罰となります。
罰金・科料でも前科となるため、刑事事件ではそもそも起訴を回避することが重要です。
しかし、起訴を免れないような案件では、正式裁判を避けて略式起訴(罰金刑)を目指すことが重要になります。
この記事では「略式起訴(略式裁判)」についてわかりやすく解説します。
1.起訴の種類
起訴とは、検察官が裁判所に対して、被疑者を裁判にかけて処罰してほしいと要求することです。
これに対して不起訴(不起訴処分)とは、いわゆる「お咎めなし」で、その事件について起訴せず終結させると検察官が判断することです。
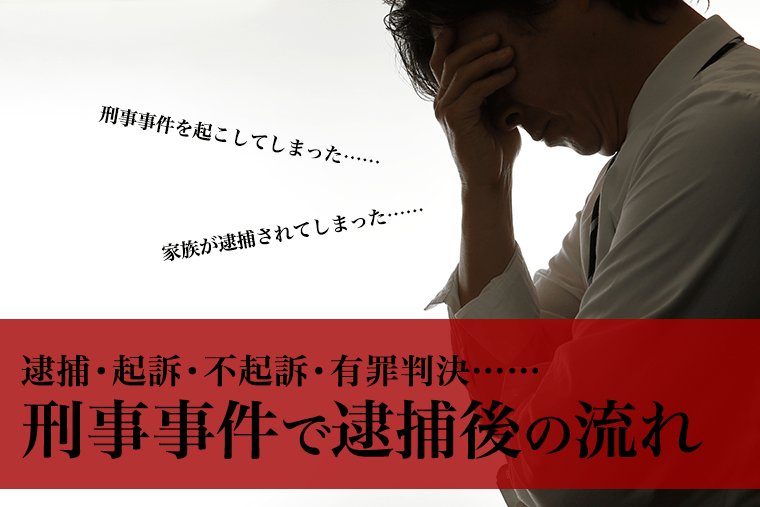
[参考記事]
逮捕から起訴・不起訴の決定までの流れ
検察官が裁判所に対して求める刑事裁判には、①正式裁判、②略式手続、③即決裁判手続という3つの手続が用意されています。
これに対応して、検察官の起訴にも、①公判請求、②略式命令請求、③即決裁判請求という3種類があります。
(1) 正式裁判を求める「公判請求」
正式裁判とは、公開の法廷で厳格な手続に従って行われる裁判です。
テレビドラマや映画でおなじみの刑事裁判シーンを思い浮かべていただければ間違いありません。
検察官が被疑者を正式裁判にかけるよう裁判所に求めることを「公判請求」と呼びます。これが原則的な裁判の方式です。
一般的に、単に「起訴」という場合は、公判請求のことを指しています。
(2) 略式手続を求める「略式命令請求」
略式手続とは、検察官の請求を受けた簡易裁判所が、公判を開かず、書面審理だけで100万円以下の罰金または科料の刑罰を被告人に課す裁判手続です。
検察官が簡易裁判所に対し、略式命令を求めることが「略式命令請求」です。
この「略式命令請求」は、検察官が被疑者を簡易裁判所に起訴すると同時に略式命令にしてほしいと請求するもので、俗称として「略式起訴」とも呼ばれています。
正式裁判は、被告人にとっては公開法廷に出廷する肉体的・精神的な負担が大きく、検察庁・裁判所にとっても、人的・物的・時間的に多大なコストがかかる手続です。
そこで、罰金または科料が相当な事案で、被告人自身が簡略な手続での裁判に異議がなければ、あえて公判を開くことなく事件を処理した方が望ましいと言え、略式手続は、このような実際上の要請に応じた制度です。
とはいっても、略式起訴は起訴の一種なので、略式起訴で有罪判決(罰金・科料)が出されれば前科がつくことに変わりありません。
略式手続とすることができるのは、次の3つの条件を満たす場合です。
- 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- 100万円以下の罰金または科料を科すことができる事件であること
- 略式手続によることにつき、被疑者に異議がないこと
(3) 即決裁判手続を求める「即決裁判請求」
即決裁判手続とは、明白かつ軽微な事案について、被疑者の同意を条件として、早期に開廷される公判期日において、簡略・効率化した証拠調べ手続を行い、即日に、罰金刑または執行猶予付き自由刑(懲役刑・禁錮刑)を言い渡す裁判手続です(350条の16)。
この手続も、事件処理の効率化を図ることで、正式裁判の厳格な手続による被告人・検察庁・裁判所の負担を軽減するための制度です。
2.略式手続の流れ
ここからは上記(2)の略式手続きの流れについて見ていきましょう。
(1) 被疑者の同意を得る
検察官が略式手続相当と判断したときは、略式命令請求をする前に、被疑者に対して、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し(正式裁判を受けることもできると告げた上で)、略式手続を受けることに異議がないかどうかを確認しなければなりません(刑訴法461条1項)。
略式手続に異議がない被疑者は、検察官から告知説明を受けたことを明らかにする「告知手続書」と、異議はない旨を申し出る「申述書」が一体となった通称「略式請書」に署名・指印をします(刑訴法461条の2)。
(2) 起訴状の提出
検察官は、起訴状に「略式命令を請求する」との記載をしたうえで、簡易裁判所に起訴状、略式請書、その他証拠物などを提出することで、起訴と同時に略式命令請求を行います(462条)。
実務では、この場合の起訴状を「略式命令請求書」とよんでいます。
また、実務では罰金・科料の金額などについて検察官の意見を記載した「科刑意見書」も提出しています。正式裁判の「求刑」に相応するものです。
(3) 簡易裁判所の審理
略式命令請求を受けた裁判所は、検察官が提出した資料を調査、審理して略式命令を発します。
遅くとも検察官が略式命令請求をした日から14日以内に略式命令を発しなくてはなりません(刑事訴訟規則290条1項)。
3.略式命令ができないケース
次の場合には、裁判所は略式命令を出すことはできず、通常の規定にしたがった裁判手続を行わなくてはなりません(463条1項、2項)。
- 略式命令の要件を満たさないとき
- 略式命令の手続が規定に違反しているとき
- 略式命令をすることが相当でないと思料するとき
(1) 略式命令の要件を満たさないとき
例としては、次のような場合です。
- 罰金・科料の定めのない罪だったとき
- 検察官の提出した証拠では不十分で無罪を言い渡すべきとき
- 公訴時効が完成していて、免訴の判決を言い渡すべきとき
いずれも実務的には検察官のミスと言えましょう。
特に略式命令では、裁判所は100万円以下の罰金・科料以外の判決を出すことはできませんから、これと異なる有罪判決や無罪、免訴、公訴棄却などの判決が必要な場合は、正式裁判を行う他ないです。
(2) 略式命令の手続が規定に違反しているとき
例としては、次のような場合です。
- 被疑者に対して、検察官からの略式手続に関する告知説明がなかったとき
- 被告人の「略式請書」が提出されていないとき
これも実務的には明らかな検察官のミスです。
(3) 略式命令をすることが相当でないと思料するとき
例としては、次のような場合です。
- 事案が極めて複雑な事件
- 検察官の主張する犯罪事実の記載(「訴因」と言います)の変更や追加が必要と判断されるとき
- 100万円以下の罰金・科料で処理するのは相当でないと判断されるとき
- 検察官の科刑意見書の内容と著しく異なる量刑が相当と判断したとき
これらは検察官のミスではなく、事件に対する検察官と裁判官の意見が相違した場合と言えます。
例えば、2017年7月、大手広告代理店の電通が社員に違法残業をさせていた労働基準法違反事件で、検察官からの略式命令請求を受けた東京簡易裁判所が、略式命令は不相当と判断して、正式裁判の開廷を決めたことが話題になりました(※)。
検察官は略式命令が相当と判断したのに対し、裁判所からは社員が過労で自殺するという結果の重大性や社会的な関心の高さから、略式命令にはふさわしくないと判断されたものと思われます。
※2017年7月12日産経ニュース「電通違法残業事件、正式裁判に 東京簡裁『略式不相当』」
法文上は、「被告人が犯罪事実を認めていること」は略式命令の条件とはなっていません。そこで、被告人が略式手続には同意しているものの、犯罪事実自体は否認している場合には、「略式命令をすることが相当でない」場合にあたるか否か議論があります。
一方では、被告人が争う姿勢を示している以上は、公判廷で正式裁判を行うことが相当であるという主張があります(※1)。他方では、否認のために事実認定が困難な事件については正式裁判を行うべきだが、単に「酔っ払って覚えていない」というだけで、検察官の提出した資料から明らかに犯罪事実が認められる事案にまで略式命令が相当でないとするべきではないという主張もあります(※2)。
実務では、被告人が否認していても、略式手続に異議がないなら、そのまま略式命令を発している例が多いとされています(※3)。
※1:田宮裕「刑事訴訟法(新版)」(有斐閣)413頁
※2:「新基本法コンメンタール刑事訴訟法(第3版)」(日本評論社)693頁
※3:「基本法コンメンタール刑事訴訟法(新版)」(日本評論社)380頁
4.略式命令に不服がある場合
被告人や検察官は、略式命令で出された罰金額等に不服があるときは、その告知を受けた日(つまり略式命令謄本を受け取った日)から告知の日の翌日を含めて14日以内であれば、正式裁判を開くことを請求することができます(465条1項)。
正式裁判の請求は、略式命令をした簡易裁判所に対して書面で請求する必要があります(465条2項)。理由を書面に記載する必要はありません。
正式裁判の請求がなされたときは、あらためて法廷での公判期日が指定され、通常の裁判が開始されることになります。
略式命令が出されると、被告人は罰金・科料を納付しなければなりません。罰金・科料を払えないときは、刑事施設内の労役場で強制的に働かなくてはなりません。これを「労役場留置」と言います(刑法18条1項)。
裁判官が罰金・科料の刑を言い渡すときには、必ず支払えなかった場合の労役場留置の期間を定めて言い渡さなくてはなりません(刑法18条4項)。その期間は、法定の範囲内(罰金は2年以下、科料は30日以下)で、裁判官の裁量で決められますが、実務では1日5000円で計算する例が多いとされています。
5.不起訴に向けて泉総合法律事務所にご相談を
略式命令は被告人にとっても出廷の負担がなく、早期に結論が出され、罰金・科料で済むことから、検察官から「略式命令で済ませる」と話を向けられると、ほとんどの被疑者はほっとするでしょう。
しかし、罰金も科料も刑罰であり、略式命令は有罪判決ですから、前科となることを忘れてはいけません。不起訴処分を勝ちとることを第1に目指すべきなのです。
そのためには弁護士の力が必要です。
泉総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護経験が豊富にあり、多くの案件で不起訴処分を獲得しています。まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

[参考記事]
刑事事件・刑事裁判における弁護士の役割