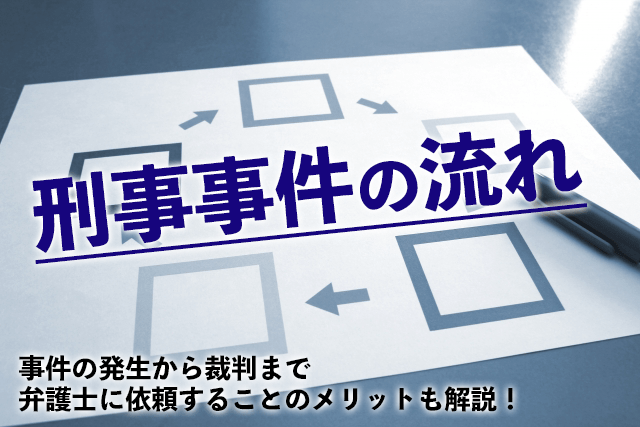逮捕から起訴・不起訴の決定までの流れ
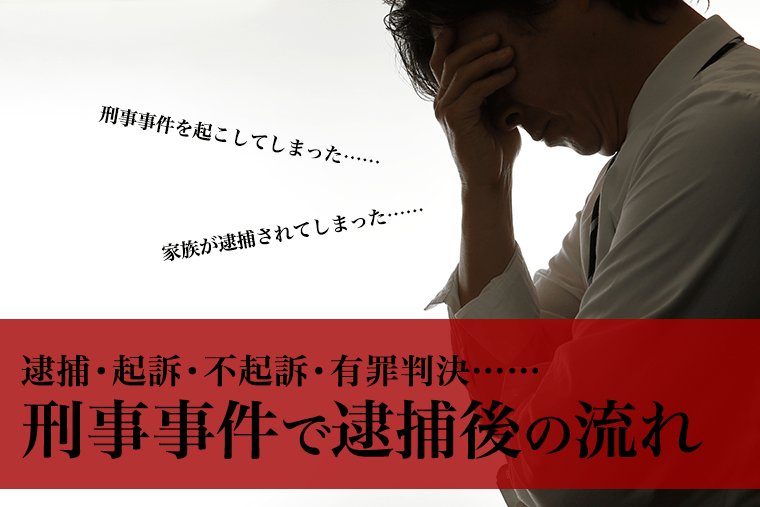
日常生活において刑事事件に関わることは滅多にありません。
しかし、「魔が差して痴漢をしてしまった」「酔った勢いで暴行事件を起こしてしまった」など、ある日突然刑事事件の犯人となってしまう可能性は0ではありません。
刑事事件について何の知識もないまま警察官に現行犯逮捕されてしまうような事案では、不安でパニックに陥ってしまうことも考えられます。
今回は、万が一刑事事件に関わってしまった場合・ご家族・ご友人が逮捕されてしまった場合に備え、逮捕から起訴・不起訴の決定までの身柄事件の流れ、早期釈放や不起訴を獲得するために必要となる弁護活動の概要について解説します。
1.刑事事件の起訴・不起訴決定までの流れ
刑事事件は、被疑者の身体の拘束の有無を基準として「身柄事件」と「在宅事件」に区別されます。
身柄事件とは、文字通り、被疑者の身体を逮捕状により通常逮捕するなどし、留置場などに拘束した状態において取調べ等を進める刑事事件のことです。
在宅事件とは、被疑者の身体を拘束しない状態において捜査を進める刑事事件のことです。
ここでは、身柄事件のケースについて詳しく説明します。
在宅事件について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。
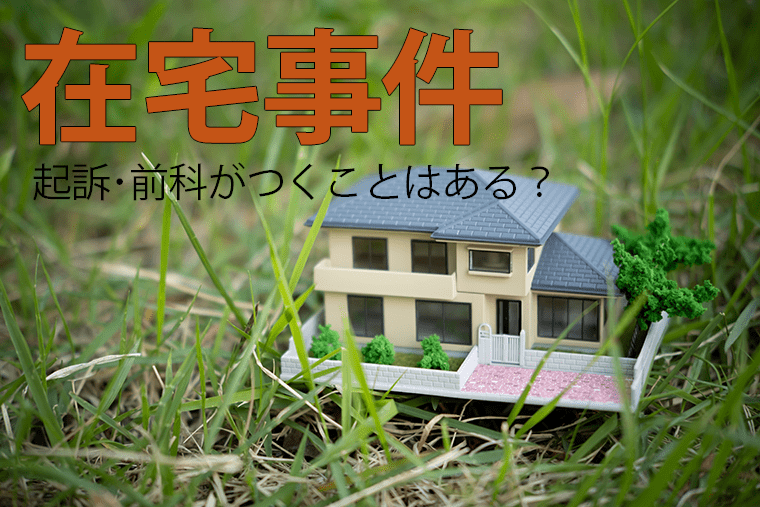
[参考記事]
在宅事件の流れ|起訴・前科がつくことはあるのか
(1) 起訴前の身柄拘束
犯罪が発生すると、捜査機関は被疑者を身体拘束して捜査を進める場合があります。起訴前の身柄拘束は、「逮捕」と「勾留」に分けられます。
①逮捕
逮捕は「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」(刑事訴訟法199条2項)とき、逃亡・証拠隠滅のおそれがあるなどの必要性の認められる場合に行われる身柄拘束です。よく行われる逮捕は、犯行現場を押さえられる現行犯逮捕、逮捕令状により行う通常逮捕(後日逮捕)です。
逮捕は上記要件を充足した場合に行われるものなので、なんでもかんでも事件があれば被疑者を逮捕するというわけではありません。
しかし、犯行を否認している場合、殺人・強盗などの重大犯罪の場合、証拠隠滅される可能性が高い薬物事件の場合などには、逮捕されてしまうケースが多いでしょう。
一方で、痴漢や盗撮・万引きなど、比較的軽微な犯罪で、罪を認めていて逃亡のおそれもないと判断されれば、たとえ犯行現場を押さえられても、逮捕されずにその場で帰されることもあります。
②勾留
警察に逮捕された場合には、微罪処分(検察官送致がされない事件)にならない限り、逮捕から48時間以内に事件の捜査書類と身柄は検察官に送致されます(検察官送致)

[参考記事]
微罪処分になる要件とは?呼び出しはあるのか、前歴はつくか
そして、検察官が引き続き身柄を拘束する必要性があると判断したときは、送検後24時間以内かつ逮捕から72時間以内に裁判所へ「勾留請求」します。
検察官の勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面会して話を聞きます。これを「勾留質問」といいます。
裁判所は、勾留質問の結果と、検察官から提出された証拠資料に基づき、勾留請求に対する判断を下します(刑事訴訟法60条1項、同207条1項)。
勾留の要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり(刑事訴訟法60条1項柱書)、かつ、以下のうちどれかに該当することです。
- 住居不定(同項1号)
- 罪証隠滅の恐れ(同項2号)
- 逃亡の恐れ(同項3号)
逮捕と同様に、事件があれば必ず勾留をするというわけではなく、必要がある場合に限り行われます。
勾留請求を認める決定をした場合、原則として、被疑者は勾留請求の日から10日間身柄を拘束されます。これを「起訴前勾留」または「被疑者勾留」と呼びます。

[参考記事]
逮捕後の勾留の要件とは?勾留の必要性を否定して釈放を目指す
検察官は、10日間の勾留の期限を超えて被疑者の身柄を拘束する必要があると判断した場合、裁判官に対して「勾留の延長」を請求します。
勾留延長請求を受けた裁判官は、やむを得ない事由があると認める場合に限り、最大10日間までの勾留延長を決定することができます(刑事訴訟法208条2項)。したがって、起訴前勾留は最大で20日間続きます。

[参考記事]
勾留期間が延長された場合の対処法
勾留延長を含めれば、被疑者は逮捕後最長で23日間身柄を拘束されることになります。
(2) 起訴後の身柄拘束
在宅事件では必要な捜査が終わった段階、身柄事件では起訴前勾留の期限前の段階で、検察官により起訴処分・不起訴処分の判断がされます。
起訴をするとなった場合、検察官は「略式命令請求」か「公判請求」を選択します(「即決裁判請求」もありますが、実務上の数は少ないので割愛します)。
略式命令請求(略式起訴)は、検察官が簡易裁判所に対し、公開の法廷ではなく、書類上の手続だけで裁判を行って罰金または科料を命ずる「略式命令」を求めるものです。裁判所が略式命令を行うには、被告人の同意が必要となります。

[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
他方、検察官が裁判所に対し、公開法廷での刑事裁判を開いて厳格な手続のもとに審理を行い、刑罰を科すことを求めるのが公判請求です。

[参考記事]
公判請求とは?略式請求との違い・公判を避ける方法
この場合、起訴前に勾留されている者は自動的に起訴後の勾留に切り替わり(刑事訴訟法60条2項)、被疑者から「被告人」という名称に変わります。
保釈が認められなければ、少なくとも刑事裁判が終わるまで身体拘束されることになるので、弁護士に依頼して保釈請求を行う必要があります(詳しくは後述)。
一方、不起訴となれば釈放されますから、早期の社会復帰が可能になり、社会的な不利益を最小限にとどめることができます。
裁判に必要な時間と労力からも解放されることになるでしょう。
2.身柄事件の弁護活動
身柄事件における弁護活動の基本は、「早期の身柄解放」と「可能な限り有利な処分(不起訴など)を獲得する」ことの2つです。
(1) 身柄解放のための弁護活動
刑事事件における身柄の拘束は法律に基づく処遇ですから、弁護士は法律の要件を満たさない身柄拘束について不服申立することができます。
また、裁判所に身柄の拘束を求めるか否かの判断は捜査機関の裁量であり、法の要件を満たすか否かの認定は裁判所の裁量に委ねられていますから、早期の身柄解放のため、捜査機関や裁判所を説得することも大切になります。
①起訴前の釈放
起訴前の身柄拘束は、先でご説明した通り「逮捕」と「勾留」になります。
このうち、逮捕については、現在の法律では不服申立の制度は用意されていません。逮捕の適法性は、勾留請求の適否を判断する際に、まとめて審査対象とされていると理解されています。
そこで、弁護士としては、検察官や裁判所に対して「勾留請求しない」あるいは「勾留請求を却下する」よう説得します。
その際には、身柄引受人の存在・学校や仕事の存在・被害者との示談など、前述した勾留の要件が存在しないことを示す具体的な事実を主張します。
もし、勾留を認められてしまった場合には、裁判所に対してその判断の誤りを主張して、勾留の決定の取消を求めることができます(これを準抗告といいます)。

[参考記事]
勾留請求・準抗告とは?釈放を目指すなら泉総合法律事務所へ!
勾留延長についての弁護活動は、基本的に勾留を阻止するための弁護活動と同様です。
②起訴後の釈放
起訴後の勾留に対する身柄解放のための弁護活動は「保釈請求」です。
保釈は、一定条件を満たすことと、一定額の保釈保証金(保釈金)の納付により、被告人の身柄を解放する制度です。
保釈保証金の金額は、保釈を許可する裁判所の裁量により決められます。
事件の内容や被告人の社会的地位、資力などにより幅はあるものの、一般的には最低でも150万円~200万円を目安にされています。
なお、保釈保証金の額については裁判官と交渉する余地があり、交渉して捻出可能な範囲内に抑えることも弁護士の仕事のひとつです。

[参考記事]
保釈に強い弁護士|弁護士に依頼する場合と依頼しない場合の違い
(2) 可能な限り有利な処分を獲得
弁護士は、最終的に刑罰を科せられてしまうのか、科せられるとしてどのような内容の刑罰を科せられるのか、という点について、可能な限り有利な結果を導くための弁護活動も行います。
捜査段階における弁護人の最大の目標は、不起訴(起訴猶予)を獲得することです。
不起訴となった場合には釈放となり、刑罰を科せられるという不利益を免れる上、前科が付くことを回避できます。
起訴・不起訴を判断するのは検察官です。弁護人は検察官に対して、示談の成立による被害者感情の緩和、被疑者の反省などの事情から刑罰を科す必要性のないことを意見書により伝えます。
起訴され有罪判決は免れないような事件の場合でも、条件を満たすなら、略式起訴による罰金刑に留めるよう求めます。
一方、公判請求となった場合には、裁判での審理を経て有罪・無罪の判断と科すべき刑の内容が判断されます。
この場合の弁護人は、被告人本人と綿密な打ち合わせを行い、裁判においてどのような方針で弁護活動すべきか決めます。
罪を犯したこと自体は争わない自白事件では、執行猶予の獲得、懲役刑を回避し軽い罰金刑の獲得を目指します。
そのために、示談を成立させて示談書を提出したり、情状証人として被告人の家族を出廷させて、今後の指導監督を誓約する旨を証言してもらったりします。

[参考記事]
刑事事件の示談の意義・効果、流れ、タイミング、費用などを解説
また、被告人が反省状況を的確に裁判所に伝えられるよう、被告人質問での質問内容や回答内容についてよく打ち合わせをします。
一方、無罪を主張するような否認事件では、証拠によって犯罪事実を立証する責任は検察官にあるので、弁護人が積極的に被告人の無罪を証明する必要はなく、「検察官が主張する事実が立証されていない」という状況を作ることが目標となります。
3.まとめ
「早期の身柄解放」と「可能な限り有利な処分を獲得する」という2つの目標を実現するためには、弁護士が刑事事件に関する法律に精通していることに加え、検察官や裁判官を説得するための具体的事実を掘り起こし、その証拠を迅速かつ確実に収集・呈示する能力が必要になります。
こうした弁護活動は、刑事事件に精通している弁護士とそうでない弁護士とでは、その結果にかなりの差が出てきます。
もし、自分や知人・家族が刑事事件に関わってしまったときには、是非、刑事事件に精通した泉総合法律事務所の弁護士に私選弁護を依頼することを検討してみてください。無料相談も実施しております。