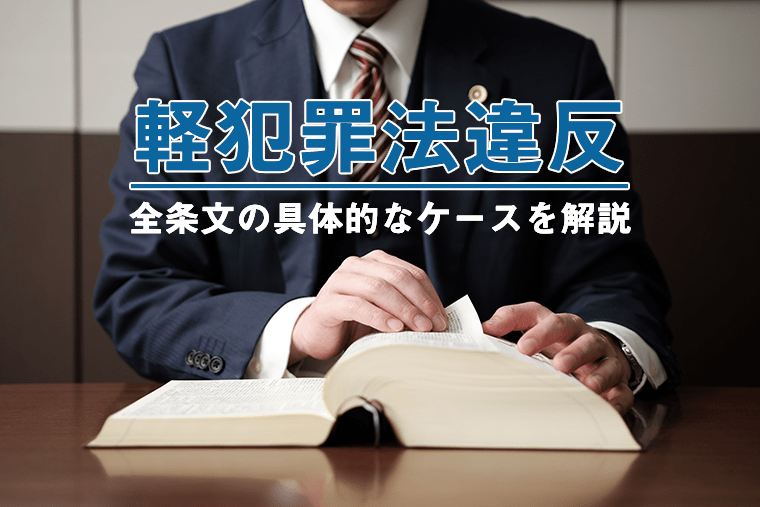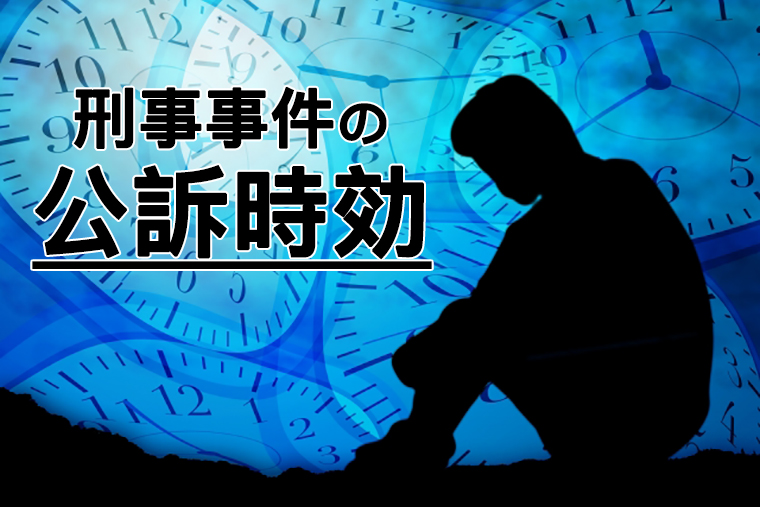刑事裁判に呼ばれる情状証人とは?どんな役割で何を証言すればいいか

自分の周りで犯罪を犯した方がいたとして、起訴・正式裁判となった場合、「情状証人」として出廷を頼まれることがあります。
刑事裁判では、①被告人が検察官の起訴した事実を犯したかどうか、つまり、有罪か無罪か、及び②有罪の場合、被告人に対してどのような刑罰を科すかということについて判断されます。
情状証人というのは、このうち後者に関係してきます。
このコラムでは、情状証人について詳しく説明していきます。
1.情状証人とは?
情状証人とは、起訴された事実を認めている被告人について、再度罪を犯さないようにきちんと監督することを裁判官の前で証言する人のことを言います。
被告人が自分の犯した罪について認めている場合、被告人は、なるべく刑罰を軽くしたり、執行猶予がつくような判決を求めたりすることになります。
裁判所は、被告人の反省の態度や、裁判が終わった後に実社会の中で更生させていくことが適当かどうか、再び犯罪を行う可能性(再犯可能性)がないかなども踏まえて刑罰の内容を決めます。
そこで、被告人の弁護人は、情状証人に裁判所に出廷してもらい、裁判官の前できちんと被告人の監督を行うという内容を話してもらうことを考えるのです。
情状証人は、今後、被告人が再び罪を犯さないよう監督することに適している人に頼まれます。
例えば、同居の親族、親しい友人、勤務先の上司や社長など、その被告人にとって最適な人にお願いすることになります。
2.情状証人が行うこと
(1) 書面の作成
情状証人は、被告人との従前の関係や今後の監督方針等をまとめた書面を作成します。そして、その書面を証拠として裁判所に提出し、取り調べてもらいます。
この書面は、弁護人が事情を聴取して下書きを作成してくれることがほとんどです。よって、情状証人は弁護人の事務所等でその事情聴取に協力するだけで十分です。
(2) 裁判期日の出廷
しかし、上記のような書面だけでは裁判所へのアピールとして十分でない場合もあります。そのような場合、実際に裁判所に赴いてもらい、検察官や裁判官のいる前できちんと話をすることで十分なアピールをすることができます。
情状証人は、刑事裁判の期日に裁判所に出廷します。そして、証言台で、弁護人や検察官、さらに裁判官から「本当に監督していけるのか」「監督するためにどういったことをするか」などの質問がなされます。そのような質問に対して、裁判官の方向を見て証言することになります。
もっとも、事前に弁護人からどのような内容の質問がなされるかといったことや、どのような回答をすればいいか等について、綿密な打ち合わせがなされることがほとんどですので、いきなり裁判所で発言するということは滅多にありません。
また、一人の被告人に対して複数人の情状証人から話を聞くことは裁判所も負担ですので、通常、情状証人は一人で、その他の方は書面の作成だけで終わります。
3.刑事裁判で不安になったら泉総合法律事務所へ
このように、自分の身の回りに刑事犯罪を犯し正式裁判となった人がいる場合、その人の弁護人から「情状証人となってもらえないか?」と頼まれる場合があります。
そのような場合、被告人とのこれまでの関係を考えて、ぜひとも被告人のために情状証人としてご協力されてみてはいかがでしょうか。
一方、あなたやその家族が刑事事件で逮捕されてしまったら、場合によっては起訴されて刑事裁判となってしまうかもしれません。
起訴されてしまった場合、日本の刑事裁判の有罪率は約99%と言われています。
泉総合法律事務所では、たとえ起訴されてしまっても執行猶予付きの判決を目指すなど、被疑者・被告人の方の弁護活動に最後まで全力で取り組んでおります。刑事弁護は、是非ともお早めに泉総合法律事務所にご相談ください。