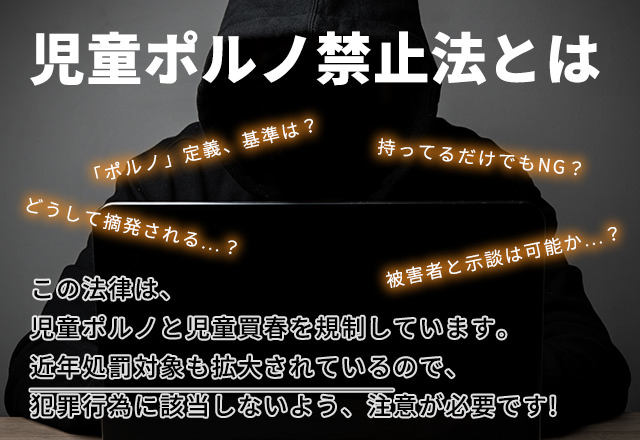家出をかくまうのは罪?未成年の略取と誘拐(刑法)

「未成年の家出少女を、少女の同意の上で自宅に泊めた」
「劣悪な家庭環境にあるらしい少女が家を出て行くと言うので、自宅でかくまうことにした」
最近では、ほとんどの未成年者が携帯電話を持つようになったこともあり、このような「家出少女に協力してかくまう」「親の同意を得ずして未成年者を自宅に住まわせる」といった事案が多く発生しています。
このような場合、「少女の同意がある」「家出をした後で危険な状態になることを回避した」ということで、連れ込んだ本人は罪に問われないのではないか?と思われがちです。
しかし、このようなケースでも、「未成年の略取・誘拐」という、刑法上の犯罪に該当します。
この記事では、未成年者の略取・誘拐の罪について、様々なケースに分けて解説します。
※以下の説明では、略取と誘拐とを併せて「拐取」といい、その罪を「拐取罪」といいます。
1.未成年者の「略取」「誘拐」とは?
(1) 略取、誘拐の定義
刑法第33章では、「人を従来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力的支配下に移す犯罪」を処罰する「略取、誘拐及び人身売買の罪」として、未成年者拐取罪など多数の罪を規定しています。
「略取」も「誘拐」も、共に、他人を従来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力的支配下に移すことです。
そして、「略取」は暴行・脅迫を手段とするのに対し、「誘拐」は欺罔・誘惑を手段とするものです。
これらの手段は、必ずしも未成年者自身に対して加えられる必要はなく、その保護監督者に対して加えられてもよいとされています(大判大13.6.19刑集3・502)。
なお、通説及び判例(大判大12.12.3刑集2・915)は、略取・誘拐は未成年者を場所的に移転させることを要するとしていますが、保護者を立ち去らせることによっても可能であるとしています。
(2) 同意がある場合は「略取」「誘拐」になる?
未成年者の略取、誘拐の罪の保護法益については、未成年者の自由のほか、保護者の監護権も含まれるとする説が通説です(大判明43.9.30刑録16・1569)。
よって、例え未成年者の同意があったとしても、未成年者を自宅に連れ込む行為は「保護者の監護権」を侵害することになるため、刑法上の犯罪が成立します。
犯罪が成立しないためには、未成年およびその保護者双方からの同意がなければいけません。
2.未成年者の略取・誘拐に関する罪の種類
(1) 未成年者拐取罪(刑法224条)
未成年者を略取又は誘拐することによって成立します。
処罰としては、3月以上7年以下の懲役が科せられ、未遂も処罰されます(228条)。
なお、本罪は未遂の場合も含め親告罪です(229条)。
婚姻して(民法上は)成人に達したものとみなされる者でも、20歳未満(=19歳以下)である限りは本罪の客体となります。
また、相手が未成年者であることを知らなくても、未成年であることを知り得た場合(未必的)、本罪は成立します。
下記(2)ないし(4)のように、営利目的等拐取、身の代金目的拐取、所在国外移送目的拐取の各罪が成立するときは、本罪はこれらの罪に吸収されます。
【参考判例】
母親の監督下にある2歳の子を別居中で離婚係争中の父親が有形力を用いて連れ去った行為は、未成年者略取罪の構成要件に該当し、父親が共同親権者の1人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべきものであり、連れ去る行為に及んだことにつき、子の監督養育上それが現に必要とされるような特段の事情が認められず、行為態様が粗暴で強引なものであるなどの事情の下では、違法性が阻却されるものではない(最決平17.12.6刑集59・10・1901)。
(2) 営利目的等拐取罪(刑法225条)
営利、わいせつ、結婚又は生命・身体に対する加害の目的で、人を略取又は誘拐することによって成立します。
処罰としては、1年以上10年以下の懲役が科せられます。未遂も処罰されます(228条)。
- 「営利の目的」とは、財産上の利益を得る目的をいいます。
- 「わいせつの目的」とは、未成年者を含む人にわいせつ行為をさせ、又はわいせつ行為の対象とする目的をいいます。
- 「結婚の目的」とは、法律上の婚姻であることを要せず、事実上の婚姻、すなわち、内縁関係で足りると解されます。
- 「生命・身体に対する加害の目的」とは、臓器摘出、暴行・傷害、殺人等の目的をいいます。
本罪は、未成年者を含む人を実力的支配下に置いたときに既遂に達し、営利等の目的を遂げたか否かは問いません。
(3) 身の代金目的拐取罪(刑法225条の2第1項)
「身の代金」の名称の通り、近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、財物を交付させる目的で人を拐取することによって成立します。
処罰としては、無期又は3年以上の懲役が科せられます。動機の悪質さを考慮して重い刑が科されており、未遂も処罰されます(228条)。
「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者」とは、未成年者を含む人と密接な人間関係にあるため、その生命又は身体に対する危険を親身になって心配する者をいいます。
「憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」とは、未成年者の安否に関する近親者の憂慮の状態を利用して、その者から、未成年者を含む人を釈放すること又はこれに危害を加えないことに対する代償としての財物(身の代金)を交付させる目的をいいます。
このような目的で拐取行為をすれば、その段階で本罪は既遂に達し、その目的が達成されたか否かは問いません。
なお、本罪を犯した者が、公訴が提起される前に未成年者を含む人を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽するとされています(228条の2)。
これを「解放減軽」といいますが、未成年者を含む人の生命・身体の安全を図ろうとした刑事政策的な規定ということになります。
(4) 所在国外移送目的拐取罪(刑法226条)
所在国外に移送する目的で人を略取又は誘拐することによって成立します。
処罰としては、2年以上の有期懲役が科せられます。未遂も処罰されます(228条)。
「所在国外に移送する目的」とは、未成年者を含む人を、その所在する国の領土・領海・領空外に運び去る目的をいいます。
【参考判例】
日本人である妻と別居中のオランダ国籍の者が、妻において監護養育していた2歳4か月の子をオランダに連れ去る目的で入院中の病院から有形力を用いて連れ出した行為は、国外移送略取罪に該当し、その者が親権者の1人として子を母国に連れ帰ろうとしたものであることを考慮しても、その違法性は阻却されない(最決平15.3.18刑集57・3・371)。
3.未成年者の略取・誘拐と示談
例え親切心であったとしても、家出した未成年を親の同意なく泊めたりかくまったりした場合、未成年者の略取・誘拐の罪に問われる可能性があります。
未成年の連れ去りが発覚して罪に問われてしまったならば、刑事事件に強い弁護士へ法律相談をしましょう。
未成年者の略取・誘拐の罪に関する処分結果に大きく影響を与えるのは、自首、被害者の解放、被害者側との示談です。
「未成年者の略取、誘拐」ということから、親の怒りは大きくなっているケースが多く、示談の成立には困難を伴うことが予想されますので、自力で示談を成立させるのはほとんど不可能と言えるでしょう。
しかし、未成年者の略取・誘拐について、罪名からくる悪質なイメージとは異なり、実際の事件においては様々な態様があります。
例えば、未成年の方から頼み込まれて仕方なく家に泊めたケースはもちろん、自分が成人の場合、交際中の未成年者と駆け落ちしたようなケースでも、法律的には「未成年者の略取、誘拐」の罪に問われることがあるわけです。
そして、未成年者拐取罪のみであれば「親告罪(=被害者側の告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)」ですので、示談の成否は被疑者の処分に関して重要な要素となります。
被害者が未成年者の場合、示談の相手方は未成年者の保護者となります。
略取・誘拐事件となれば、当然として怒りの大きいであろう保護者の方と示談を取り付けるためには、交渉を弁護士に委ねるしか方法がありません。
代理人の弁護士を通して反省の意を示せば、保護者の方も示談交渉を受け入れてくれる可能性があります。
「誘拐のつもりではなかった」という納得のいく理由を説明できれば、示談金の支払いも低額に抑えた上で許してもらえるかもしれません。
行動が遅いと心証も悪くなりますので、略取・誘拐の被疑者やそのご家族は、できる限りお早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
4.未成年の家出問題で罪に問われたら弁護士家
下記のような状況では、いずれも未成年者拐取罪が成立する可能性があります。
- 未成年の家出少女を自宅に連れ込んだ
- 未成年が「家出したからかくまってほしい」と言うので、仕方なく一晩泊めた
- 未成年に道案内をするつもりで歩いていたら通報された
- 離婚した親権のない父親が、元妻が監護養育している我が子を連れ去った
- 迷子の子供を家まで送ると称して、車に乗せて必要以上に連れ回した
場合によっては、道を案内しようとしたところで逮捕されたり、かくまうつもりで自宅に連れ込んだら逮捕されたり等、本人にその意思がなくても罪に問われてしまうことが多々あります。親切心での行為でも、警察や保護者は略取・誘拐と受け取るでしょう。
刑事事件で逮捕されてしまいお困りの際には、お早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件の解決実績豊富な弁護士が、被疑者の方の利益を守るために全力でサポート致します。