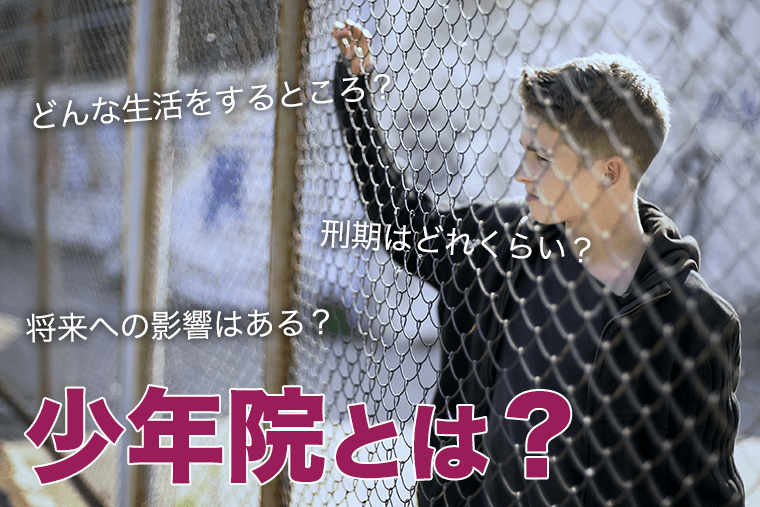少年審判を分かりやすく解説|その意味と当日の流れ

少年が窃盗や暴行などの事件を起こした場合、成人とは異なる手続を受けます。家庭裁判所の「少年審判」です。
刑罰を与えることを目的とした成人の刑事手続に対し、少年審判は刑罰を目的とはしません。
あくまでも、少年に反省を促し、その健全な育成をはかる各種の「保護処分」等を決定する手続です(少年法第1条)。
少年とは、20歳に満たない者です(少年法第2条1項)。少年が起こした刑事事件などを「少年事件」と総称します
この「少年事件」には少年法が適用され、成人に対する通常の刑事手続とは異なる手続が用意されています。
ここでは、少年審判について、その手続の意味や手続の流れについて解説します。
1.少年審判を受ける可能性のある少年事件とは?
成人に対する通常の刑事手続とは異なり、少年法で家庭裁判所の審判を受ける可能性がある少年事件は3種類です。
それが、①犯罪少年、②触法少年(しょく法少年)、③虞犯少年(ぐはん少年)です。
(1) 犯罪少年
犯罪少年とは、14歳以上の時点で犯罪を犯した少年です(少年法第3条1項1号)。
14歳以上であれば一律に刑事責任無能力を認めるのが刑法の立場(刑法第41条)ですから、本来、犯罪少年は刑法による処罰対象です。
しかし、少年の可塑性(成長し、更生できる可能性)に配慮して、特別に少年法の手続による保護を与えることを原則とします。
(2) 触法少年
触法少年とは、刑罰法令に触れる行為をしたけれど、行為の当時14歳未満だったため、前述の刑法41条によって法律上は犯罪が成立しない者です(少年法第3条1項2号)。
法的に犯罪が成立しないため、刑事処罰を受けることはありませんが、当然、放置することはできません。そこで、少年法の手続にしたがって保護対象としています。
(3) 虞犯少年
虞犯少年とは、20歳未満で、「保護者の正当な監督に従わない」、「正当の理由がなく家庭に寄り附かない」、「犯罪性のある人や不道徳な人と交際し、いかがわしい場所に出入する」などの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来、犯罪を犯すなどのおそれのある少年です(少年法第3条1項3号)。
犯罪を犯したわけでも、刑罰法規に触れる行為をしたわけでもありませんが、その危険性がある者を事前に保護し、健全な育成を目指すというわけです。
少年法の目的は、「少年」を保護して健全な育成を図ることにあるので、手続の時点で成人に達した者は対象外です。
このため、たとえ事件を起こしたときには20歳未満でも、手続の際に20歳に達していれば、成人として通常の刑事手続で処分されます(少年法第19条2項)。
2.少年事件が発生した後の手続の流れ
少年事件が発生してから、家裁による審判が行われるまでの手続の流れについて説明しましょう。
(1) 少年事件発生から家庭裁判所への送致まで
犯罪少年の場合
犯罪少年の場合は、まずは成人の刑事事件と同様に、警察から取調べ等の捜査を受けます
少年であっても、犯罪の嫌疑があり、逃亡・証拠隠滅のおそれといった身柄拘束の必要性があれば、逮捕されることは別段珍しいことではありません。
警察は捜査の結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるときは、直接に家庭裁判所へ事件を送致しなくてはなりません(少年法第41条)。
また、死刑・懲役刑・禁錮刑にあたる犯罪の嫌疑があるときは、検察官へ事件を送致します(少年法第40条、刑事訴訟法第246条)。
警察から事件の送致を受けた検察は、犯罪の嫌疑があるときは、事件を家庭裁判所に送致しなくてはなりません(少年法第42条1項)。
成人の場合、起訴処分によって事件を裁判所の裁判にかけるかどうかは、検察官の裁量で決まり、これを起訴便宜主義と呼びますが(刑事訴訟法248条)、少年事件では、全てを家庭裁判所に送らなくてはならないので、これを「全件送致主義」と呼びます。
これは犯罪の嫌疑のある少年を、処罰を目的とする捜査機関の刑事手続からいったん引き離して、家庭裁判所の手続内で、健全な育成のための方策を検討するための制度です。
触法少年の場合
触法少年は犯罪を犯したわけではありませんが、刑罰法規に抵触しているので、そのままにはできませんから、警察は児童相談所に通告しなければなりません(児童福祉法第25条)。
同時に警察は、その触法事件について調査(触法調査)を行うこともでき、調査結果も児童相談所に送られます(少年法第6条の2)。
通告を受けた児童相談所は、少年の福祉を図る観点から調査し、少年の身柄を保護所に一時保護するなどの対応をしますが(児童福祉法第33条1項)、家庭裁判所の審判が適当と判断した場合には、少年を家庭裁判所に送致します(児童福祉法第27条1項4号)。
こうして、触法少年も家庭裁判所の審判を受ける場合があります(少年法第3条第2項)。
虞犯少年の場合
虞犯少年は、犯罪を犯したわけでも、刑罰法規に抵触したわけでもありませんが、このままでは、犯罪少年や触法少年となる危険性があるので、そのまま放置するべきではありません。
虞犯少年の対応は、その年齢によって異なります。
- 虞犯少年が14歳未満
虞犯少年が14歳未満の場合は、警察は児童相談所または福祉事務所に通告します(児童福祉法第25条1項本文)。対応した児童相談所等が、家庭裁判所の審判を受けさせることが適当と判断した場合は、家庭裁判所に送致されます(児童福祉法第27条1項4号)。- 虞犯少年が14歳以上、18歳未満の場合
虞犯少年が14歳以上、18歳未満の場合は、警察は①児童相談所への通告、または、②家庭裁判所への送致のどちらか適当と判断される処理を選択できます(少年法第6条2項)。
性格、環境に照らして、犯罪危険性が低く、少年の自由を拘束・制限する必要がなく、保護者が協力的な場合などには、児童相談所への通告が相当とされています。- 虞犯少年が18歳以上の場合
虞犯少年が18歳以上の場合は、児童福祉法の「児童」には該当しないため(児童福祉法第4条1項)、家庭裁判所へ送致されます。
このように、犯罪少年だけでなく、触法少年、虞犯少年であっても、家庭裁判所の審判を受けるケースがあるのです。
(2) 送致から審判開始決定まで
観護措置決定
事件の送致を受けた家庭裁判所は、少年を少年鑑別所に収容するか否かを判断します。少年鑑別所へ収容することを観護措置と言います(少年法第17条1項2号)。
少年鑑別所は、家庭裁判所で審判を行う判断材料とするために、少年を調査・観察すると共に、指導・教育するための場所です。
もっとも実際には、観護措置には、少年が調査や審判に出頭しない恐れがある場合の身柄確保、犯罪仲間の誘いや接触からの防御、親の暴力などの劣悪な生活環境に戻ることを防止するなど、少年を保護する観点や少年の資質を見定めて更生を促す観点等の様々な機能があります。
このため、身柄を拘束される場所に収容されるというマイナスイメージや通学、通勤が犠牲となるデメリットはあるものの、単純に「鑑別所送りは避けるべき」とは言えないのが実情です。
少年鑑別所の収容期間は原則が2週間で、さらに一度だけ2週間の延長が認められるので、最長で4週間となります(少年法第17条3項)。
この少年鑑別所に在所している期間内に、精神状態、健康状態、生育歴、家庭・学校・職場での生活状況、保護者の状況、犯行の経緯、反省の状況、学校や勤務先といった身柄解放後の引き受け態勢など、少年をとりまくあらゆる事実が調査されます。
また併行して、保護者等は家庭裁判所に呼び出され、調査官の調査を受けることになります。
観護措置がなされず、少年鑑別所に収容されない場合でも、家庭裁判所の調査官が少年をとりまく事実の調査を行うことができますが(少年法第17条1項1号)、実際の実務では、この方法は、ほとんど行われていません。

[参考記事]
少年鑑別所とは|生活、入る理由、期間などを解説
審判開始の決定
家庭裁判所は、捜査機関からの資料や調査官の調査結果などに基づき、少年を審判に付するか否かを決定します(少年法第21条)。
実務では、観護措置がとられている事件では、ほとんどの場合、観護措置の期間中に審判に付するか否かを決定したうえ、観護措置の決定から3週、または4週間目前半に審判期日を指定します。
つまり、観護措置期間中に審判を受けるのです。これは調査官の調査日数(※1)と少年の出頭を確保しつつ(※2)、職場や家庭といった引受先の環境の変化など不測の事態に対応できるよう余裕をもった日程を組むためです。
※1:通常、送致した当日に観護措置決定が出るので、調査官の調査は観護措置期間内に行うしかないため。
※2:監護措置期限が切れると釈放しなくてはならないため。
審判に付されない場合とは、そもそも犯罪の嫌疑がないと判断した場合、または事案が軽微であったり、少年が十分に反省していたりして審判に付することが相当でない場合です(少年法第19条1項)。
検察官への逆送致
また、次の3つの場合は、家庭裁判所は事件を検察官に送致しなくてはなりません。
これを「逆送」と呼びます。
- 調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したとき(少年法第19条2項)
- 少年が死刑、懲役又は禁錮に当たる罪を犯したときに14歳以上であった場合で、その罪質及び情状から、成人と同じ刑事手続で刑罰を科するのが相当と判断される場合(少年法第20条1項)。
- 少年が故意に被害者を死亡させ、その罪を犯したとき16歳以上であった場合。ただし、この場合は、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは逆送する必要はありません(少年法第20条2項)。
これらの場合、事件を受け取った検察官は、成人の刑事事件と同様の刑事手続きを進めていきます。
3.少年審判当日の具体的な手続の流れ
少年審判の手続が、どのような流れで進んでいくかを説明しましょう。
(1) 非公開で原則として検察官は出席しない
この手続きは非公開で行われ(少年法第22条2項)、また、検察官は出席しないことが原則です(少年法第22条の2第1項参照)。
また、少年審判は刑事事件の法廷とは異なり、教育的配慮が求められる場であって、次のように定められています。
少年法第22条1項
「審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。」
(2) 人定質問・黙秘権の告知
まずは、少年に人定質問が行われます。人定質問とは、少年の氏名や生年月日を尋ね、少年と出頭した者が同一人か否かを確かめる手続きです(刑事訴訟規則第196条、少年法第40条)。
その後、少年に黙秘権の告知を行います(少年審判規則第29条の2)。
(3) 犯罪事実の告知
裁判官は、審判の対象となる犯罪などの事実を少年に告げます。そして、内容に誤りがないかを確認し、付添人にも意見の機会を与えなくてはなりません(少年審判規則第29条の2)。
さて、付添人とは、①成人の刑事事件における弁護人と同様に少年の権利を保護する役割があると同時に、②少年の健全な育成、更生を手助けする役割をも担う存在です。
前者の立場では、少年が犯罪事実を否認している場合や違法な捜査が行われた場合など、少年の無実を明らかにし、適正な審判手続を実現させるため、捜査機関や裁判所と激しく対立し、闘う場合もあります。
他方、後者の立場では、家庭・学校・職場といった、少年が立ち直るための生活環境を整えるなど、少年の更生を助けるため、保護者はもとより、調査官、裁判官(審判官)とも協力する関係となります。
付添人は必須ではありませんが、付添人がつくケースのほとんどは、その役割を弁護士が担っているのが実情です。
(4) 裁判官・付添人・調査官による少年・保護者への質問
審判期日では、少年は裁判官から様々な質問を受けます。犯行の動機、犯行状況、反省の有無、被害者に対する気持ち、今後の生活、将来の夢など、処分内容を判断するために必要なあらゆる事項です。
また、出頭している保護者に対しても数々の質問が行われます。少年の雇い主や担任教師などの今後の監督を委ねる者が証人として出頭している場合は、これらの人々も質問を受けます。
各人への質問は、裁判官だけでなく、調査官、付添人からも発せられます(裁判官、付添人、調査官という順番が通常です)。
(5) 少年らの最終意見陳述
質問が終われば、付添人、少年、保護者らは裁判官の許可を得て、処分内容に関する意見を述べることができます(少年審判規則第30条)。
(6) 裁判官による処分
犯罪事実に争いがない事件の場合、通常、審判は1回だけ行われ、1時間弱程度で、質問、意見陳述などの手続が終了すると、その場で、審判の結果が伝えられます。
審判で下される処分には、以下のものがあります。
保護処分
- 保護観察:少年を施設に収容せずに、社会内で保護司や保護観察官の監督・指導を受けながら更生を図る処分(少年法24条1項1号)
- 少年院送致:少年院において矯正教育を受けさせること(少年法24条1項3号)
- 児童自立支援施設または児童養護施設への送致:児童福祉法上の支援を行うことを目的として設けられた開放的で家庭的な施設に少年を入所若しくは通所させること(少年法24条1項2号)
- 都道府県知事または児童相談所への送致:少年を児童福祉機関で指導するのが相当と考えられる場合に行われます(少年法18条1項)。
試験観察(中間処分)
直ちに処分を決めることができない場合に、処分を一時留保し、少年を一定期間、調査官が観察すること(少年法25条)。この場合、試験観察期間経過後、改めて審判が行われます。
不処分
犯罪事実が存在しないと認められた場合や、保護処分が不必要と認められた場合です(少年法23条2項)。
4.少年事件における弁護活動とは
少年事件はその特殊性ゆえ、通常の刑事弁護とは異なる活動が必要です。
家裁送致前の捜査段階から弁護士が付いた場合、まずは少年に対して取調べを受ける際の注意点や少年が行使できる権利についての助言などを行います。
事件が学校や職場に発覚することが不利益となる事案では、捜査機関に対して配慮を申し入れます。とはいえ、捜査機関と学校との協定で、直ぐに伝えられてしまうケースもあります。
また、少年事件では、少年の更生のために、審判手続に、学校や職場の協力が不可欠となる事案は珍しくありません。弁護士は、少年本人、保護者と十分に協議して、どのような対応が望ましいかを選択します。
事件が家庭裁判所に送致された後は、審判不開始を求めたり、逆送を防いだりする活動を行います。
その際、意見書などを家庭裁判所に提出したり、裁判官に面会を求めたりすることになります。
事実に争いがあるような事件を除き、通常は、調査官と緊密に連絡をとりながら、少年にとってもっとも良い処分を考え、それが実現するよう尽力します。もちろん、観護措置を受けた少年との面会も欠かせません。
また、審判期日には、付添人として出席し、意見を述べ、事案に応じて、不処分や少年院送致の回避を目指します。
少年審判においては、調査官の意見が決定的に重みを持ち、裁判官の結論は調査官の考えに大きく左右されます(少年審判規則第13条)。その調査官の出す方針は、審判期日の前日までに決まっているのが実情です。
そこで、付添人となった弁護士は、調査官との間で情報のキャッチボールを行いながら、できるだけ少年に有利な処分となるように、審判期日に向け、時間をかけて、調査官が調査を踏まえて心配している点を取り除くなどして、その実績を元に調査官を説得していくことになります。
5.まとめ
犯罪を犯したと言っても、少年はまだ若く、更生することが十分に期待できます。
社会内で立ち直りが可能であれば、できれば、監護措置や少年院送致は避けたいところです。そして、早期のうちから対応して長期間をかけて働きかけをすることで、家庭裁判所の審判において最も重要な要素の一つである少年の再非行の可能性(要保護性)を効果的に低下させることが出来ます。
少年の将来のためにも、ご子息が事件を起こしてしまったら、泉総合法律事務所の弁護士に相談してください。