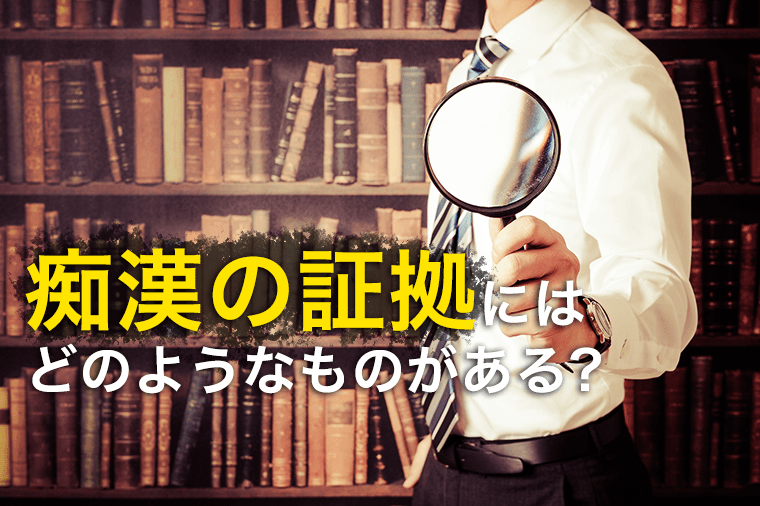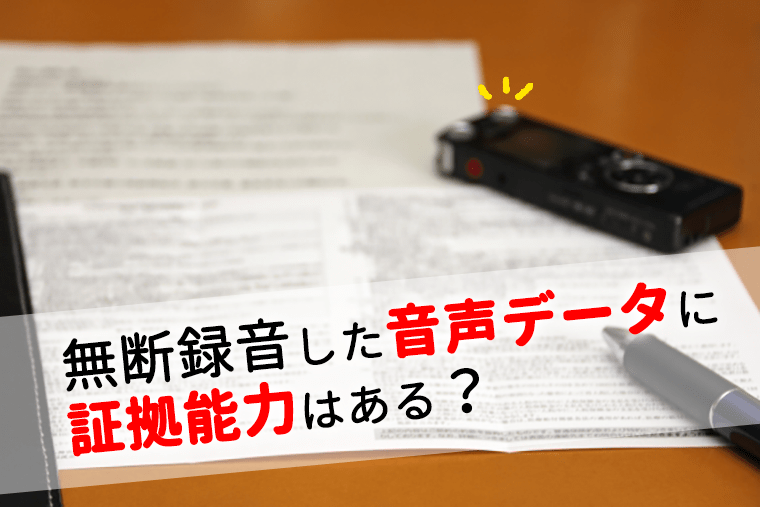情況証拠は弱い?情況証拠と直接証拠の違い

「情況証拠」という言葉には、「あやふやな」「不安定な」「不確実な」証拠というイメージがあるかもしれません。「情況」という単語自体が「漠然としたもの」という印象を与えるのも事実でしょう。
実際、「情況証拠のみで判決が出るなんて…」という意見はインターネット等でよく耳にします。
しかし、果たして情況証拠は本当に弱い証拠なのでしょうか?
情況証拠のみで事実認定をすることは本当に間違っているといえるのでしょうか?
1.情況証拠(間接証拠)と直接証拠の違い
「証拠」とは、「裁判上、事実認定の基礎とすることのできる資料」のことをいいます。
そして、「証拠」は様々な観点から分類することができます。
情況証拠(間接証拠)と間接証拠に限っていえば、これは証明の対象となる事実(要証事実)との関係での分類です。
一般的には、要証事実を直接に証明するのに用いられる証拠を直接証拠といい、要証事実を直接証明することはできないがこれを推認させる事実(間接事実)を証明するのに用いられる証拠を間接証拠といいます。この間接証拠が情況証拠と呼ばれています(※情況証拠の定義には様々な考え方があります)。
しかし、このように定義を説明されてもピンとこないでしょうから、以下でそれぞれの証拠の具体例を解説していきます。
2.情況証拠・間接証拠の具体例
(1) 「甲が乙を包丁で突き刺して殺害した」という事例
Aが「乙の死の直後、甲が包丁を持っているのを見た」と供述したとします。Aの供述は(もし信用できることを前提とするならば)甲による包丁の所持については直接証拠となります。
しかし、この供述は「甲が乙を包丁で突き刺して殺害した」という要証事実を直接証明するものではありません。乙の死の直後の甲による包丁の所持という事実(X)からは、甲の包丁による乙の刺殺という事実(要証事実)が推認される関係にあります。
(X)を間接事実といいますが、この間接事実を証明する証拠を情況証拠(=間接証拠)といいます。
よって、Aの供述は情況証拠ということになります。
一方、「甲がジャンパーの内ポケットから包丁を取り出し、包丁の柄を両手で握り、刃先を前に向け、乙の腹部目がけて包丁で刺したのを見た」というBの供述とか、「自分が乙を殺すため、包丁で乙の腹部を突き刺した」と認める被告人甲の自白が、直接証拠となります。
これらの直接証拠があると(それらの供述が信用できることを前提とするならば)「推論」の助けを借りないで、要証事実を認定することができます。
(2)「甲の運転する車が対向車線にはみ出して、対面進行してきた乙車に衝突し、乙を死亡させた」という事例
対向車線に残っていた甲の車のタイヤ痕は、情況証拠(「甲の車のタイヤ痕が対向車線にあった」という間接事実を証明する証拠)です。
情況証拠ではありますが、この証拠が「対向車線にはみ出して乙車に衝突し、乙を死亡させた」という要証事実を証明する力は大きいと言えます。
一方、「甲車が対向車線にはみ出して、乙車に衝突したのを見た」というAの供述とか、「自分が車を運転中、ハンドル操作を誤って対向車線にはみ出し、対面進行してきた乙車に衝突した」と認める被告人甲の自白が、直接証拠となります。
(3)「甲が乙宅から指輪を盗み取った」という事例
「犯行当時、金に困っていた被告人甲から金を無心されたが断った」というAの供述、「犯行直後に乙宅前で被告人甲の姿を見かけた」というBの供述、「被告人甲がその後間もなく指輪を入質した」という質屋Cの供述等は情況証拠になります。
この複数の状況証拠があれば、これらを総合して被告人甲を窃盗の犯人と認めることも可能でしょう。
一方、「甲が鏡台から指輪を盗むのを隣室で見ていた」という乙の供述とか、「自分が乙宅で鏡台にあった指輪を盗んだ」と認める被告人甲の自白が、直接証拠となります。
3.情況証拠のみで事実認定をするのは合理的?(判例)
では、情況証拠のみで事実認定をすることは間違っているのか否か、判例を元に検討します。
結論から言えば、直接証拠と情況証拠との間には、証拠の価値の点で差がありません。
最決平19.10.16(刑集61巻7号677頁)は、「有罪認定に必要とされる立証の程度としての『合理的な疑いを差し挟む余地がない』の意義は、直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。」旨判示しています。
さらに、最判平22.4.27(刑集64巻3号233頁)は、
「情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが、直接証拠がないのであるから、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。」
旨判示しています。
この太字部分の趣旨は、「情況証拠による事実認定に際して、被告人が犯人であるとすればそのすべてが矛盾なく(合理的に)説明できる場合に、直ちに被告人が犯人であると速断することを戒め、逆に被告人が犯人でないとしても合理的に説明し得る余地はないか(他の者が犯人である合理的可能性はないか)を裏側から検証して有罪立証の確実性を確認するように注意を喚起したものと理解される。」とされています。
また、情況証拠によって有罪認定をする場合は、総合評価に加わる個々の間接事実の単体としての推認力は低くてもよい、とするのが多数説とされています。
例えば、ある間接事実から犯人となり得る者が甲、乙、丙のいずれかと認められ、それと別個独立の他の間接事実から犯人となり得る者が甲、丁、戊のいずれかと認められれば、犯人が甲であることは高度の蓋然性をもって推認できます。複数の間接事実を総合した事実関係でも、有罪認定は妨げられないと考えられるのです。
なお、上記最判平22.4.27後の刑事裁判の実状を見ますと、間接事実からの総合判断に際して、「被告人が犯人であれば合理的に説明できる事実関係がある」というだけでは立証として不十分であることが改めて意識され、認定した事実を総合した場合に被告人が犯人でない可能性はどの程度あるのか(=被告人が犯人でないとしたならば合理的な説明が極めて困難である事実関係があるのか)についても検討されているのが現在は一般です。
以上から、情況証拠のみで事実認定をするのは間違っているといえないことになります。
4.おわりに
刑事事件でどのような証拠が決定的となるのかは、その事件の内容によって様々です。
刑事事件で裁判となってしまった場合、刑事弁護を弁護士に頼むならば、様々な刑事事件を経験し判例の理解を含む証拠法に精通している弁護士に依頼しましょう。
泉総合法律事務所は、様々な刑事事件を解決してきた実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。刑事事件で裁判となりそうな場合だけでなく、逮捕されてしまった場合に起訴を避けるためにも、お早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。