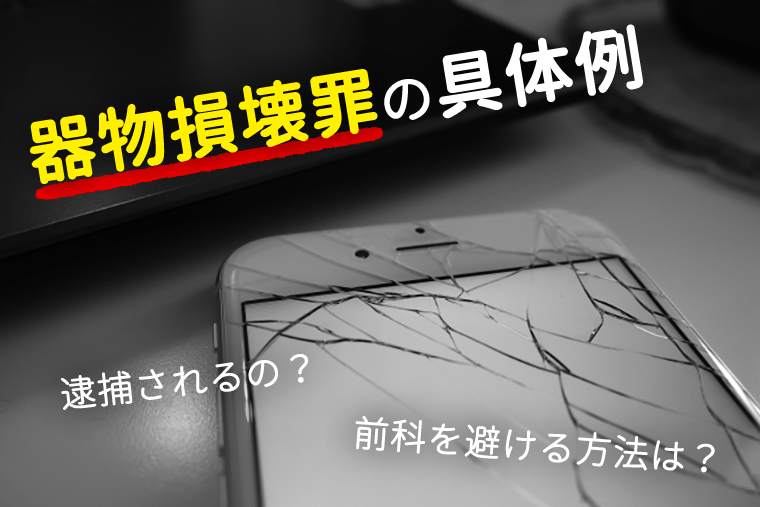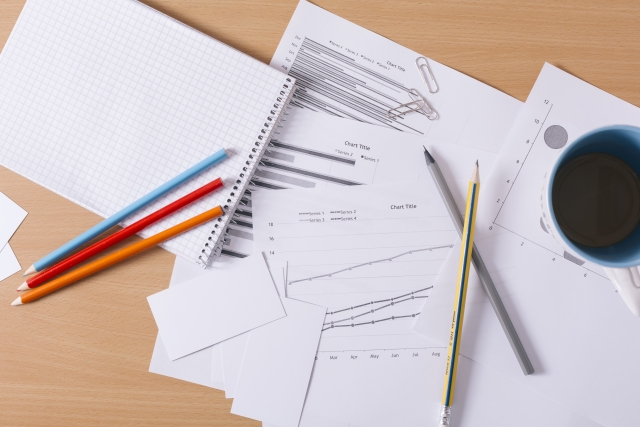不動産侵奪罪・境界損壊罪|土地に関する刑事事件
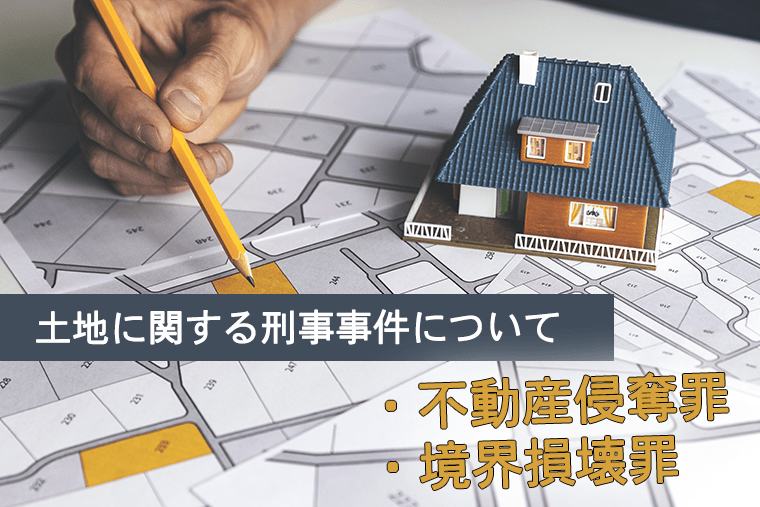
土地に関するトラブルは意外に多いものです。
例えば、相続をきっかけに「この土地は実は親の土地ではなかった」または「実は親の土地なのに、他の人が使用していた」などの事実が判明することがあります。
また、土地付きの家を買ってみたら「登記簿上では自分の土地なのに、隣の人が占有していた」という例もしばしば発生します。
土地に関するトラブルの多くは民事的な解決を図りますが、ときには刑事事件となってしまう場合もあります。
本記事では、刑法に記載されている土地に関する罪について紹介・解説していきます。
1.土地に関する罪とは
刑法上、土地に関する罪とされているものは「不動産侵奪罪」と「境界損壊罪」の2つです。
(1) 不動産侵奪罪
刑法第235条の2
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
不動産侵奪罪は「窃盗及び強盗の罪」の中に規定されています。
窃盗とは財物の占有を侵害する行為です。
動産と異なり、不動産の占有を侵害しても、不動産それ自体は動かすことは不可能なため、被害者が占有を回復することは困難ではなく、民事的な保護で足りるとして、窃盗の客体から不動産は除外されていました。
しかし、日本の社会が近代化し、権利関係が複雑化するにつれ、占有を侵害された権利者が民事手続に訴えても、占有を回復することが簡単ではなくなってきたため、第二次大戦前においても不動産を窃盗罪の客体に含めるべきであるという意見が強くなっていました。
しかも、敗戦後の混乱した社会状況において、闇市など、他人の土地を不法占拠して、住居や店舗を設置し、既成事実化してしまうケースが珍しくなくなりました。
被害者側が民事手続での救済を求めても時間もコストもかかるため、やむなく実力行使による自力救済が横行し、暴力対暴力の争いになってしまうことが頻発したのです。
そこで、このような事態を沈静化するために、昭和35年、不動産の占有侵害を犯罪とする不動産侵奪罪が定められたのです。なお、同時に、後述の境界毀損罪も定められました。
法定刑は10年以下の懲役となっており、罰金刑がない点で窃盗罪よりも重いものとなっています。
また、刑法243条の規定によって、不動産侵奪罪は未遂でも成立することになっています。
不動産侵奪罪の公訴時効は、侵奪が終わってから7年と定められています(刑事訴訟法235条4号)。
①「侵奪」とは?
条文には「侵奪」という聞き慣れない言葉がでてきますが、ここでいう侵奪とは「他人が不動産を占有することを排除して、事実上自分の占有下に置く行為」を意味します。他人の動産の占有を侵害して自分が占有する「窃取」と同じ概念だと考えてください。
例えば、他人の土地の上に勝手に家を建てる、他人が所有している空き家に勝手に入りこんでその空き家を不法占拠・無断使用した場合には、不動産侵奪罪が成立します。
一方、不動産侵奪罪における占有は、窃盗罪とパラレルに理解されるため、横領罪のような法律的な支配を含みません。そのため、例えば、他人の不動産について虚偽の所有権移転登記を行ったとしても、現実に占有していなければ不動産侵奪罪にはあたりません。
ただし、この場合は、虚偽の登記申請にあたり、勝手に被害者名義の売買契約書などを偽造した行為が「有印私文書偽造・行使罪」に問われ、登記官に虚偽内容の登記をさせた行為が「公正証書原本等不実記載罪」に問われる可能性があります。
また、他人の土地に入るだけでは、他人の占有を排除していないので、侵奪とは評価されません。
なお、不動産を侵奪するときに占有者を暴行したり脅迫したりすると強盗罪になり得ます。さらに、他人を騙して不動産を侵奪した場合は詐欺罪に該当することもあります。
これらの場合、対象不動産の占有を奪うことは、強盗罪や詐欺罪における行為の一部に過ぎないので、別個に不動産侵奪罪が成立することはありません。
②親族間の不動産侵奪はどうなる?
刑法244条には「親族間の犯罪に関する特例」があり、配偶者や直系血族または同居の親族との間で不動産侵奪罪が発生した場合(または未遂の場合)は刑が免除されることになっています。
また、上記以外の親族関係の場合は親告罪となり、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができないと定められています。
この特別な扱いは、「法律は家庭に入らず」という法思想、すなわち親族間における犯罪に国家が干渉するよりも、親族間で解決させた方が親族内の秩序維持に資するという思想に基づきます。
ただし、親族が不動産侵奪罪を犯した時に親族以外の共犯者がいた場合、当然ですが、親族でない共犯者については「親族間の犯罪に関する特例」が適用されません。
(2) 境界損壊罪
刑法第262条の2
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
境界損壊罪は「毀棄及び隠匿の罪」の中に規定があります。
土地に設置された境界標に何らかの行為をする等して、どこが土地の境目なのかをわからなくした場合、この罪に問われます。土地の権利関係の明確性を保護するための規定です。
土地の「境界がわからない状態にする」ことが犯罪であり、境界標を損壊・移動・除去する行為は、その例示に過ぎません。
また、「境界」は、所有権の境界に限らず、地上権、抵当権、賃借権などの境界も含まれますし、都道府県や市区町村の境界も含まれます。
①境界標とは?
境界標とは、杭や柵など土地の境界をわかるようにした物全般を意味します。
境界標の所有権を保護する規定ではないので、自分で作った境界標柵を自分で破壊したり移動をしたりしても境界損壊罪に問われます。
境界標の損壊を行っても、境界自体がわかる状態であれば境界損壊罪にはなりません。ただし、その境界標が他人の所有物であれば、器物損壊罪などに問われることはあります。
虚偽または間違って設置されている境界標を勝手に移動したり除去したりしても境界損壊罪が成立します。たとえ正当な境界でなくとも、裁判など法的手続に則って変更されるまでは、事実上の境界を尊重し、保護するべきだからです。
したがって、勝手な判断で境界標を移動または除去してはいけません。
境界標を移動または除去するなどして境界をわからなくしたうえで他人の不動産を侵奪した場合は、境界損壊罪と不動産侵奪罪の両方の罪に問われます。
2.土地に関する罪の具体例
それでは、どのような行為が不動産侵奪罪や境界損壊罪として認定されたのでしょうか?
(1) 不動産侵奪罪の例
①境界線を移動させて他人の土地を占有する
柵などをわざと隣地である他人の敷地にはみ出させただけでは相手の占有を排除したとは言えませんが、鉄条網などで相手が利用できない状態にしてしまえば、占有を奪ったとして不動産侵奪罪となります。
②他人の土地に無断で建物を作る
不動産侵奪罪の典型例です。不動産侵奪罪が作られる契機となった「梅田村事件」(※大阪高裁昭和31年12月11日判決)は、土地を不法占拠していた多数の木造バラック店舗を地権者が重機で破壊し、自力救済を図ったことで建造物損壊罪で起訴された事件です。
被告人は正当防衛による無罪が認められましたが、不動産の不法占拠行為に対して、民事手続だけでは権利者に有効な救済手段が与えられないことが、改めて問題視され、不動産侵奪罪の制定につながったとされています。
【参考】公園予定地に簡易建物を建てた行為に不動産侵奪罪が成立するとされた事例|最高裁平成12年12月15日判決(平成12(あ)第451号事件)
なお、侵奪行為は、窃盗罪における窃取と同様に、行為者が自分に占有を移した場合だけでなく、第三者に占有させた場合も含みますから、他人の土地を勝手に売って第三者に建築物を作らせた場合も不動産侵奪罪が成立します。
③他人の土地の上に張り出すように自宅を増築する
民法では、「土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」(民法207条)と定められており、地上権も空間利用を目的として設定することが可能です(民法269条の2第1項)。したがって、土地の占有とは、地表面だけではなく、上方の空間と地下の事実的支配も含む概念です。
このことから、不動産侵奪罪で保護される土地も、地面だけでなく、地上の空間及び地下をも含むことに異論はありません。
ですから、他人の土地に張り出した建物を作れば、不動産侵奪罪となるのは当然です。
④アパートの一室を占拠する
そのアパートと何ら契約関係にない人が、勝手に部屋に入り込んで部屋を占有するケースです。
不動産侵奪罪は土地の一部や建物の一部のみを占有しても成立します。不動産の全体を占有しなくても罪に問われるのです。
ここで混同されやすいのが、賃貸期間を過ぎた後、賃借人が所有者からの立ち退きを請求されているのにアパートに居座るケースです。この場合、不動産を継続して使用している人は、以前からの占有を継続しているだけで、新たに自分の占有を取得して所有者の占有を侵害したわけではありません。したがって、侵奪行為が存在しないので、不動産侵奪罪は成立しません。
⑤他人の土地に廃棄物を投棄する・耕作する
いわゆる不法投棄です。他人の土地を掘り、土砂を搬出して、そこに廃棄物を投棄した事件で不動産侵奪罪が適用されたことがあります(大阪高判昭和58年8月26日・判例時報1102号155頁)。
また、他人の土地を無断で耕して種を蒔き、植物を栽培するような行為も不動産侵奪罪です。
⑥土地が転貸され転借人が土地上に容易に撤去できない建物を作った
土地の使用貸借契約において、転貸を禁止し、直ちに撤去可能な屋台営業だけを認める約定をしていたところ、無断転貸が行われ、転借人が増改築を行って撤去困難な建物を設置したという事例で、転借人に不動産侵奪罪が認められました。
この事案では、転借人は、転貸人の占有を引き継いだだけであり、新たな占有侵害行為がないのではないかという点が争点となりましたが、増改築によって撤去の困難性が格段に増したことから、この増改築が新たな占有侵害行為と評価できると判断されました。
【参考】最高裁平成12年12月15日決定(平成12年(あ)第840号事件)
(2) 境界損壊罪の例
①境界標としていた柵や杭などを撤去または移動した
境界標の機能を有していた人工物に何らかの行為を加え、土地の境界をわからなくするものです。
自分で作った人工物でなくても、先祖代々土地の境界として使われてきた石垣などが境界標として認められることがあるので注意してください。
②境界標としていた木や石などを撤去または移動した
境界標は人工物だけではありません。自然に生えた木や石を境界標として使っている場合もあります。
そういった場合、境界をわからなくする目的で木を伐採して切り株を除去したり、石を移動してしまったりすると境界損壊罪にあたることがあります。
3.まとめ
刑事事件では、「こんなことが罪になるの?」というものが意外と多く存在します。
不動産侵奪罪などが適用されるかどうかは法律的な判断が必要なので、疑いがあった場合は速やかに弁護士に相談するといいでしょう。
万が一刑事事件の被疑者になってしまった場合は、できるだけ早く刑事事件に詳しい泉総合法律事務所の弁護士にお問い合わせください。