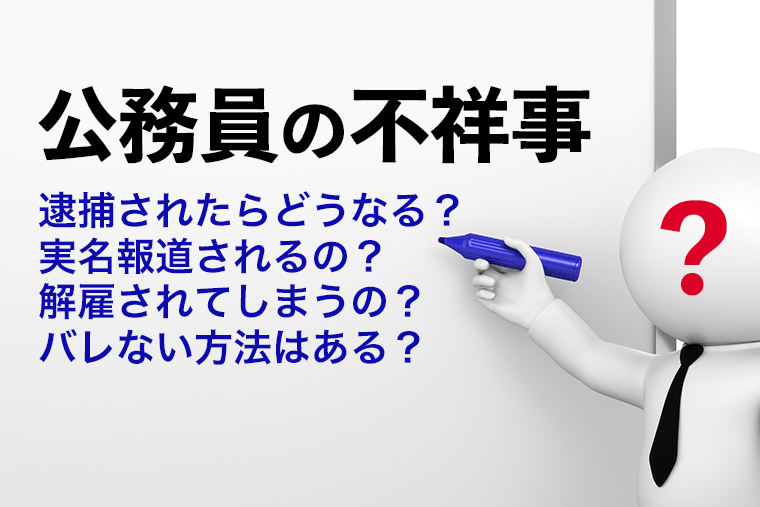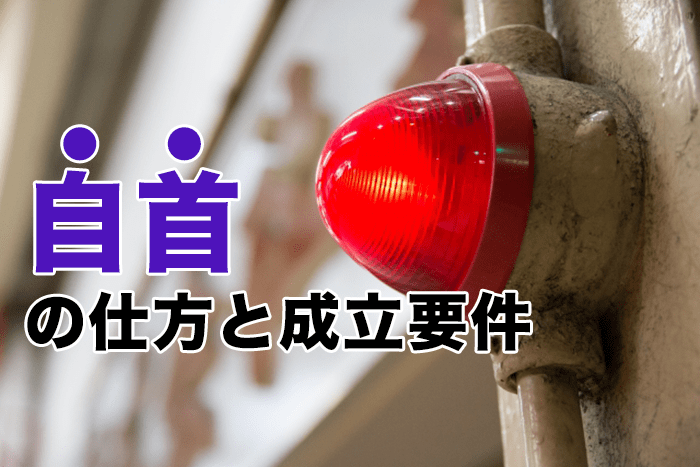公務員が刑事事件を起こしたら懲戒処分?

盗撮、痴漢、不同意わいせつ(強制わいせつ)など、刑事事件の犯人が公務員だった、というニュースは頻繁に耳にします。
公務員も人間ですから、魔が刺したなどの理由で罪を犯すことはもちろん有り得ます。
しかし、公務員の場合、民間従業員以上に社会の風当たりが強いだけでなく、厳格な法律で動いている職場からの制裁を覚悟しなくてはなりません。今後の刑事処分だけでなく、職場での懲戒処分が不安な公務員の方は多いと思います。
この記事では、国家公務員、地方公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、懲戒処分を含めて、国や地方公共団体からどのような対応がなされるかについて、詳しく説明していきます。
1.公務員の刑事事件に対する国、地方公共団体の対応
公務員が刑事事件を起こした場合、任免権者である国や地方公共団体が取り得る対応は次の4種類です。
①失職
②懲戒(懲戒免職を含む)
③分限免職
④休職
(1) 失職
失職とは、公務員が「欠格事由」に該当するに至った場合、当然に職員の身分を失うことです。
その欠格事由について、国家公務員は「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」は当然に失職すると定めており(国家公務員法76条、同38条1号)、地方公務員も同様です(地方公務員法28条4項、同16条)。
つまり、例えば懲役2年の実刑判決が確定した場合は服役して刑期が終了するまでの間が欠格であり、執行猶予付き判決が確定した場合は執行猶予期間が終了するまでの間が欠格です。
失職は、後に説明する懲戒免職処分や分限免職処分と異なり、任免権者による行政処分として職を奪われるのではなく、当然に離職の効果が生じ、国や地方公共団体の裁量の入る余地はありません。
【失職と退職金】
国家公務員が失職した場合には、退職手当の全部または一部を支給しないことができます(国家公務員退職手当法12条1項2号)。
地方公務員については各条例が定めており、例えば東京都では、国家公務員と同様の規定がおかれています(東京都「職員の退職手当に関する条例」17条1項2号)。
(2) 懲戒
懲戒とは、非違行為のあった職員に対する制裁として行われる処分です。
国家公務員に対する懲戒処分の種類は、①戒告、②減給、③停職、④免職と法定されています(国家公務員法82条1項柱書)。地方公務員も同様です(地方公務員法29条1項)。
各処分の内容は、国家公務員では人事院規則、地方公務員では各条例(例:東京都「職員の懲戒に関する条例」)に定められています。
国家公務員に関する懲戒事由は、次のとおり法定されています(国家公務員法82条1項)。
①国家公務員法もしくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
②職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合
③国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
地方公務員に対する懲戒事由も同様の定めが置かれています(地方公務員法29条第1項)。
(3) 分限免職について
分限免職は、行政運営上、当該職員を職につけておくことが不適切なために行われるもので、本人に対する非難や制裁の性格を有しない処分です(国家公務員法78条、地方公務員法28条)。
例えば、病気で職務遂行に堪えない場合や人員削減の場合も分限免職処分が行われます(国家公務員法78条各号、地方公務員法28条1項各号)。
分限免職は制裁ではないので退職手当が全額支給されます。
制裁ではないので、公務員が刑事事件を起こした場合には、分限免職にはならないはずです。しかし、分限免職事由の中には、「その他その官職に必要な適格性を欠く場合」(国家公務員法78条3号、地方公務員法28条1項3号)が規定されているので、刑事事件を起こしたことを理由として分限免職が行われるケースもあります。
ある地方自治体が、28万円相当の収賄事件で逮捕された職員を、懲戒免職とせずに分限免職として退職手当を支払ったところ、その後、当該職員は合計で300万円以上の収賄をしていたことが判明して起訴されたという事案です。懲戒免職とするべきであって、地方自治体による分限免職処分が違法だとして住民訴訟が提起されました。
しかし、最高裁は、懲戒事由が存在するときに、懲戒処分を行うかどうか、どのような処分内容を選択するかは任命権者の裁量に委ねられており、刑事手続が進行中で、事件の全貌が不明な段階でも、「必要な適格性を欠く」職員を早期に公務から排除して公務の適正な運用を回復するという要請に応える必要があることなどを考慮し、これを違法とはしませんでした(※最高裁昭和60年9月12日判決)。
(4) 休職
休職とは、職員の身分を保持したまま、職員を職務に従事させない処分であって、停職と類似しますが、停職は制裁としての懲戒処分であるのに対し、休職は制裁の意味を有しない分限処分の一種です。
国家公務員が刑事事件に関して起訴された場合は、その事件が裁判所に係属している間、休職とすることができ、その期間中、無給とされることが原則です(国家公務員法79条2号、80条2項、同4項)。
地方公務員の場合も、刑事事件に関し起訴された場合は休職とすることができ(地方公務員法28条2項2号)、国家公務員の場合と同様の内容が各条例で定められています(例:東京都「職員の分限に関する条例」第4条3項、第5条)。
2.刑事事件を起こした公務員の懲戒処分
さて、罪を犯した公務員が逮捕された場合、逮捕・勾留→起訴→公判→有罪判決と刑事手続が進みますが、上に説明した国や地方公共団体の対応が行われるのはどの段階なのでしょうか?
また、刑事手続における検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所による判決の内容は、国や地方公共団体の対応に影響するのでしょうか?
(1) 懲戒処分等がされるタイミング
まず失職は、「禁錮以上の刑に処せられ」たことが欠格事由ですから、禁錮・懲役・死刑の判決が確定した段階でなければ失職しないことが明らかです。
次に分限免職は、任命権者の裁量で「官職に必要な適格性を欠く」と判断した場合に行うことができますから、刑事手続が起訴や判決に至っていない段階での分限免職処分も許されます。
実際、先の最高裁判例の事案は、逮捕からわずか4日後に分限免職処分を行ったケースです。
もちろん、任命権者の裁量と言っても、何らの制約もないものではありませんから、職員が否認しており、検察官が「嫌疑なし」と判断して不起訴処分とした場合に、国や地方公共団体が独自に不合理な犯罪事実を認定して処分をした場合は、裁量を逸脱するものとして違法の問題を生じます。
しかし、検察官の起訴不起訴の判断や裁判官の判決内容に、国や地方公共団体が拘束されるわけではないのです。
このことは懲戒免職においても同じです。
国家公務員法第85条
「懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。(以下略)」
つまり、刑事裁判の結果が出る前でも、人事院または人事院の承認をもらった任命権者は、その刑事事件について懲戒処分をすることが可能なのです。
しかも、これを受けて人事院規則では、刑事裁判にかけられている職員が、①公判廷で犯罪事実を認めたときはもちろん、②その前でも、任免権者に対して犯罪事実を認めたときは、人事院の承認があったものと同視して、任免権者は懲戒手続を進めることができるとしています(人事院規則12-0、第8条)
地方公務員についても、同様に刑事裁判継続中であっても懲戒手続を進めることができることが定められています(例:東京都「職員の懲戒に関する条例」第5条)。
ですから、刑事事件に対しては、どの段階でも法的には懲戒処分が可能であって、刑事手続のどの段階で、どのような懲戒処分をするかは国や地方公共団体の裁量によって決まります。
国や地方公共団体、検察官や裁判官の判断をどの程度尊重するかは、懲戒処分を受けた職員が、後にこれを不服として訴訟で争ったときに、国や地方公共団体が勝訴することができるかどうかという観点から判断されることです。
(2) 起訴・不起訴と懲戒の関係
この観点からすると、不起訴処分のうちでも、「起訴猶予」は有罪の見込みを前提にあえて起訴しないものですから、任免権者としても、犯罪事実があったものとして懲戒に踏み切る可能性が高いでしょう。
これに対し、不起訴処分の理由が「嫌疑なし」のときは、人違いや犯罪の証拠がない場合ですから、任免権者が懲戒に踏み切る可能性はほとんどないでしょう。
他方、不起訴処分の理由が「嫌疑不十分」の場合は有罪判決を得るに十分な証拠が足りない場合です。しかし、証拠が足りないなら懲戒されることはないと考えることはできません。
検察官が判断する「証拠が足りない」とは、刑事裁判における検察官の責任である、裁判官が合理的な疑いを容れる余地がない程度に立証できるレベルには至っていないという意味だからです。
刑事裁判で有罪を見込める証拠が足りなくとも、民事訴訟、行政訴訟で犯罪事実があったと証明できる可能性のある証拠があれば、任免権者が懲戒処分に踏み切る可能性もあるわけです。
したがって、これは理屈のうえでは無罪判決を得た場合も同じです。
無罪判決が確定した場合に、あえて懲戒処分に踏み切るリスクをとる任免権者はいないだろうと思われますが、ひとくちに無罪判決と言っても様々であって、例えば正当防衛が成立するかどうか微妙な事案での無罪や、高裁での逆転無罪では、任免権者側が必ずしも懲戒処分を諦めるとは限りません。
3. 公務員の懲戒処分事例
最後に、公務員に対する懲戒処分の事例をいくつか紹介します(年月は処分発令月)。
なお、懲戒処分では、懲戒処分をするか否か、いかなる処分内容を選択するかにつき、任命権者に裁量があるため、任命権者による不統一が生じることは避けなくてはなりません。
そこで、国家公務員法の場合、人事院が通達によって「懲戒処分の指針」を定めています。犯罪類型ごとに、適用となる懲戒処分の種類が挙げられています。
参考:人事院「懲戒処分の指針について」
(1) 盗撮 停職3ヶ月
令和元年11月 国家公務員・男性31歳
喫茶店内の男女共用トイレに隠しカメラを設置して盗撮行為を行った(刑事処分不明)
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/fukumu/choukai20191127-2.pdf
(2) 強制わいせつ罪 不起訴でも減給
令和元年9月 国家公務員・男性37歳 減給12月 10分の1
知人の女性にわいせつな行為を複数回行い、検察庁に「強制わいせつ罪」で書類送致され不起訴処分となった。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban01_02000026.html
(3) 傷害 停職10日
令和2年9月 地方公務員・男性60歳
居酒屋で交際相手の女性の顔を殴り、全治10日の傷害を負わせた。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/03jinji/pdf/fukumu/choukai20200904.pdf
(4) 窃盗罪 停職2ヶ月
平成23年11月 国家公務員・男性24歳 停職2月間
某大学校内で、1万9千円相当の革靴を窃取した(刑事処分は不明)。
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin10_02000003.html
4.公務員の刑事事件は、早めに弁護士へ相談・依頼を
公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合は、何よりも、これを「事件化させない」ことが重要です。
警察の捜査が始まる前に、弁護士が被害者と交渉をして示談を成立させ、被害届や告訴状の提出を思いとどまってもらうことができれば、事件の存在自体を発覚させずに円満に終了させ、職場に知られて懲戒処分を受けることはありません。
また、既に逮捕されてしまった場合でも、示談によって、勾留による長期の身体拘束を阻止し、起訴猶予処分を獲得する可能性が高まり、懲戒処分を受けたとしても、処分を軽くすることが期待できます。
是非、刑事事件に強い泉総合法律事務所にご相談ください。