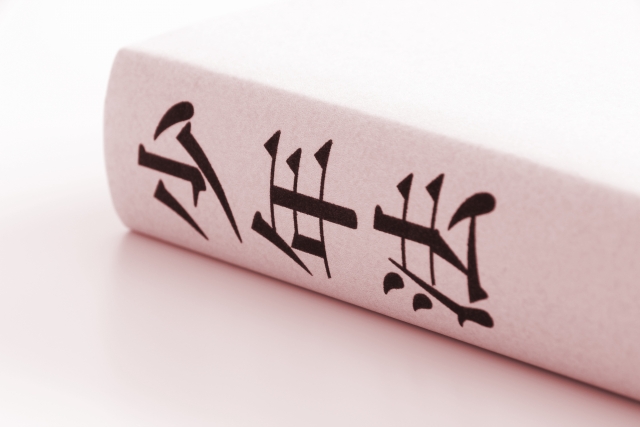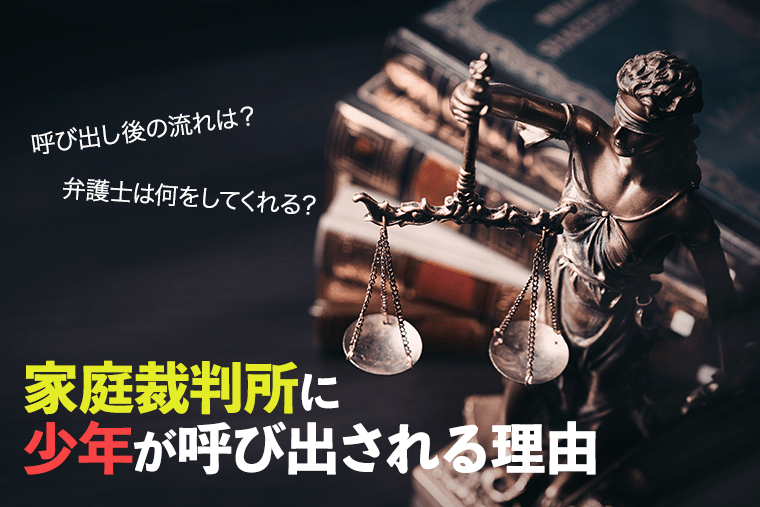成人年齢引き下げで変わる刑法と少年法の問題【20歳→18歳】

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法の改正案が成立し、2022年4月1日から施行されました。
これによって、刑事事件に何かしら影響はあるのでしょうか?
1.民法の成人年齢引き下げの経緯
(1) 国民投票法の制定
自民党が憲法改正を目指していることは、よく知られていることです。
しかし、憲法を改正するには、国民投票で過半数の賛成を得ることが必要です。
そこで、その国民投票のやり方等を定めた「憲法の改正手続に関する法律」が平成19年に成立しました。この法律では、憲法改正のための国民投票権を有する年齢を満18歳以上と定めました。
その理由は、「国際的に国民投票権を有する年齢が18歳である例が多いこと」と、「憲法改正という重大な事由に関しては、多くの国民、特に将来の日本を背負って立つ若い人々に参加してもらうべき」というところにあります。
それだけではなく、若い層の投票を取り込みたい政治家の思惑もあると指摘されていました。
そして、国際的には、国民投票権を持つ年齢、選挙権を持つ年齢、成人年齢は一致していることが非常に多いことから、この法律の附則3条に公職選挙法、成人年齢を決める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることが定められました。
(2) 公職選挙法の改正と民法の改正へ
まず、平成27年6月に公職選挙法が改正され、選挙権を持つ年齢が満18歳以上となりました。
そして、この公職選挙法改正法の附則第11条に、民法、少年法その他の法令についても検討を加え、必要な法制上の措置を講ずることが記載されました。
さらに、民法の成人年齢も18歳に引き下げられることになりました。
しかしながら、世の中のすべての事柄が、民法上の「成人年齢」によって区別されているわけではありません。
例えば、15歳から遺言ができるなど、成人年齢と関係なく年齢制限が定められている条項があります。
また、選挙権は18歳に引き下げられましたが、国政に関する被選挙権(立候補する権利)は、衆議院議員で満25歳以上、参議院議員で満30歳以上と、成人年齢とは別の年齢が設定されています。
これは、やはり国民の代表となる者は、成人してすぐではなく、一定の社会経験を積んで成熟した者であるべきという理由からです。
このように、その「行為」に適した年齢は何歳なのかということは、民法上の「成人年齢」だけにとらわれることなく、個別具体的に検討されるべきなのです。
2.成人年齢と法律
(1) 飲酒

未成年飲酒禁止法の第1条1項は、「満20歳に至らざる者は酒類を飲用することを得す」と定めて、20歳未満の者の飲酒を禁止しています。
この法律の目的は、アルコールが成長期の身体にとって害があるため、成長期にある者を保護することにあります。
また、立法背景には、飲酒は喫煙と並んで、非行の温床になるから禁止した方が良いという考えもあったようです。
ビール酒造組合のホームページによると、「未成年者は、アルコールを代謝する働きが弱いこと」「アルコールは、成長期にある脳の神経細胞への影響が大きいこと、肝臓や膵臓などの臓器障害に陥りやすいこと」など、成長期にアルコールを摂取することの悪影響が指摘されています。
【参考】ビール酒造組合
そして、民法が成人年齢を18歳にしたからといって、アルコールが成長期にある者に与える悪影響が変わるわけではありません。急性アルコール中毒やアルコール依存症に対する対策も必要です。
そのような配慮から、この未成年飲酒禁止法によって、成人年齢が18歳になっても20歳未満の者の飲酒は認められないことに変わりありません。
(2) たばこ

未成年者喫煙禁止法の第1条は、「満20歳に至らざる者は、煙草を喫することを得ず」と定めており、20歳未満の者の喫煙は禁止されています。
厚生労働省によると、青少年期に喫煙を開始すると、成人後に喫煙を開始した場合に比べて、がんや虚血性心疾患などの危険性がより高くなるとのことです。
肺がんでは、20歳未満で喫煙を開始した場合の死亡率は、非喫煙者に比べて5.5倍となっているそうです。
また、たばこを吸い始める年齢が若いほど、ニコチンへの依存度が高い人が多くなるという報告もあるとのことです。
最近では、大人であっても受動喫煙が問題になるなど、たばこの害は健康に対する問題が指摘されています。
そこで、喫煙できる年齢を引き下げることは健康へのリスクを増やすだけとも言えますから、やはり、民法の成人年齢引き下げの後も満20歳未満の者の喫煙は禁止されることになっています。
(3) ギャンブル

ギャンブルは原則として刑法上の賭博罪に当たるのですが、競馬や競輪など一定のギャンブルは、それぞれ特別な法律によって認められています。
競馬や競輪、競艇、オートレースなどは「公営ギャンブル」と言われ、競馬なら競馬法、競輪なら自動車競技法、競艇には自転車競技法、オートレースには小型自動車競走法という特別法があります。
そして、どの法律を見ても、「未成年者」は投票権を購入することを禁止されています。そうすると、民法上の「未成年者」が、18歳未満になると、公営ギャンブルの投票権を購入できる年齢も18歳未満となってしまいます。
しかし、そもそも賭博は、人の射幸心を煽り、依存症になる危険を持つものですから、特に判断能力が未熟な若年者に安易に認めるべきものではありません。
このような法律の目的に照らし、民法の成人年齢が引き下げられたことに伴って、公営ギャンブルに関する上記4つの法律は、「満20歳未満の者」は投票権を購入できないと改正されました。
なお、パチンコは公営ギャンブルではなく、風俗営業法の規制を受けていて、民法の規定に関係なく従前から18歳未満が入店禁止です。
また、カジノ法案によると(年齢制限がIR実施法の条文に明記されているわけではありませんが)カジノには20歳以上が入場可能になっていると思われます。
(4) 少年法
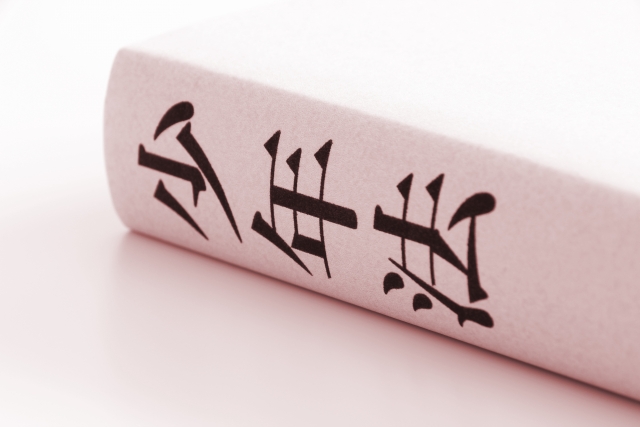
民法の成人年齢の引き下げに伴って、多くの人の関心があるのは「少年法」ではないでしょうか?
少年法では、「少年」の定義について、「二十歳に満たない者」と定めています。
しかし、改正民法の施行により令和2年に少年法が改正された結果、少年のうち18歳以上の者は特定少年とされ、その者が犯罪を犯した場合には、以前より厳しい処分が科される可能性が高くなりました。
18歳、19歳で悪質な少年事件を起こした者については、通常の刑事処分によって厳罰を受けさせることは可能なのです(もっとも、少年法の適用を受ける以上、実名報道されるかどうかなど、成人との扱いの違いはあります)。
また、少年であっても、「逆送致」といって、通常の刑事処分を受けさせる手続きもあります。
逆送致されるのは、下記のような場合です。
- (罪を犯したときに20歳ではなくても)調査・審判の段階で20歳であることが判明した者
- 死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき
- 故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの(ただし、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情は考慮される)
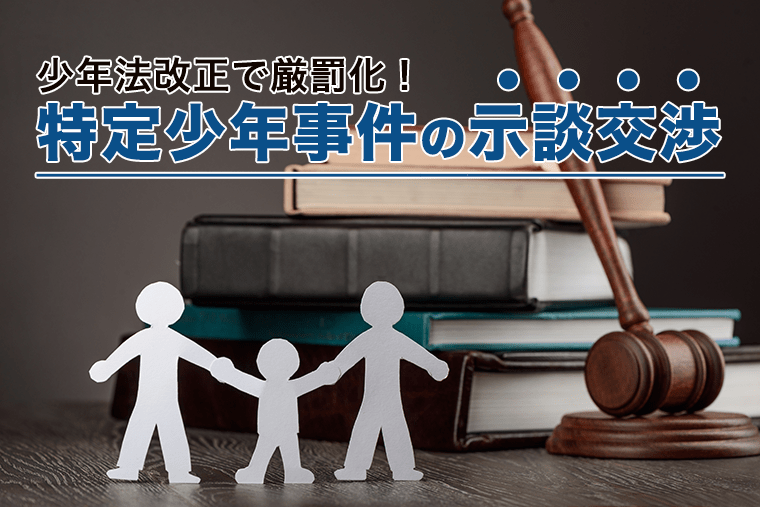
[参考記事]
少年法改正で厳罰化|特定少年事件の示談交渉
3.まとめ
世の中には、「成人」と「未成年」で区別されている事柄は多いですが、すべてが民法の成人年齢と連動しているわけではありません。
それぞれの法律には目的がありますから、その目的に従って対象年齢が決められることになります。
少年法改正後の運用については、今後の動向に注目しておくべきでしょう。