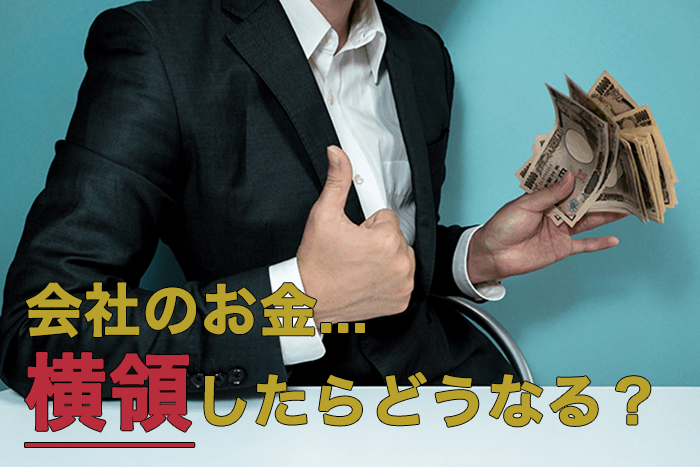レジのお金を盗む業務上横領罪の証拠について
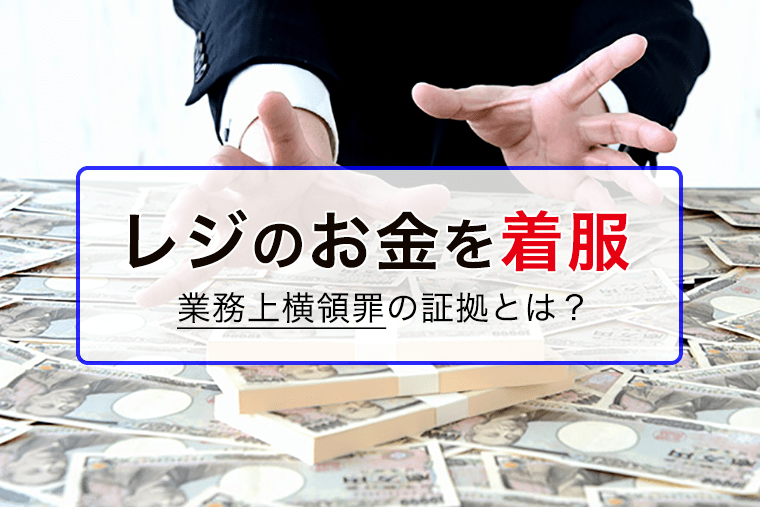
横領は立証が難しい、証拠がない、といわれることがありますが、それは本当なのでしょうか?
横領を証明するための証拠としてはどのようなものがあり、横領の被害に遭った会社の側ではどのようにして証拠集めをするのでしょうか?
この記事では、業務上横領罪の中でも、特に弁護士が相談を受けることが珍しくない「店舗のレジにおける業務上横領の証拠」について詳しく解説していきます。
1.業務上横領罪とは
まず、業務上横領罪の基礎知識について見ておきましょう。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
横領罪は、法律的な表現で説明すると、「他人との委託信任関係に基づいて占有している他人の財物を、委託の趣旨に反して領得する犯罪」となります。
ごく平たく言えば、「他人から預かった財産を着服する犯罪」です。
業務上横領罪の「業務」とは、これも法律的な表現で説明すると、「委託を受けて財物を管理(占有・保管)することを内容とする事務」となりますが、要するに「仕事として預かった場合」と理解すれば足ります。
このように、「店舗のレジ係が商品の販売代金を懐にいれてしまった」などの典型的な犯行は、業務上横領罪に該当します。
2.横領は立証が難しい?
横領の証拠はない、横領の立証は難しい、といった問題については、結論から言うとそんなことはありません。
預かったお金の使い込みですから、あるはずのお金がなければ着服は明白です。財産を預かった者が単数の場合は、むしろ横領罪の立証は容易でしょう。
ただ、同じ財産を着服する機会のあった者が複数存在する場合には、誰が着服したかを立証することが容易でないケースもあります。
店舗レジ係による着服は、まさにこれに当たります。
なお、証拠がないというケースは、委託した被害者の金銭管理がルーズで、いくら預けたのかわからない(被害にあったのかどうかもわからない)というようなパターンが考えられます。
3.店舗レジ係による着服行為の証拠について
さて、「店舗のレジ係が商品の販売代金を着服した」という業務上横領罪では、どのような証拠が考えられるでしょうか?
(1) 直接証拠としての目撃者や防犯カメラ
犯人のレジ係が、客から受け取った代金をレジに入れずにその場でポケットや自分の財布に入れてしまったという現場を目撃した人間の証言や、これを撮影した防犯カメラの映像があるなら、ことは簡単です。
しかし、一般的に犯人は着服がバレないように気を配るものですから、そのような決定的な直接的な証拠を得られるのは偶然の所産です。
また、偶然現場の目撃証言や動画が得られたとしても、多くの場合、そのような着服行為は比較的長期間にわたって反復継続されていますから、すべての損害に対応する全犯行を裏付ける証拠としては不十分です。
なお、現代の大手スーパーや百貨店などが導入しているレジスター機器は、①特定の従業員がその機械を使用した日時、②その従業員がその機械を使用している間に販売された商品とその代金額を、すべて記録しています。
さらに③商品名と代金額の入力はバーコードの読み取りで自動的になされ、④客から受け取った金銭を投入口から機械内に投入すると自動的に金額を読み取り、⑤機械が計算して自動的に釣り銭を排出するという自動化がなされています。
このシステムでは、商品バーコードの読み取りが間違いなくなされている限りは、機械への入金と出金は誤魔化しようがありませんから、およそ着服は不可能であり、仮に着服しても機械の記録が証拠となってすぐに犯人が判明します。
したがって、この記事で問題にするのは、少なくとも③④⑤の機能がないレジスターを使用している店舗での犯行についてです。
(2) 間接証拠(犯人を推認できる事実)
どのようなレジスターでも、売れた商品とその金額の記録は必ず残りますから、店舗側は「現金が足りない」ことにはすぐに気がつくことができます。
問題は「誰が着服したか」です。現実にレジ内に入った金額を自動記録できない機器では、この点がわからないことになります。
では、店舗レジ係による着服行為について、目撃者や防犯カメラといった直接的な証拠がない場合、他に証拠となるものは何があるのでしょうか?
直接的な証拠がない以上、間接的な証拠に着目するしかありません。
間接的な証拠とは、その従業員が犯人であることを推認させる事実です。
従業員の金遣い
例えば、「最近、高そうな服を着てくるようになった」とか「キャバクラでの遊び方が派手になった」などという事実もこれに含まれます。
「最近着てきた服の市販価格」や「行きつけのキャバクラで支払った金額」を調査し、給与水準に不相応な金銭を消費している事実があれば、犯人である可能性が高まるのです。
実際にスーパーの売上金が店員によって横領された事案で、その店員がキャバクラ嬢に50万円もする大画面高級テレビをプレゼントしたという噂が流れ、店舗側の調査によってそれが間違いなく事実であることが確認されて、犯人を特定する突破口となったという事件もありました。
その従業員が金銭に困っていたという事実があるなら、それも間接事実のひとつなのです。
日々のレジの集計記録からの推察
ただ、当然ですが、上記のような間接事実だけでは、着服行為を裏付けるには全く不十分です。
では、他に何が考えられるでしょう?
例えば、現金の集計は毎日行っているのですから、現金が足りなくなる日にそのレジを使用した従業員が誰かは容易に判明します。何日間にもわたって調べれば、着服した可能性のある従業員の人数は絞れるはずです。
現金が不足した日の全てにわたってその機械を使用していた従業員がただ一人しかいないという記録があれば、それは、その従業員こそが犯人であると推認する強力な間接事実となります。
現金の集計を、1日のうちに複数回行なっていれば、現金が足りなくなった時間帯を細かく特定することが可能ですから、より推認が容易になります。
4.まとめ
このように、店舗側が「売り上げを着服されているらしい」という疑念を生じさせたり、その実行犯を特定したりすることは案外容易なものです。
業務上横領罪での刑事処罰を避けるためには、対応を弁護士にお任せすることをお勧めします。
これについて、詳しくは以下のコラムで解説していますので、是非ご覧ください。
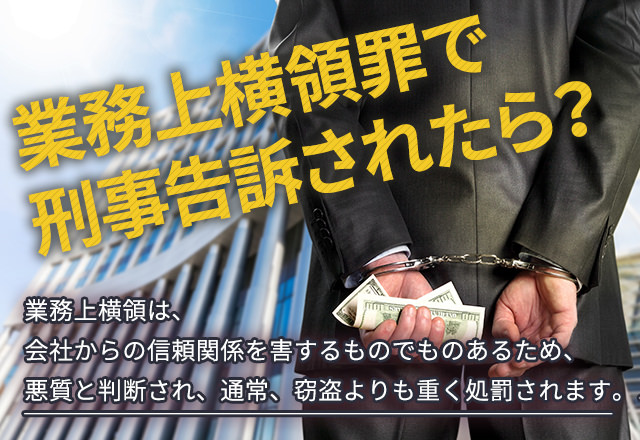
[参考記事]
業務上横領罪で刑事告訴・被害届!横領・着服事件の示談の重要性