無断録音した音声データ(録音テープ)は証拠能力があるのか?
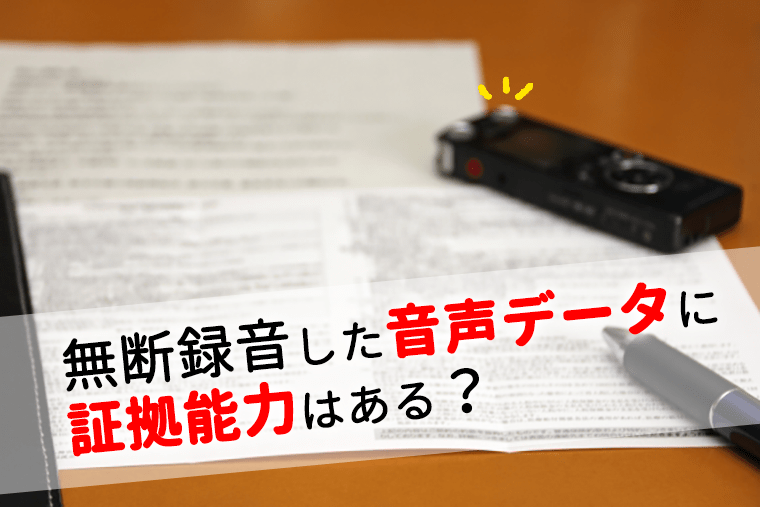
最近話題のパワハラや、政界のスキャンダルなどで、録音した音声データが注目されています。
皆さんの会社などで同様の事件が発生した場合、「ボイスレコーダー等で上司の発言を録って、これを証拠として提出したい!」と思うかもしれません。
しかし、相手に秘密で会話内容を録音することは犯罪になるのでは?と考える方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、無断録音それ自体は犯罪ではありません。
しかし、無断録音された音声データを証拠として使用できるかどうかはケースバイケースです。
以下では、無断録音データの証拠能力について説明します。
なお、ここに証拠能力とは、裁判において、ある証拠を証拠とすることができる資格ないし適格性のことです。
1.録音テープの証拠能力
そもそも、無断録音か否かにかかわらず、録音テープに証拠能力があるか否かは、証拠として提出する裁判が、刑事訴訟か・民事訴訟かで全く異なります。
また刑事訴訟の場合は、その録音内容が「供述録音」か「現場録音」かによっても全く異なります。
これは法律のイロハですので、ここに整理しておきます。
(1) 刑事訴訟の場合
刑事裁判における伝聞法則
ある情報が、人の知覚・記憶・表現・叙述というプロセスを経て法廷に証拠として顕出される証拠で、その内容が真実であることをもってある事実を立証しようとする場合、これを供述証拠と呼びます。
例えば、Aが「私は、B課長が女子社員C子の胸を無理矢理触るところを見た」という手紙を警察に送ったという場合、この手紙をBがCにわいせつ行為をした証拠とするためには、本当にAがBによるCへのわいせつ行為を見たこと、つまり、この手紙の内容が真実であることが前提となります。
しかし、人の知覚・記憶・表現・叙述というプロセスには、嘘や誤りが混入しやすいものですから、誤判を防止するためには、本当にAが「BがCの胸に触るところを見た」のか、その真実性を吟味しなくてはなりません。
最良の吟味方法は反対尋問です。ところが、当然ですが手紙それ自体には反対尋問をするわけにはいきません。
吟味ができないのであれば、この手紙を証拠とすることはできないことが原則です(刑事訴訟法321条1項3号)。これを伝聞法則と呼びます。
なお、もちろんAが証人として出廷して証言するなら、Aに対して反対尋問をしてその発言内容が真実かどうかを吟味することが可能ですが、その場合は法廷でのAの証言を証拠として採用すれば良いのであって、Aの手紙を証拠とする必要はありませんから、やはり原則として手紙の証拠能力は否定されます。
供述録音とは
さて、録音テープに「B課長がC子の胸を強引に触るところを見ちゃった」というAの発言が録音されていた場合、これをBがCにわいせつ行為をした証拠とするためには、この録音の内容が真実であることが前提となり、反対尋問での吟味が必要であること、録音テープ自体には反対尋問をすることはできないこと、発言者Aが出廷して証言し反対尋問を受ける場合には、その法廷での証言を証拠とすれば良いことは、手紙の場合と何ら異なりません。
したがって、この場合、録音テープの証拠能力は原則として否定されます。これを「供述録音」と呼びます。
現場録音とは
一方、録音テープに、C子の悲鳴が録音されていた場合に、これをC子が強制わいせつ罪の被害を受けた事実の証拠とするには、C子の発言内容が真実であったかどうかは問題となりません。
悲鳴をあげた事実それ自体が、犯行を推認する証拠となるからです。
そして録音テープは機械的な記録で、人の知覚・記憶・表現・叙述というプロセスはたどりませんから、C子が悲鳴をあげた事実それ自体は嘘や間違いがなく記録されていると評価できます。
したがって、反対尋問による吟味は不要であり、録音テープの証拠能力は認められます。これを「現場録音」と呼びます。
なお、もちろん、それが本当にC子の悲鳴かどうか、本当に犯行当日に犯行現場で録音されたものかどうか、偽造や修正がないかどうかは吟味されなくてはなりませんが、それは伝聞法則が適用されるか否かにかかわらず、証拠一般について要求される証明力の問題です。
(2) 民事裁判の場合
民事裁判においては、伝聞法則の適用はありませんから、供述録音であろうと現場録音であろうと、証拠能力が認められます(※最高裁昭和27年12月5日判決・民集6巻11号1117頁)。
2.刑事裁判の無断録音テープの証拠能力
録音テープの証拠能力は、刑事裁判においては「供述録音」の証拠能力は原則として否定され、「現場録音」の証拠能力は肯定されることがわかりました。
では、録音が無断であった場合、この結論が異なる結果となるのでしょうか?
同じく無断録音といっても、①当事者の承諾が全くない「盗聴」のケースと、②当事者の一部の承諾はあるケースに分けて考えられます。
(1) 第三者が会話当事者の同意なしに会話を録音する場合
会話当事者の承諾が全くないのに、その会話を盗聴して録音することは、当事者のプライバシー権・人格権や通信の秘密を侵害する重大な違法行為です。
そこで、例えば、最高裁の判例では、「捜査機関が電話の通話内容を当事者の同意を得ずに傍受することは、重大犯罪に関する十分な嫌疑があり、他の方法では重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの特別な事情がある場合に、裁判所の発する特別な検証許可状があることを条件に、刑事訴訟法上の強制捜査として例外的に許される」と判断していました(※最高裁平成11年12月16日決定)。
これは通信傍受法(正式名称「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」)制定前の判例であり、現在では、同法の要件を満たす場合に限って、強制捜査として認められます。
したがって、捜査機関が電話の会話を盗聴して録音したテープは、それが通信傍受法の要件を満たしておらず、令状主義の精神を没却する重大な違法がある場合には、違法収集証拠として排除され、証拠能力は認められません。
では、同様の行為が一般民間人によって行われた場合はどうなるでしょうか?
会話当事者のプライバシー権などが保護尊重されるべきことは、公権力でも私人でも違いはありません。
しかし、違法収集証拠の証拠能力が否定される理由が、「将来の違法捜査の抑制」と「司法の廉潔性(潔白性)の確保」にある以上は、捜査機関の依頼による場合で捜査の一環と評価できる場合や、違法の程度が著しく重大な場合には、同様に証拠能力を否定するべきでしょう。
(2) 会話当事者が相手方の同意なしに会話を録音する場合
私人である会話当事者の一方が、相手方の同意を得ないで会話を録音する行為はどうでしょうか?
この場合、侵害されるのは、せいぜい「私的な会話を相手に録音はされないだろう」という相手方の自由やプライバシーに対する期待にすぎませんから、一般的には、重要な利益を侵害したとまでははいえません。
そのため、違法とはいえず、刑事訴訟にあっても証拠能力は肯定されると解されています。
例えば、以下のような事例があり、録音テープの証拠能力が肯定されています。
- 私人Aが、殺人事件に関する被告人Xとの会話を録音した場合(松江地判昭57.2.1判時1051・162)
- 新聞記者Aが、取材の結果を正確に記録しておくため、相手方の同意を得ないで会話内容を録音した場合(最決昭56.11.20)
- 詐欺の被害を受けたと考えたAが、後日の証拠とするため、被告人Xとの会話を録音した場合(最決平12.7.12)
では、捜査機関が、会話当事者の一方の同意を得て会話を録音した場合はどうでしょうか?
この場合も、やはり相手方が侵害されるのはせいぜい期待権に過ぎませんから、重大な権利・利益を侵害するものとは言えず、刑事訴訟法上の強制処分にあたらないので、任意処分として許されます。
なお、任意処分であっても、刑事訴訟法上の捜査には必要性と相当性が要求されます(比例原則)から、一方の同意があることだけで常に許容されるわけではないことに注意するべきです。
3.まとめ
このように、刑事裁判において秘密録音が違法とされ証拠として用いること事ができない場合があります。
証拠があるから勝てるはずだと過信したり、録音テープをとられたから有罪になることが確実だと諦めてしまったり、素人判断をするのは早計です。
録音テープの証拠能力が認められず、不起訴処分や無罪を勝ちとることができる場合もあるのです。必ず、専門家である弁護士に相談するべきです。
まずはお気軽に、刑事弁護に強い泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。








