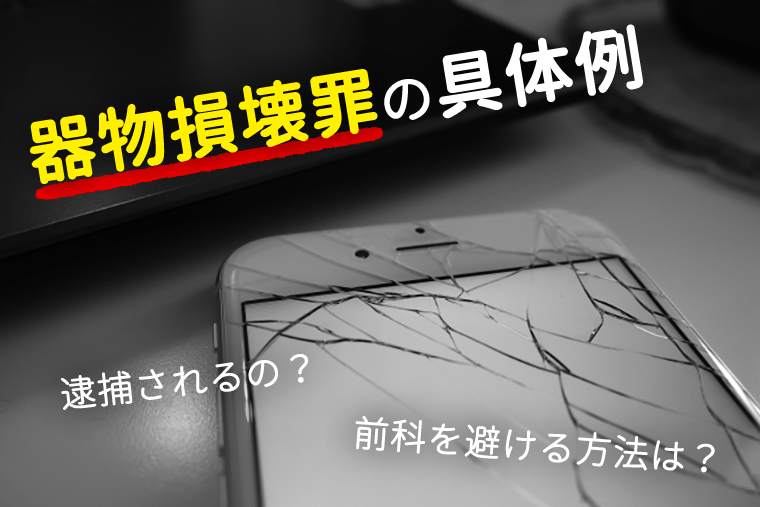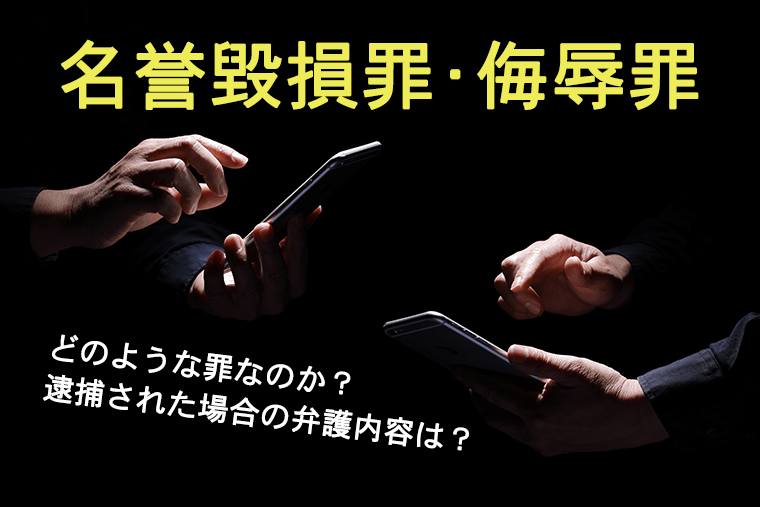クレーム電話で逮捕・罰金・懲役!?威力業務妨害罪とは?

「届いた商品が壊れていた」「サービスが期待した水準でなかった」
このような不満から、メーカーやサービス会社に電話で問い合わせたり、返金を要求したりすることもあるでしょう。
もちろん、これら行為自体は正当ですが、冷静さを欠いた、度が過ぎる発言・行動は、ただのクレーマーであって、最悪の場合は刑事事件に発展します。
今回は、よくあるクレーム電話が「業務妨害罪」になり得ること、そして「威力業務妨害罪」と「偽計業務妨害罪」の詳しい内容を解説します。
1.業務妨害罪とは?
刑法は、「業務を妨害した者」を処罰しており、これを業務妨害罪と呼びます。
刑法233条「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
刑法234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」
まず、妨害対象となる「業務」とは何かですが、判例によると、職業、その他の社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業を意味するとされます(大審院大正10年10月24日判決・大審院刑事判決録第27輯643頁)。
職業としての経済活動を典型とする社会生活上の活動であることが必要で、趣味としての散歩、学生の勉強のような「個人的な活動」、家事などの「家庭生活上の活動」、レジャーとしてのドライブのような「娯楽活動」は「業務」に含まれないとされています(山口厚「刑法各論(第2版)」有斐閣156頁)。
では、上のような業務を、どのように妨害すると犯罪となるのでしょうか。
先の条文で見たように、業務の妨害形態として、①虚偽の風説を流布すること(要するに「嘘の噂を流すこと」)、②「偽計」を用いること、③「威力」を用いること、という3つの行為が処罰対象とされていることがわかります。
①虚偽の風説の流布と②偽計は233条、③威力は234条と書き分けられているため、一般的には、233条を偽計業務妨害罪、234条を威力業務妨害罪と呼びます。
威力業務妨害罪も、「前条の例による」として、偽計業務妨害罪と全く同じ扱いとされているので、被疑者・被告人の側にとっては、偽計と威力を区別することに実益はありません。
他方、検察官が被疑者を起訴する際には、起訴状に公訴事実だけでなく、「罪名」と「罰条」(該当条文)も記載しなくてはならず(刑訴法256条2項3号、4項)、裁判官が有罪判決を下す際にも「法令の適用」を示さなくてはならないので(刑訴法335条1項)、実務の手続上は、犯行が「偽計」業務妨害で233条違反なのか、それとも「威力」業務妨害で234条違反なのか、その区別をつけなくては手続違反となってしまいます。
(1) 「威力」とは
威力とは、本来の言葉の意味は、「他をおさえつけて服従させる強い力・勢力」を意味します。
最高裁は威力とは、「犯人の威勢、人数及び四囲の状勢よりみて、被害者の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力」としています(※最高裁昭和28年1月30日判決)。
この判例は労働争議の事案で、複数の労働者が会社の工場に侵入し、工場長に団体交渉を求めた行為が威力業務妨害罪に該当するか否かが争われたケースなので、加害者が複数人であることを前提としていますが、もちろん、威力業務妨害罪は単独犯でも成立します。
威力業務妨害罪とされた例
- シュプレヒコールなどによりテレビの生放送に雑音をいれる行為
- デパートの食堂に蛇を撒く行為
- 数人で食堂内で怒鳴り散らし騒然とさせる行為
- 議場で発煙筒を焚く行為
- 開会中の国会で答弁する大臣に傍聴席からスニーカーを投げつける行為
これらの例から、非常に幅広い行為が威力業務妨害罪とされていることが理解できると思います。
(2) 「偽計」とは
偽計とは、本来の言葉の意味は、「人をあざむくこと。計略をめぐらせること」であり、偽計業務妨害罪においては、「人を欺罔・誘惑する行為や人の錯誤や不知を利用する行為」を広く含むと理解されています。
偽計業務妨害とされた例
- 駅弁が不潔・不衛生という葉書を鉄道会社に出した行為
- 新聞の購読者を奪うために、紛らわしい名称で体裁も似た新聞を発行した行為
- 漁場の海底に障害物を沈めて漁網を破損する行為
- 電話料金の課金システムを回避する機械を電話に取り付けた行為
- 寝具売り場の布団に縫い針を混入した行為
- 電気メーターに工作して実際より少ない電気使用量を示させた行為
偽計業務妨害罪も、威力業務妨害罪と同様に、とても幅広い行為が含まれていることが理解できるでしょう。
上に挙げた各裁判例から、威力と偽計の区別基準を読み取ることはなかなか難しいと言えます。威力も偽計も、共に内容が不明確で、様々な態様を含むので、両者の区別を厳密につけることは困難なのです。
ただ傾向としては、公然の行為か、非公然の行為かで分けられるという考え方が妥当でしょう。次の各意見が参考となります。
「相手の錯誤を誘発する行為が偽計で、相手の意思を制圧する行為が威力なので、公然と相手方に障害の存在を誇示する態様の場合は威力に分類されることになろう」、
「例えば、列車の座席に針を刺しておく行為は、待ち針を目に見える形で刺して、その存在を誇示することにより乗客に不安感を生じさせて輸送業務を妨害するのであれば威力業務妨害罪であり、目に見えない形で刺してあれば、偽計業務妨害罪にあたる」(前田雅英「刑法各論講義(第5版)」214~215頁)。
「本罪は端的に『業務の円滑な遂行』を保護するものとなって」おり、「その結果、偽計と威力の区別も本質的な意義を失い、単に業務妨害の手段が公然か非公然かという差異でしかなくなっている」(西田典之・橋爪隆「刑法各論(第7版)」142頁)。
2.クレーム電話は威力業務妨害罪にあたるのか
迷惑電話に関しては、中華料理屋に約970回の無言電話をかけた行為が偽計業務妨害罪とされた裁判例があります(東京高裁昭和48年8月7日判決・高等裁判所刑事判例集26巻3号322頁)。
この事案は、昼夜を問わず電話をかけ、店の者が客からの電話かもしれないと思って電話に出ると、無言を通したり、電話を放置したりして、そのままにする行為を繰り返していたというものです。
この裁判例では、相手を困惑させるような手段策術も偽計に含まれると理由づけています。
ただ、昭和48年当時は着信番号の通知システムや割込電話(キャッチホン)は普及しておらず、店側としては、電話があれば注文かも知れないと思って電話に出るしかなく、業務と無関係の無言電話に出なくてはならないという意味でも、無言電話がかかっている間は本当の客からの注文を受けることができないという意味でも、現実に業務が妨害されているわけです。
では無言電話ではなく、クレーム電話の場合はどうでしょうか?
クレーム電話は、それが真実、相手の業務へのクレームであり、常識的な回数であれば、その電話に相手が対応すること自体は「通常の業務行為」であって、何ら業務は妨害されていませんし、妨害の危険を生じさせる行為でもありませんから、威力業務妨害でも、偽計業務妨害でもありません。
しかし、上の中華料理屋の裁判例のように、執拗に多数回のクレーム電話をかけ続けたような場合には、その電話はもはやクレームを伝える行為ではなく、嫌がらせ目的であることは明らかであって、相手にこれへの対応を余儀なくさせることは、業務を妨害する行為であることは間違いありません。
そして、先の「公然・非公然」という区別基準からすると、クレーム電話は偽計による業務妨害行為に分けられるでしょう。
相手の店舗や事務所に出向き従業員に直接にクレームを伝える行為でも、それが何十回も反復されるときは、公然行為で相手の対応を余儀なくさせているので、威力業務妨害罪となるでしょう。
また、相手の店舗や事務所で、クレームを伝えるだけでなく、大声で怒鳴る、暴言を吐く、机を叩くなどの行為があれば、たとえ一回の行為であっても、威力業務妨害罪となる可能性があります。
もちろん、これに加えて、例えば「営業できなくしてやる」などと害悪の告知を伴えば脅迫罪、さらに金銭を要求する行為を伴えば恐喝罪となります。退去を求められて応じなければ不退去罪となる可能性も生じます。
3.威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪の弁護活動
威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪は懲役刑もあり、明らかに証拠隠滅や逃亡のおそれがない場合を除けば、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されれば、通常の場合、その後の勾留も含めると最大23日間も身体拘束を受けることになります。さらに、その期間内に起訴されれば99%の確率で有罪判決を受け、たとえ罰金刑や執行猶予判決であっても前科がついてしまいます。略式起訴による罰金刑の場合であっても同じです。
このような事態を回避するには、業務妨害行為が事実であるならば、早急に相手方に謝罪し、示談に応じてもらうことです。
弁護士を弁護人に選任し、被害者との示談交渉を担当してもらい、示談を成立させ、示談金を支払う代わりに、示談書に処罰を求めない旨を記載してもらうのです。告訴されているときは告訴状も取り下げてもらいます。
これにより被害が金銭的に回復され、処罰感情も無くなったことが明らかとなり、検察官が起訴不起訴の判断をする際に、被疑者に有利な事情として考慮され、起訴猶予処分を勝ちとることができる可能性が高くなるのです。
万一、起訴されてしまった場合でも、示談が成立していれば、裁判官の量刑判断において、被告人に有利な情状となります。
4.まとめ
商品の欠陥や不具合が散見される場合、泣き寝入りすることなくメーカー等に問い合わせをすること自体は、1人の消費者の行動として決して間違っているものではありません。
問題なのは「度が過ぎてしまうこと」です。そこでは、必ずしも回数だけということではなく、内容や話し方、電話を掛ける時間帯等も考えなければいけません。
正しい権利行使であっても、節度を保った行動を心がけることが大切と言えるでしょう。
相手方の商品などに問題がある場合には、消費者センターなど公的機関に相談されることもお勧めします。
万が一、威力業務妨害罪で逮捕されたてしまった方やそのご家族の方は、すぐに刑事に強い泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。