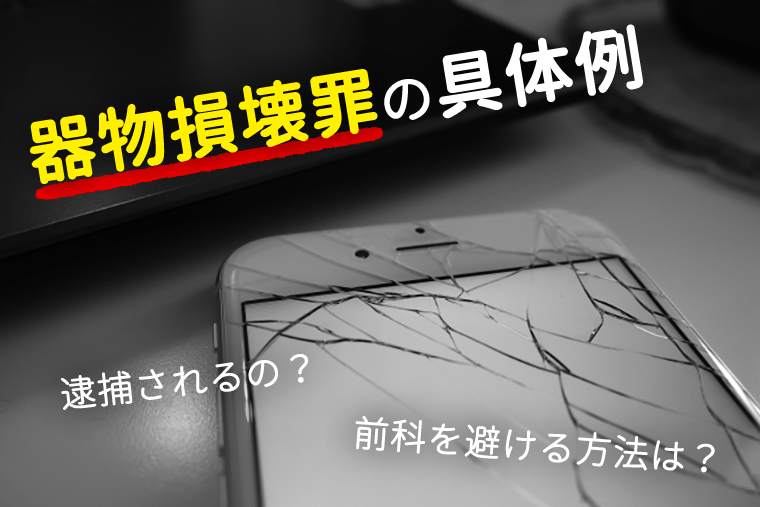名誉毀損罪・侮辱罪とは?不起訴処分に向けた弁護活動
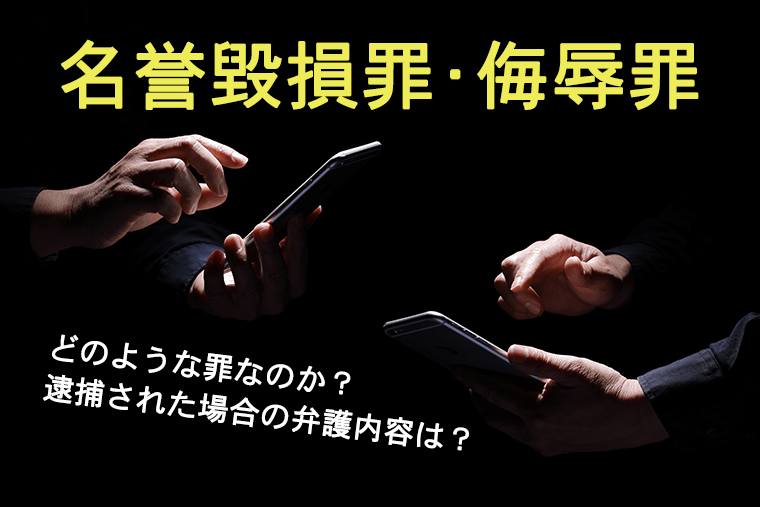
本人にそのつもりはない、軽い気持ちで行ったことだとしても、刑事事件では思わぬところで被疑者となってしまいます。
名誉毀損罪や侮辱罪などはその典型でしょう。
これらは誹謗中傷ともいわれ、インターネット上(SNS、匿名掲示板等)での芸能人に対する罵詈雑言などは昨今の社会問題となっています。
以下では、名誉毀損罪・侮辱罪の内容、弁護活動について解説します。
1.名誉に対する罪
人は、他人・世間からの評価を受けながら社会生活を送っており、その評価の高低は、当人の日常生活や社会活動に大きな影響を与えますから、不当に評価を貶められない利益は法的保護に値します。
刑法は、この利益を侵害する犯罪として、名誉毀損罪と侮辱罪を規定しています。
2.名誉毀損罪
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」によって成立します(刑法230条1項)。
(1) 名誉毀損の成立要件
同罪の客体(侵害の対象)は人の名誉です。「名誉」とは、人の価値に対する社会的評価をいいます。
人の価値には、行為や人格に関するものに限らず、身体的・精神的資質、政治的・学問的・芸術的能力、容貌、健康、職業など社会において価値があるとされているものの一切が含まれます。
ただ、経済的な支払能力は、信用毀損罪(233条)の保護法益とされていますので、ここにいう名誉には含まれません。
名誉毀損罪が「その事実の有無にかかわらず」(230条1項)と規定され、事実が真実であるか否かにかかわりなく犯罪が成立するとされていることから、人の価値に対する社会的評価は、人の真価と合致する必要はなく、虚名(実際の力以上の評価)もまた名誉として保護されます。
①「公然」とは?
「公然」とは、不特定又は多数人の認識し得る状態をいうとするのが判例(最判昭36.10.13刑集15・9・1586等)です。
すなわち、不特定の者が認識し得るのであれば、少数の不特定者でもよく、また、多数の者が認識し得るのであれば、特定された多数人でもよいのです。
さらに事実を摘示した相手が特定かつ少数人であっても、そこから不特定または多数人に伝播する可能性があるときも「公然」であるとするのが判例です(最判昭和34.5.7刑集13・5・641等)
インターネット上で誹謗中傷が行われたケースは、多くの場合、この公然性の要件を充足するでしょう。
②「事実を摘示」とは?
「事実を摘示」するとは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘・表示することをいいます。
このような事実である限りは、必ずしも悪事醜行に限らず(大判大7.3.1刑録24・116)、前述のとおり、その真否を問わず、たとえ公知の事実であっても、まだ事実を知らなかった者が知ることになる可能性がある以上、これに含まれるのです(大判大5.12.13刑録22・1822)。
事実を摘示する方法には特に制限はなく、口頭、文書・図画、身振り等のいずれでもかまいません。
事実は、事実そのものとしてではなく、風聞、噂、伝聞等の形で表示されても同じです。評価を低下させるというその効果において、事実そのものを表示したのと異ならないからです。
③「名誉を毀損」とは?
「名誉を毀損」するとは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を作出することをいいます。
現実に社会的評価が低下したことは必要ではありません(大判昭13.2.28刑集117.141)。現に社会定期評価が低下したかを証明することは困難ないし不可能だからです。
同罪の法定刑は、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金です。
死者の名誉を毀損する行為については、虚偽の事実を摘示した場合のみ罰せられます(230条2項)。歴史的評価の対象として、真実に基づく批判を許す趣旨です。
虚偽の認識が必要ですから、誤って虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損しても名誉毀損罪は成立しません。
ただし、名誉毀損行為の時点で被害者が生きていた限り、名誉毀損をした後、被害者が死亡したとしても、死者の名誉毀損の問題ではありません。生者に対する名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されません。
(2) 名誉毀損罪となる具体例
名誉毀損罪に該当すると判断された事例としては、以下のようなものがあります。
フランチャイズ飲食業を運営する株式会社○○食品について、「インチキFC○○粉砕!」「○○で食事をすると、飲食代の4~5%がカルト集団の収入になります」「まともな企業のふりしてんじゃねえよ」などとネット上のホームページに掲載した事案(最高裁平成22年3月15日決定)
ネット上の「こんな人間に腹が立つ」という名称の掲示板に、「馬鹿教師」という題名で、被害者である教師の実名をあげたうえ、「教育者であるのに校則を知らない」「うそをうそで塗り固める」と記載した事案(大阪高裁平成16年4月22日判決)
ネット上のホームページに、被害者である弁護士某について、「某は、数年前、自分の息子にテレクラをやらせ、男性関係で悩んでいる女性を探し出させて、弁護士としての自分のクライアントを獲得していたという」などと記載した事案(福岡地裁平成14年11月12日判決)
3.侮辱罪
侮辱罪は、事実を摘示しなくとも、公然と人を侮辱することによって成立します。
この犯罪も、名誉毀損罪と同様に、人の社会的な評価を保護するものであって、被害者の名誉感情を保護するものではないとするのが判例です。したがって、名誉感情を有しない幼児・精神病者も被害者に含まれます。
なお、先に見たように刑法は、より重い名誉毀損罪では死者の名誉に関する特別の規定を置いているのに対し、より軽い侮辱罪では格別の定めを置いていないことから、死者の名誉は侮辱罪の保護対象に含まれないと解されます。
「事実を摘示しなくとも」とは、「事実を摘示せずに」の意味であり、この点で名誉毀損罪と区別されるとするのが判例(大判大15.7.5刑集5・303)です。
このように侮辱罪も名誉毀損罪も社会的評価を低下させる行為を処罰するものであり、具体的な事実を摘示する行為の方が、評価が下がる危険が大きいことから、名誉毀損罪で重く処罰されます。
したがって、「侮辱」とは、具体的事実を摘示しないで、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断(侮蔑的表現)を不特定または多数人の認識できる状態にすることをいいます。
侮辱罪においても、たんなる名誉感情は保護対象ではありませんから、相手方の名誉感情を害することを要しません(前掲大判大15.7.5)。
また、侮辱の方法には、特に制限はありません。
例えば、「Xは馬鹿だ」「Xは浮気者だ」「X社は悪徳企業だ」などと多衆の前で言った場合には侮辱罪が成立します。
これに対し、「Xは毎回テストで0点ばかりとっている馬鹿だ」「Xは今も浮気をしている浮気者だ」「X社は、欠陥商品を売りつけている悪徳企業だ」という各表現は、具体的な事実の摘示を含みますから、侮辱罪ではなく、名誉毀損罪の対象です。
同罪の法定刑は拘留(1日以上30日未満の身体拘束)又は科料(1000円以上1万円未満の金銭の支払)です。
4.名誉に対する罪のまとめ
| 名誉毀損罪 | 侮辱罪 | |
|---|---|---|
| 客体(保護対象) | 人の名誉(社会的評価) | |
| 行為 |
|
|
| 処罰 | 3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金 | 拘留又は科料 |
| 時効 | 3年 | 1年 |
5.名誉毀損罪・侮辱罪の弁護活動
もともと名誉に対する罪で起訴される人数は少なく、起訴の場合も、公判請求ではなく略式起訴(公開の法廷で裁判が行われない)が多いと指摘されています。
そして、悪質でなければ、告訴の有無にかかわらず、逮捕されることも稀です。また、逮捕されたからといって、必ず前科がつくというものではありません。
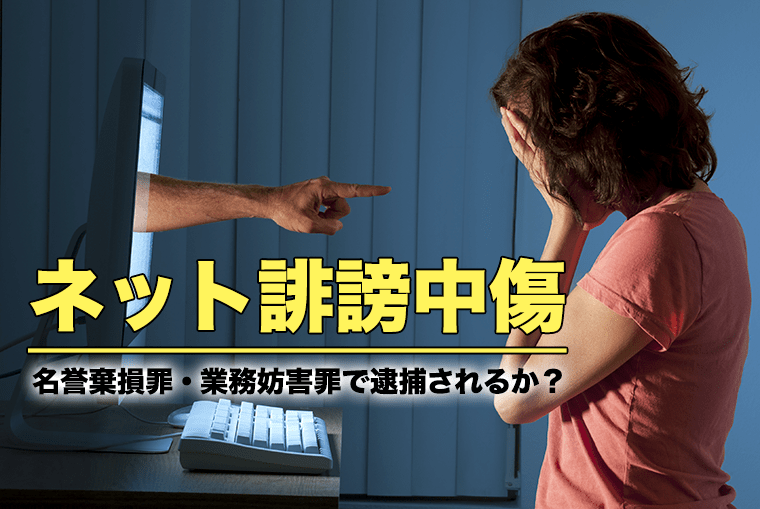
[参考記事]
ネットの誹謗中傷で逮捕される?|名誉棄損罪・業務妨害罪
しかし、仮に起訴されて略式手続を経て罰金刑が科された場合、前科がつきます。そのため被疑者としては、略式起訴であっても起訴を免れたいでしょう。

[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
罪を犯した事実があっても、検察官の裁量により起訴されない場合(起訴猶予)には、刑事裁判が行われませんので、その罪が前科として残ることはありません。
起訴猶予の多くは、弁護士が被害者と示談交渉して示談を成立させたことによるものです。
しかも、名誉毀損罪と侮辱罪は親告罪(起訴するには被害者の告訴がなければならない犯罪)ですので、検察官は被害者の告訴がなければ起訴することはありません(232条1項)。したがって、被害者の告訴がなければ、不起訴処分で終わることになります。
さらに、多くの場合、被害者との示談は、示談金の支払いと引き換えに、被害者が告訴を思いとどまったり、すでになされた告訴を取り下げたりすることを約束する内容となります。
被害者に対する誠意ある謝罪と慰謝の措置を講じることで、早期に示談が成立すれば、被疑者に有利な処分結果が出ることが期待できるのです。
6.まとめ
本人に大きな悪気がなくても、名誉毀損罪や侮辱罪で警察に検挙され、逮捕されてしまうことがあります。
また、刑事事件化されなくても、被害者から民事訴訟を提起され損害賠償請求(慰謝料請求)を請求される可能性もあります。
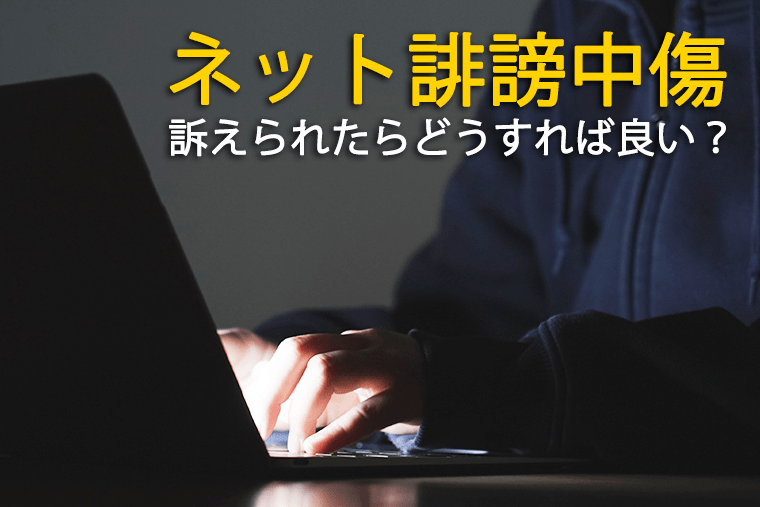
[参考記事]
ネット誹謗中傷で訴えられたらどうすれば良い?
自分自身で対応するのは限界があります。他人に誹謗中傷をしてしまった方はお早めに弁護士にご相談ください。
被害者と示談することで不起訴になり、前科がつくことを免れることができる可能性があります。