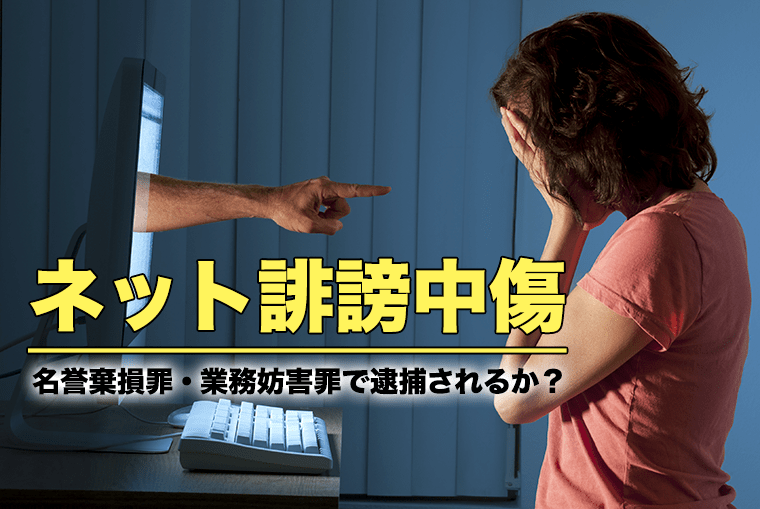判例で見る – スポーツ競技における犯罪(傷害罪)の成否

日大アメフト選手が、危険なタックルを行い、関学大アメフト選手に怪我を負わせたということで、世間の耳目を集めるとともに、監督・コーチの指導方法にも批判が注がれ、ある意味では、大きな社会問題にもなっています。
では、アメリカンフットボールの試合中の出来事であれ、いわゆるスポーツ競技中に相手選手に怪我を負わせたような場合、加害選手は罪に問われるのでしょうか。問われるとすれば、その判断基準はどこにあるのでしょうか。
以下においては、スポーツ競技中に起こり得る犯罪、違法性が阻却される根拠と理由、スポーツ競技上での行為が刑事事件となる可能性、どのような場合に、スポーツ競技中の傷害罪等で逮捕されるのか、スポーツ競技において刑事責任が問題となった事例などに触れながら、スポーツ競技における犯罪の成否について解説することとします。
なお、以下の刑法における条文は、単に条文番号のみを掲げています。
1.スポーツ競技中に起こり得る犯罪
これまで、刑事事件などの裁判例で問題になった事例を前提としますと、スポーツ競技中に相手選手に傷害を負わせた場合には、傷害罪、業務上過失傷害罪の構成要件に、また、死亡させてしまった場合には、傷害致死罪、業務上過失致死罪の構成要件に、一応該当することが考えられます。
しかし、スポーツ競技との関係でみてみますと、下記2.のように、特に格闘技の場合、競技者は暴行罪や傷害罪の構成要件に該当するわけですが、その行為が処罰されることがないのは、理論上、違法性が阻却されるからであると解されています。
この理は、基本的に、格闘技以外の他のスポーツ競技においても当てはまるとされています。そうはいっても、スポーツ競技中であれば、いかなる行為であっても、違法性が阻却されることになるわけではないでしょう。
では、スポーツ競技においては、いかなる要素によって、行為の違法性が阻却されるのか、その具体的な判断基準を検討してみましょう。
まず、下記において、上記犯罪の成立要件と刑罰を確認し、次いで、違法性が阻却される根拠と理由について、下記2.で取り上げ考えてみることにします。
傷害罪(204条)
人の身体を傷害することによって成立します。15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。業務上過失傷害罪(211条前段)
業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害させることによって成立します。5年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。傷害致死罪(205条)
身体を傷害し、よって人を死亡させることによって成立します。3年以上の有期懲役が科せられます。業務上過失致死罪(211条前段)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させることによって成立します。5年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
2.違法性が阻却される根拠と理由
⑴ 根拠
スポーツ競技中の死傷結果が、通常の場合、違法性を欠く根拠については、正当業務行為ないし正当行為になるとの見解と、危険の引受け又は被害者の承諾の理論による見解があります。
その理論構成はともかく、スポーツ競技中の死傷結果につき、35条を根拠に違法性が阻却されるという結論は、通説的見解とされています。
35条は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と定めています。社会生活上、正当なものとして許容される行為につき、それが特定の構成要件に該当する場合であっても、違法性が阻却され、処罰されない旨を規定したものです。
文言上は法令行為と正当業務行為が正当行為として挙げられていますが、これは例示でして、上記のような性質を有する行為は、広く35条の正当行為として違法性が阻却されると解されています。以下においては、正当行為として説明することとします。
⑵ 理由
スポーツ競技における行為が、プロであれアマチュアであれ、正当行為として違法性が阻却されるのは、裁判例や学説によりますと、スポーツ競技の目的で、一定のルールを守ってそれが行われたこと、また、被害者の同意の範囲内で行われたこと、という正当化事由が認められる場合ということになります。
要するに、当該スポーツにおいて通常予想され許容される行為に起因して、結果的に相手選手に死傷を負わせたとしても、その結果は被害者の同意の範囲内にあることから、正当行為として違法性が阻却され、傷害罪等は成立しないと解されているのです。
3.スポーツ競技上での行為が刑事事件となる可能性
⑴ 競技上の正当性
スポーツは、基本的には身体を動かすことを目的としていますので、スポーツ競技中に自らが怪我をしたり、他人に怪我をさせたりするという危険は、現実問題として、避けられないことです。
特に、レスリング、ボクシング、空手、柔道、相撲といった格闘技は、直接的に相手の身体を攻撃しますので、相手に怪我をさせるどころか、場合によっては死に至らしめる危険性も孕んでいます。
では、同じコートやフィールド内で一つのボールを奪い合い、ボールの行方が得点に結び付き、結果的に勝敗を左右することになる、アメリカンフットボール、サッカー、ラグビー、ハンドボール、バスケットボールなどの競技の場合は、どう考えたらよいのでしょうか。
プレーをしている選手は、ボールを持っている相手チームの選手だけでなく、そのボールの捕り手となる相手チームの選手、場合によっては味方チームの選手に対しても、ボールを奪うため、あるいはボールが放たれるのを阻止するなどのために、行動を起こした際に、敵味方を問わず、他の選手と接触するだけでなく、身体をぶつけ合ったり、タックルしたり(アメリカンフットボールやラグビー)、結果的に足を攻撃することになったり(サッカー)するのが、一般的と考えられます。
このように、自らも含め、人の身体に対する危険を内在しながら勝負を争う競技は、その競技で是認されるルールの範囲内で、選手が一定の危険を冒すことが容認されているといえます。
競技によっては、コート(テニス、バドミントン、バレーボール)や台(卓球)を異にし、味方選手同士の接触はあっても(テニス、バドミントン、卓球のダブルスやバレーボール)、基本的に、相手選手と接触することがないスポーツもあります。
また、野球やソフトボールでは、相手選手と走者の間でも、身体に対する危険を伴うとはいえ、投手が打者に与えるデッドボールで、死亡や重大な傷害が生じることがあるため、刑事責任の可能性が問題となります。
しかし、この場合も、その競技で是認されるルールの範囲内にある限り、打者は投手の投げミスを容認しているといわざるを得ません。
以上のように、それぞれの競技で是認されるルールの範囲内にある限り、たとえ死傷の結果が生じたとしても、そのスポーツ競技の目的に照らし、結果を招来した相手選手の行為は、被害者の同意の範囲内にあると考えられますから、違法性を欠くものと解されるのです。
⑵ 違法性のある行為
では、上記の違法性を欠くとはいえない、すなわち、当該行為に正当化事由が認められない場合とは、どのような場合をいうのでしょうか。
抽象的な言い方をしますと、被害者に死傷の結果を招来した当該加害行為が、そのスポーツ競技の目的に照らし、本来であれば、当然遵守しなければならない基本的なルールからも逸脱し、被害者にとっても、競技において通常考えられるプレーの範疇から大きく逸脱した、想定外の行動であり、被害者の同意の範囲内にあるとは到底いえない場合、当該行為には違法性を阻却する正当化事由が認められず、犯罪として成立すると解せられると思われます。
そこで、日大アメフト選手(以下「当該選手」といいます)の行為について検討してみますと、当該選手は、関学大のクォーターバック(QB)の選手(以下「相手選手」といいます)が、パスを投げ終えて無防備な状態になっているのに、加害意図をもって、相手選手に対し、相手チームのボールを奪うなり、阻止する必要性がないのに、当該スポーツ競技のプレーとは関係のないタックルに及び、その結果、全治3週間の傷害を負わせたもので、いかなる意味でも、その行為に正当化事由があるとは認められず、傷害罪が成立するといわざるを得ません。
では、当時の監督やコーチの刑事責任はどうなるのでしょうか。
あくまでも、当該選手の発言や第三者委員会の中間報告に基づくという前提に立った場合ですが、監督やコーチには、教唆犯(61条)あるいは共謀共同正犯(60条)が成立する可能性が高いと思われます。
4.どのような場合にスポーツ競技中の傷害罪等で逮捕されるのか
スポーツ競技中に、ルールを逸脱した行為により、相手選手に怪我を負わせたとしても、競技中であるだけに、現行犯逮捕されることは、一般的には考えられないでしょう。
そこで、通常逮捕されるとしたら、どのような場合なのかについて、考えてみることにします。
一般論としては、犯罪を犯した事実があっても、必ず逮捕されるわけではありません。
捜査官は、被疑者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがある場合に、裁判官から逮捕状の発付を得て、逮捕するのが原則となっています。
したがって、そのようなおそれがないなど、明らかに逮捕の必要がない場合には逮捕されないことになります(刑訴法199条2項)。
ここにいう、罪証隠滅のおそれとは、証拠に対する不正な働きかけによって、判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりするおそれがあることをいいます。
物的な証拠品を壊したり隠したりすることはもちろん、事件の目撃者や関係者と接触して口裏合わせを行うことなども含まれます。
そして、逮捕の必要性とは、捜査上、身柄を確保しておく必要のあること、具体的に言いますと、その主たるものは、被疑者の逃亡のおそれ、又は、被疑者による罪証隠滅のおそれを防止する必要のあること(刑訴規則143条の3)を意味します。
実務的には、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重及び態様等を総合考慮して、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを判断するわけですが、ことスポーツ競技に関する限り、一般的には逃亡のおそれは考え難いため、罪証隠滅のおそれが問題となります。
スポーツ競技中の傷害等では、特に、動機、計画性の有無、犯行態様の悪質性、手段方法、組織性、結果の軽重、共犯者の有無、社会的影響等が重視されると思われます。
これらの解明の必要性が高く、口裏合わせや働きかけが現実に行われ、今後更なる罪証隠滅がなされれば、当該関係者の刑事責任の追及が困難になるような場合には、逮捕の可能性が高まるといえます。
5.スポーツ競技において刑事責任が問題となった事例
⑴ 大阪地判昭62.4.21判時1238・160(空手練習における傷害致死事件)
【事案の概要】
本件は、被告人が、深夜路上で、親しい友人といわゆる「寸止」ではなく、空手の練習としてお互いの身体を殴打・足蹴りする技を掛け合っていた際、相手が攻撃してくるのに対応するうち、興奮のあまり、被害者に対して一方的にその胸部・腹部・背部等を数十回にわたって手拳で殴打したり、皮製ブーツを着用した足で足蹴りして転倒させるなどの暴行を加え、その結果、被害者を死亡させた。
被告人は、傷害致死罪で起訴され、懲役2年の実刑に処せられた。
【判旨】
そもそも、スポーツの練習中の加害行為が被害者の承諾に基づく行為としてその違法性が阻却されるには、特に「空手」という危険な格闘技においては、単に練習中であったというだけでは足りず、その危険性に鑑みて、練習の方法、程度が、社会的に相当であると是認するに足りる態様のものでなければならず、被害者の受傷内容、死因、練習経験・実力からみた被告人と被害者の立場、暴行の態様、練習の日時場所を考慮すれば、本件のように、練習場所としては、不相当な場所で何ら正規のルールに従うことなく、かかる危険な方法、態様の練習をすることが右社会的相当行為の範囲内に含まれないことは明らかであって、被告人が空手の練習としては許されると認識していたとしても、被告人の本件行為は違法なものであるといわなければならない。
【説明】
判決は、空手の当該練習が社会的に相当な行為の範囲内に含まれないとして、違法性の阻却を認めなかったものです。
違法性阻却の判断要素としては、被害者の承諾だけでなく、被害者の受傷内容、死因、練習経験・実力からみた被告人と被害者の立場、暴行の態様、練習の日時場所を挙げ、総合的に行為の違法性の有無を判断しています。
⑵ 大阪地判平4.7.20判時1456・159(拳法練習における傷害致死事件)
【事案の概要】
本件は、大学の日本拳法部の部員である被告人が、下級生の部員が退部届を出してきたため、練習名目で制裁としての暴行を加え、その結果、脳挫傷により被害者を死亡させた。
被告人は、傷害致死罪で起訴され、懲役1年6月の実刑に処せられた。
【判旨】
スポーツとして行われる格闘技及びその練習が正当行為として違法性を阻却されるためには、スポーツを行う目的で、ルールを守って行われ、かつ相手方の同意の範囲内で行われることを要するものと解される。
本件は、被害者が退部届を出したことに憤った被告人が、被害者に退部を思い止まらせ、また他の部員が退部するのを防ぐ見せしめのため、制裁として行ったものと認める外なく、心身の鍛錬に基づき技を競い合うというスポーツの練習を行う目的でなされたものとは到底認められない。
本件においては、互いに防具の着用が全く不十分なままで行われており、外形上も到底日本拳法のルールが守られていた正規の練習とは言えない。さらに、被害者は、被告人の「稽古」の申し出を明示的には拒絶していないけれども、先輩からの申し出を拒絶できない立場にあったため、やむなくこれに応じたものであり(被害者の本件直前の退部届の提出によっても、被害者の心情は十分に窺うことができる)、被害者には本件「稽古」について真意に基づく同意があったものとは認められない。
被告人の本件行為は、日拳部の練習時間、練習場所において行われたものであるが、いかなる観点からもスポーツとして是認される日本拳法の練習とはいえず、それに名を借りた制裁行為と見るべきであり、到底正当行為と見ることはできないというべきである。
【説明】
判決は、格闘技における違法性阻却の判断要素として、スポーツを行う目的で、ルールを守って行われ、かつ相手方の同意の範囲内で行われることを挙げています。
⑶ 千葉地判平7.12.13判時1565・144(ダートトライアル同乗者死亡事件)
【事案の概要】
本件は、非舗装路面を自動車で走行し、所要時間を競うダートトライアル競技の初心者であった被告人が、7年程度の競技歴を有する被害者から、乗せて欲しいと頼まれて同乗させ、三速ギアでの高速走行中、急な下り坂カーブにさしかかる際、被害者から「ブレーキ踏んで、スピード落として」などと言われたが、カーブを曲がり切れずに走行の自由を失い、コースの左側山肌に車両左後部を衝突させ、次いで、コース右側の丸太の防護柵に車両前部を激突させ、防護柵の支柱が被害者の胸部を圧迫して被害者を死亡させた。
被告人は、業務上過失致死罪で起訴されたが、無罪判決を受けた(確定)。
【判旨】
①被害者の危険の引受けについて
上級者が初心者の指導のために同乗するような場合、同乗者は転倒等によって自己の生命、身体に重大な損害が生じる危険性についての知識を有しており、技術の向上を目指す運転者が一定の危険を冒すことを予見していることもあること、そのような同乗者には、運転者への助言を通じて一定限度でその危険を制御する機会もあること、このようなダートトライアル競技の危険性についての認識、予見等の事情の下で同乗していた者については、運転者が右予見の範囲内にある運転方法をとることを容認した上で・・・それに伴う危険・・・を自己の危険として引き受けたとみることができ、右危険が現実化した事態については違法性の阻却を認める根拠がある。
もっとも、死亡や重大な傷害についての意識は薄くても、転倒や衝突を予測しているのであれば、死亡等の結果発生の危険をも引き受けたものと認めうる。
②被害者を同乗させた社会的相当性について
ダートトライアル競技は既に社会的に定着したモータースポーツであり、本件走行会も車両や走行方法などJAFの定めたルールに準じて行われていたこと、競技に準じた形態でヘルメット着用等をした上で同乗する限り、他のスポーツに比べて格段に危険性が高いものとはいえないこと、スポーツ活動においては、引き受けた危険の中に死亡や重大な傷害が含まれていても、必ずしも相当性を否定することはできないことなどによれば、被害者を同乗させた本件走行は、社会的相当性を欠くものではないといえる。
③結論
本件事故の原因となった被告人の運転方法及びこれによる被害者の死亡の結果は、同乗した被害者が引き受けていた危険の現実化というべき事態であり、また、社会的相当性を欠くものではないといえるから、被告人の本件走行は違法性が阻却されることになる。
【説明】
判決は、危険の引受けという概念を用い、被害者が引き受けていた危険の現実化というべき事態であり、また、社会的相当性を欠くものではないとして、違法性が阻却されると判断しています。
6.まとめ
刑事裁判での日本の有罪率は、99.9%と言われています。そのため、まずは不起訴を目指すことが最重要となるでしょう。
刑事事件で逮捕され、起訴されそう・起訴されてしまったという方は、お早めに刑事事件に詳しい泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。刑事事件に強い弁護士が、事件解決まで親身になってサポート致します。