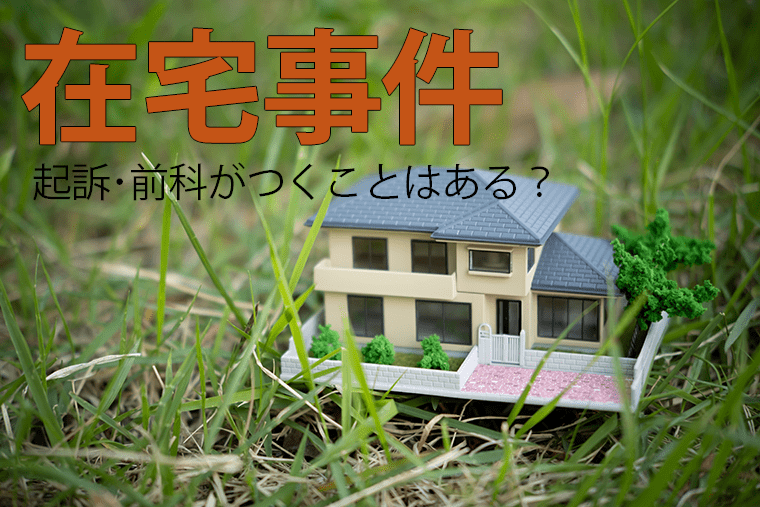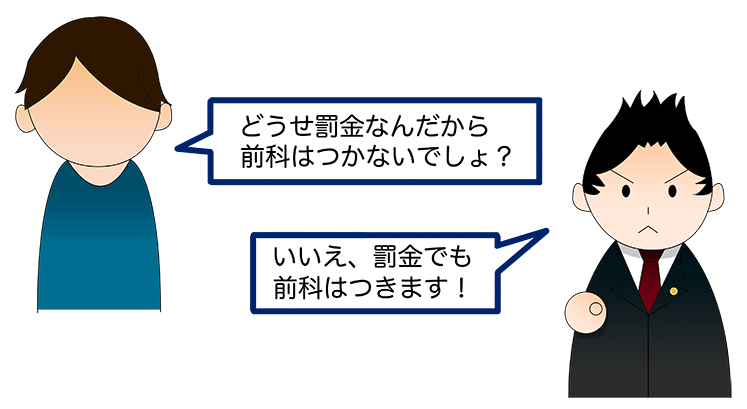贖罪寄付・供託により本当に情状が考慮されるのか?

刑事事件においては、被害者がどうしても示談に応じてくれない場合には、贖罪寄附や供託などの手段をとって、この事実を情状の一つにしてもらいます。
「情状」とは、被疑者・被告人の処分を考えるときに、考慮される一切の事情です。
被疑者や被告人にとって、「よい情状」もあれば、「悪い情状」もあります。犯罪の軽重、手段・方法、結果、社会的影響、動機、年齢、過去の境遇、普段の行状、前科前歴、反省の有無、謝罪の有無や被害弁償の有無などが「情状」となります。
贖罪寄附や供託をしたという事実は、被疑者等にとって「よい情状」となり、不起訴を勝ち取ることができたり、量刑が軽くなったりする可能性があります。
この記事では、刑事事件における贖罪寄附・供託について解説します。
1.贖罪寄附・供託とは?
(1) 贖罪寄附とは?
贖罪寄附は、日弁連及び各地の弁護士会が設けている制度です。贖罪、つまり罪を償う気持ちで弁護士会にお金を寄付すると、弁護士会が贖罪寄附を行ったという証明書を発行してくれますので、これを情状証拠として検察官に提出することができます。
寄附されたお金は、日弁連・弁護士会が行っている、人権の擁護と社会正義を実現する活動のための法律援助事業基金に充当されます。
法律援助事業基金は、弁護士による法律援助を必要とする人たちのために使用されます。
(2) 供託とは?
供託とは、民事上の制度です。
民法494条
債権者が、弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。
弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
被害者がどうしても示談に応じてくれない場合、「被害者が弁済の受領を拒んでいる」として、示談金を法務局に供託し、被害者がいつでも受け取ることができるようにします。被害者には、供託されたことの通知が送付されます。
(※被害者が弁護人にも住所を教えてくれない場合には、検察官に通知してもらうことになります。)
供託は、被害者がいる犯罪でしか利用できません。あくまで「示談金を預けておく」という制度であり、お金を寄付する贖罪寄附とは性質が異なります。
2.贖罪寄附・供託の効果
贖罪寄附や供託をしたという事実は、以下のようなタイミングで「よい情状」として考慮してもらえることになります。
(1) 起訴するかどうかの判断
まず、検察官が事件について「正式起訴するか」「略式請求するか」「不起訴にするか」を決めるときの情状になります。
刑事訴訟法248条では、起訴するかどうかの判断基準となる情状として、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、犯罪後の情状などが挙げられています。
この「犯罪後の情状」に、示談の成立、謝罪の有無の他、贖罪寄附・供託の有無が含まれます。
正式起訴になると裁判となり被疑者・被告人の負担が大きいですが、略式起訴なら罰金を支払うことによりすぐに釈放されます。
不起訴ならば、その後刑事事件について捜査を受けること自体ありません。
(2) 量刑の判断
起訴された後の刑事裁判で量刑を決めるときにも、贖罪寄附や供託は関係してきます。執行猶予にするか、実刑にするか、実刑にする場合でもどのくらいの刑にするのかを決めるときに、情状証拠は非常に重要です。
刑法66条では、「犯罪の情状に斟酌すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」とされています。そのため、「よい情状」を一つでも多く作ることは大事なことです。
(3) 被害者がいる犯罪は示談が最も有効
情状で一番重要と言えるのは「示談」です。
示談が成立しているということは、被害者に被害弁償をしている、つまり、被害を受けた人に慰謝の措置が講じられているということです。
贖罪寄附は公益のために使われるとはいえ、被害者本人の手元にはわたりません。
供託も、被害者がいつでも示談金を受け取れる状態であるとはいえ、被害者がこれを受け取っていないということは「被害者の怒りがまだ大きい、厳罰を望んでいる」ということが伺えますので、情状の効果は示談よりも劣ると言えます。いくら贖罪寄附や供託をしても、示談と同程度の効果までは見込めないということです。
それでも、日弁連が行ったアンケートによると、贖罪寄附や供託が情状に反映されたと感じた弁護士は約8割にのぼるとのことです。
確かに、贖罪寄附・供託を行ったからといって、必ず不起訴となったり、執行猶予を獲得できたり、刑が短くなったりするわけではありません。
贖罪寄附や供託は情状の一つにすぎず、他の情状によって、贖罪寄附や供託の効果が相殺されてしまうことはあります。
それでも、何もしないよりは、「謝罪の気持ちを口だけでなく行動でも現わしている」ということは、「よい情状」として受け取ってもらえるでしょう。
3.贖罪寄附・供託が有効な事件
(1) 被害者がいない犯罪
被害者がいない犯罪とは、例えば、覚せい剤などの薬物犯罪や、スピード違反・無免許運転など、人身事故が発生していない交通犯罪などです。
このような被害者がいない犯罪では、示談をすることができません。示談に代わる情状証拠として、贖罪寄附をすることは有効です。
(2) 被害者が示談を拒否している(示談できない)場合
犯罪を起こしてしまった場合、まず救われるべきは被害者であることは当然です。そのため、ぎりぎりまで示談の努力をしなければいけません。
しかし、被害者がどうしても示談に応じてくれないことはあります。
その場合に、「示談の努力をしました」という事実も情状の一つにはなりますが、示談金を供託しておくと、被害者がいつでも受け取ることができるので、より有利な情状となります。
ただし、重い犯罪を犯したのに少額の供託をしただけでは、かえって被害者を怒らせるだけということもあります。その場合には、贖罪寄附を選ぶ方がいいという判断もありえます。
被害者がいる犯罪では供託と贖罪寄附のどちらを選ぶかは、被害者の気持ちも考慮し、慎重に判断する必要があります。
4.贖罪寄附・供託の金額
では、どのくらいの金額を贖罪寄附したり、供託したりすればいいのでしょうか?
これは、支払う側である被疑者の資力や事案の軽重によって異なるとしかいいようがありません。
供託の場合は、被害者が受けとれるように示談金として相当な金額を供託します。
示談金とは、民事上の損害賠償金の支払のことですから、実際の被害額(例えば、万引きした物の代金や傷害の場合の治療費など)は当然支払わなければいけませんが、それだけではなく、これに慰謝料もプラスして払います。慰謝料にはだいたいの相場があるので、弁護人に確認してください。
そして、示談で払おうと思う金額に事件の日から年5%の遅延損害金をプラスしたものを供託します。
(※遅延損害金が「事件の日から年5%」なのは、示談金が民法上は不法行為に基づく損害賠償だからです。)
贖罪寄附では、示談金全額に相当する金額を寄附する必要はありません。自分の資力、犯罪の内容やその他の情状を考えて、弁護人と相談して金額を決めましょう。
5.示談、贖罪寄附・供託は弁護士にご相談ください
刑事事件を起こしてしまった場合、何もしないと罰金刑や正式裁判となってしまう可能性が高いです。
たとえ示談が難しいような案件でも、贖罪寄附や供託を行うことで少しでも刑を軽くすることができるかもしれません。
刑事事件を起こしてしまい、示談、贖罪寄附・供託を行いたいと考えている方は、ぜひお早めに泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。