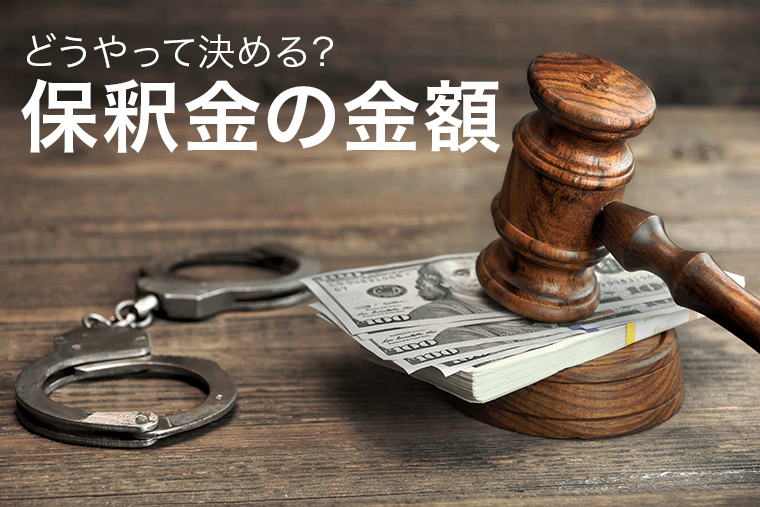追起訴されたらどうなる?再逮捕との違い

一度起訴され、その裁判の継続中に別の事件で起訴されることを追起訴と言います。
追起訴されると、保釈や判決などに何か影響があるのでしょうか?また、追起訴と再逮捕とは何が違うのでしょうか?
1.追起訴と再逮捕
逮捕とは、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間(最大72時間)の身柄拘束を継続することです。
この逮捕中に勾留決定がされると、引き続いて長期間(最大20日間)の勾留に入ります。
検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の情状などから、勾留期間が終わるまでに事件を起訴にするか不起訴にするかを決めます。
起訴とは、検察官が犯罪の有無とその量刑の判断を求めて、裁判所に公訴を提起することです。
起訴されたら、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになり、起訴後の勾留が始まります。起訴後は、保釈の請求ができるようになります。
(1) 追起訴とは?
上記のような逮捕から始まる一連の流れは、「起訴」も含め事件ごとに行うことになります(事件単位の原則)。
Aの罪とBの罪を同時に起訴することもありますが、その場合でも、「Aの罪は起訴するかしないか」「Bの罪は起訴するかしないか」ということを検察は別々に判断しています。
そして、すでにとある事件で起訴されて刑事手続きを受けている途中の被告人について、別の事件で起訴することを追起訴といいます。
よくある追起訴では、覚せい剤所持と覚せい剤使用、窃盗の余罪(複数の万引き)などがあります。
例えば、覚せい剤の所持の事件で逮捕・起訴された人が警察署で尿検査を受けたところ、覚せい剤の成分が尿から検出されたという場合、覚せい剤の使用という別の事件が発覚したということですから、覚せい剤「所持」で起訴された被疑者は覚せい剤の「使用」の容疑で再逮捕・追起訴されます。
窃盗では、同じ本屋で複数回万引きしたとしても、「11月1日の万引き」と「11月20日の万引き」は別の事件で、犯罪は2つということになります。
なお、関連した事件でなければ追起訴してはいけないということではありません。例えば、万引きで逮捕された人が覚せい剤も使用していたという場合は、万引き(窃盗罪)での起訴のあと覚せい剤使用で追起訴されるということになります。
また、万引きで逮捕された人が、数年前に起きた傷害罪の犯人であると判明したら、窃盗罪で起訴された後、傷害罪で追起訴されるということもありえます。
(2) 追起訴と再逮捕の違い
再逮捕されたからといって、必ず追起訴されるとは限りません。起訴するかどうかは、検察官がその事件ごとに決めます。
例えば、Aの罪で逮捕された人に、Bという余罪が見つかったため、Bの罪で再逮捕されたとします。この人は、まず、先に逮捕されたAの罪で起訴されました。
しかし、Bの罪を捜査した結果「示談が成立していた」「証拠不十分である」などの理由によって、不起訴が相当であると検察官が考えた場合には、Bの罪での追起訴はないということもありえます。
一方で、再逮捕がなく、追起訴されることもあります。
逮捕は、証拠を隠滅したり、逃走したりされないように身柄拘束をして捜査をするために行います。
しかし、Aの罪で逮捕された人は、すでに身柄拘束されています。そしてこの人は、Aの罪で起訴されたあとも(保釈が許可されていない限り)起訴後勾留されている状況です。
そこで、重ねての身柄拘束が必要ではないと判断されれば、再逮捕せずにBの罪の捜査を行って、Bの罪について追起訴することもあります。
例えば、覚せい剤の所持と覚せい剤の使用であれば、先行している覚せい剤所持事件での起訴前勾留・起訴後勾留の期間を利用して、覚せい剤の使用についても捜査して、追起訴することはよくあります。
なお、重い罪の捜査をするためにごく軽い罪で逮捕して、余罪捜査をすることは「別件逮捕」と言わます。
2.追起訴されることでどのような影響があるか
(1) 裁判の期間が長くなる
刑事裁判の手続きは、「冒頭手続き→検察側の主張立証→弁護側の主張立証→論告求刑→最終弁論→判決」という流れで行われます。
これが、追起訴があると、「Aの罪の冒頭手続→Aの罪の検察側の主張立証→Bの罪の冒頭手続→Bの罪の検察側の主張立証→弁護側の主張立証→論告求刑→最終弁論→判決」となるので、裁判の日数が増え、裁判の期間が長くなります。
もちろん、裁判員裁判対象事件でも、追起訴があると裁判がすべて終わるまでの期間は長くなります。
(2) 保釈申請の時期が遅れる
起訴されると、保釈を申請することができるようになります。
ただ、Aの罪で起訴されたとき、Bの罪で追起訴が見込まれる場合は保釈が認められにくくなります。
Aの罪での保釈が認められたあとにBの罪の捜査のために再逮捕されると、再び身柄拘束されてしまうため、意味がないからです。
(3) 保釈金が高額になる
さらに、追起訴されることで大きな影響があるのが保釈金です
保釈も事件単位で判断されます。そのため、保釈が認められた場合の保釈金も起訴されている犯罪ごとに納める必要があります。
そうすると、起訴されている犯罪の数が多くなり、保釈金額も高くなる可能性があります。
(4) 情状が悪くなり判決内容に影響が出る可能性
追起訴されたからといって必ず執行猶予がつかなくなるということはありません。
あくまでも、起訴されたすべての事件の情状から「懲役何年にするか」「執行猶予をつけるかどうか」が判断されます。つまり、追起訴の有無・数は情状の一つにすぎず、執行猶予がつくかどうかに直結するわけではないということです。
ただ、追起訴が多いということは、犯した犯罪の数が多いということですので、情状が悪くなることは確かですのでこの点は覚えておきましょう。
3.追起訴された際に弁護士ができる弁護活動
では、追起訴に対して、弁護士が行う弁護活動とはどのようなものでしょうか。
弁護士は、Aの罪での弁護を引き受けたからといって、Aの罪だけの弁護活動をするというわけではありません。被疑者からは前科前歴の有無や家族関係などの情状に関する事情も聞き取りますし、それ以外に必ず余罪はないか、それは再逮捕や追起訴がされそうな案件なのかということも聞き取りをします。
つまり、弁護士は余罪の存在も念頭に置きながら弁護活動を行うのが通常であるということです。
そして、Bの罪の捜査が開始したらBの罪についても早急に示談交渉を開始するなど、複数の事件の中でも、不起訴が見込めそうな案件については追起訴されないように(不起訴に持ち込めるように)弁護活動を行います。
また、追起訴された場合には、保釈の申請において、裁判官に対して適正な保釈金が多額にならないように、保釈金の金額について交渉することもできます。
4.刑事事件で逮捕されたら弁護士に相談を
逮捕された人に余罪がある場合、例え隠していたとしても、捜査の過程で明らかになることによって再逮捕・追起訴されることがあります。
もし、刑事事件で逮捕されてしまった場合、刑事事件の弁護経験が豊富な泉総合法律事務所の弁護士に早めに刑事弁護をご依頼ください。専門家が最後まで誠心誠意サポートいたします。