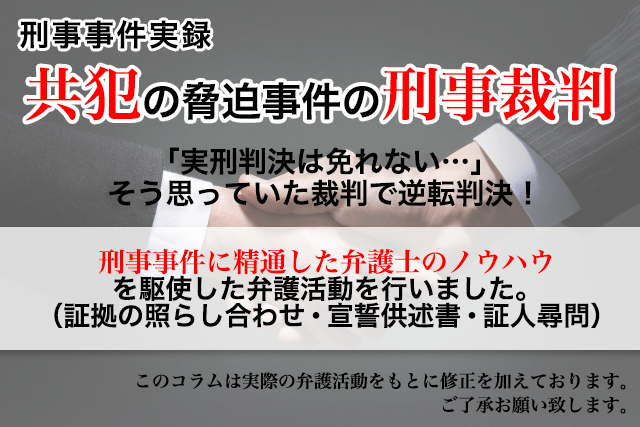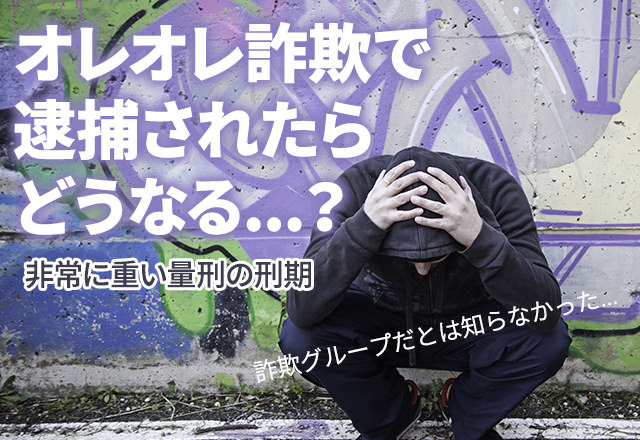否認事件の解決事例|黙秘を貫き不起訴を勝ち取った詐欺事件

今回は、泉総合法律事務所所属弁護士の刑事弁護事例(解決事例)をご紹介いたします。
当事務所の否認事件に対する弁護のあり方を、具体例を元に紹介させていただきます。
黙秘を貫き不起訴を獲得(詐欺・商標法違反)
事件内容
ある日、「警察から被疑者として何度か呼び出され、取り調べを受けている」という依頼者(被疑者)が事務所にご相談にいらっしゃいました。疑われているのは詐欺罪、そして商標法違反ということでした。
具体的には「インターネットオークションで本物のブランド品として出品し売却したものが、実は偽物だった」というものでした。
本人の主張(否認)
依頼者(被疑者)がそのブランド品を出品しそして売却したことは間違いありませんでした。
しかし、依頼者はそれが本物のブランド品だと思っていた、つまり、偽物であるとの認識がありませんでした。
このような場合、詐欺及び商標法違反の「故意」がなく、罪には問われない、ということになります。
刑事弁護活動の内容
弁護士の経験上、このような否認事件は、いずれ間違いなく逮捕される事件であると感じられました。そこで、依頼者にはその覚悟をしてもらったうえで、逮捕されてから弁護士が面会に行くまでの対応をアドバイスしました。
数日後、警察から依頼者を逮捕したという連絡が入りました。
このような状況で弁護人が直ちに判断しなければならないことは、捜査機関の取調べで、依頼者に話をしてもらうのか、それとも一切話をしない(つまり黙秘をしてもらう)のかです。

[参考記事]
黙秘権とは?黙秘権を行使するメリット・デメリット
当事務所としては、捜査機関に話をするメリットがない限りは、基本的に黙秘をするべきだと考えています。
そこで、この事件で依頼者が捜査機関に話をするメリットがあるかを考えました。
事件の争点は故意の有無
この事件の争点は、依頼者に詐欺や商標法違反の故意があったかどうか、つまり、依頼者が「出品したブランド品が偽物であることを認識していたかどうか」です。
このような人の内心の証明は、その人自身の供述に限るため、非常に困難なものとなります。
このような場合、捜査機関は被疑者自身にその事を認めさせようと躍起になって取り調べを行います。それは、刑事裁判の大原則として、被疑者が有罪であること(この事件で言えば依頼者が偽物であると認識していたこと)は捜査機関が証明しなければならない、というルールがあるからです。被疑者には、自分が無実であることを証明する義務はありません。
このルールは、国家権力を使って捜査をする側と、一個人でしかない被疑者との力の差を考え、公平にするために定められたものです。
故意でないことの証明には客観的な証拠が必要
依頼者がいくら「偽物だとは知らなかった」と言い張ったとしても、それだけではあまり意味はありません。依頼者が「偽物だとは知らなかったこと」を裏付ける別の客観的な証拠が必要となるのです。
実は、依頼者自身も、今回出品していたブランド品をインターネットオークションで購入していました。しかも、購入元は出品したのと同じサイトにおいてです。
そして、その際の購入金額は、明らかに本物のブランド品であることを前提とした非常に高い金額でした。
これらのことは、捜査機関であれば依頼者が何も言わなかったとしても、絶対に捜査し見つけることが出来る事実です。
そして、当事務所の弁護士は、この事実だけで依頼者自身も本物だと騙されて購入した被害者であることが明らかになると確信しました。
これらのことを考えて、私は依頼者が捜査機関に話をするメリットはないと判断しました。そこで、依頼者に黙秘をするよう指示しました。
勾留後に釈放され不起訴処分に
弁護士は身柄解放活動なども並行して行いましたが、残念ながらすべて認められず、依頼者は約20日間勾留されてしまいました。
しかし、依頼者には、おそらく身柄解放は認められず、20日ほどの拘束になることはあらかじめ伝えておきました。そして、なぜ黙秘をするべきなのかもしっかりと説明し、依頼者にもきちんと納得してもらいました。
依頼者は弁護士との約束をしっかり守ってくれましたが、長期の勾留となると精神的にも疲弊してしまうため、弁護士も頻繁に依頼者の元に面会に行きました。
結果、依頼者は勾留最終日に釈放され、後日、不起訴処分となりました。
黙秘の重要性について
刑事事件では、どんな事件であっても、被疑者となった人は捜査機関の取り調べを受けることになります。
そして、特に否認事件では、取り調べに対する対応がその後の結末を大きく左右します。
否認事件における弁護士は、黙秘をすべきか話をするべきかを即座に判断し、取り調べに対するアドバイスをしなければなりません。
一度被疑者の方が話をしてしまい、それが証拠として残ってしまえば、その後は黙秘しても効果は大きく下がるからです。
多くの弁護士は、「黙秘をさせる必要があるか」という考え方をしています。
しかし、当事務所の方針としては、話をするメリットがない限り基本的には黙秘をするべきというものです。ことに否認事件の場合には、それが鉄則だと考えます。

[参考記事]
黙秘権とは?黙秘権を行使するメリット・デメリット
【取り調べはほとんどが撮影されている】
現在、裁判員裁判対象事件では、警察・検察での取り調べのほぼすべてがビデオで撮影されています。また、裁判員裁判対象事件以外の事件でも、否認事件の場合には、検察での取り調べはほとんどが撮影されています。
昔は、警察官などが取り調べの最後に作成する「供述調書」に署名をしなければ、何を話しても証拠として扱われることはありませんでした。しかし、現在は状況が違います。話をしている依頼人の姿がすべて録音・録画されており、それ自体が証拠になる危険があるのです。供述調書に署名しなかったからといって、その録音・録画映像が証拠として使えなくなることはありません。
泉総合法律事務所は否認事件も全力で弁護をいたします
泉総合法律事務所は、各支店の男性弁護士全員が刑事事件弁護に取り組んでおり、それぞれの弁護士が豊富な刑事弁護経験を持っております。
刑事事件専門の弁護士事務所と同等の実力と実績がありますので、逮捕されて被疑者になってしまったという方は、どうぞ泉総合法律事務所にご相談ください。
否認事件であっても、各弁護士が釈放・不起訴に向け、全力で弁護活動をいたします。