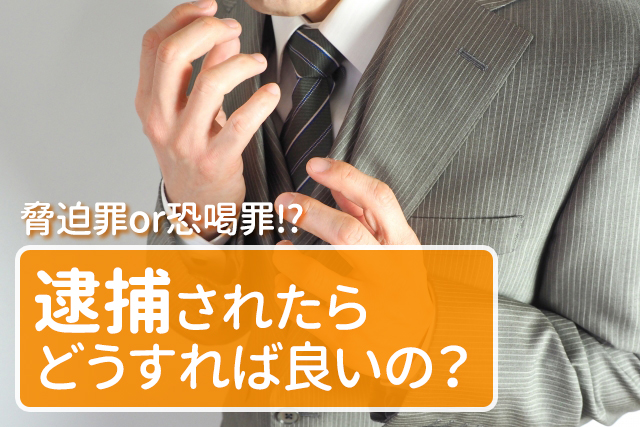共犯事件で否認している被疑者の刑事裁判|脅迫事件で執行猶予を得た事例
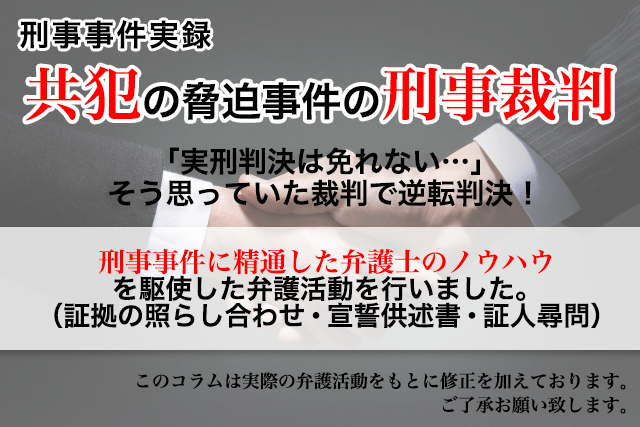
1名が脅迫を首謀して、もう1名がそれを手伝ったとの内容で逮捕・起訴され刑事裁判となった案件で、脅迫の首謀者とされた被告人の公判弁護を担当したことがありました。
今回は、このような共犯事件の否認事件の弁護実績(解決事例)をご紹介します。
なお、本コラムは実際の弁護活動をもとに若干の修正を加えておりますので、その点ご了承お願い致します。
1.共犯事件の特徴
共犯事件では、共犯者がお互いに自身の罪を軽くしようとして、「他方が首謀者で、自分は従犯(協力者)である」と主張し、お互い他方に首謀者を押し付け合うことが往々にしてあります。
これは、警察官、検察官、弁護士、裁判所も承知のことですので、検察官が取り調べをする時もこの点に念頭に置いて、共犯者間の罪の押し付け合いがないかどうかを慎重に見極めて起訴をするものです。
弁護士も同様に、共犯者間の罪の押し付け合いがないのかを留意点として、他の共犯者の言い分、弁護している被告人の言い分を吟味して判断する必要があります。
2.脅迫罪の共犯事件(否認事件)の弁護実録
事件の概要
本事件において、首謀者とされた被告人にはすでに私選弁護人がついていたのですが、その私選弁護人に不安を抱いたとのことで、紹介者を介して泉総合法律事務所に弁護依頼がありました。
首謀者とされた被告人は、脅迫事件に関与したことは認めるものの、首謀者はもう一人の共犯者だと主張していました。
泉総合法律事務所に弁護依頼が来たのは、従犯とされた他の1名の共犯者が執行猶予判決を得て判決が確定した後でした。
そうなると、通常であれば、脅迫の首謀者とされた被告人は本当に首謀者である認定され、実刑判決は十分あり得ると考えられました。
裁判所は、被告人が起訴事実を認めている場合には、被告人は反省していると考えます。一方、被告人が否認していてかつ証拠がある場合には、被告人は反省していないと受け止めるものです。
また、脅迫事件は被害者との間で示談が成立していれば執行猶予付き有罪判決が確実視されます。しかし、本件では被害者の被害感情が強いため示談ができず、犯行態様も悪質で執拗と評価されるものでした。
なお、共犯事件は通常同じ公判で審理されますが、首謀者とされない従犯(協力者)の被告人が起訴事実を認め、首謀者とされた被告人が起訴事実を否認している場合には、別々に審理されます。
刑事弁護の内容
有効な弁護方針が決まらない中、先に執行猶予判決を受けたもう1名の共犯者が、「実は自分が犯行を主導した首謀者だ」と供述しているとのことが担当弁護士に伝わってきました。
そこで、その共犯者が実際にそのようなことを供述しているのかどうか、直接弁護士だけが会って確認することにしました。
その共犯者から詳しい話を聞きながら、手元にあった客観的証拠も付き合わせ、その方の供述が確かなものかどうか確認していきました。その結果、本当の首謀者は共犯者の方で間違いないと考えられました。
その共犯者が述べたことが真実であること、自らの意思で述べたことを後で撤回されないよう、公証人役場で宣誓供述書にしてもらうことにしました。
【宣誓供述書とは】
宣誓供述書は、本人が供述したことを文書にしたものについて、公証人の前で本人に内容が間違いないことを述べてもらい、公証人がその点を証明する書類です。あまり作成することはない文書ですが、本件ではこの宣誓供述書を裁判所に証拠として提出するとともに、脅迫の従犯と認定された共犯者を証人申請しました。
結果、共犯者に対して、担当弁護士から証人尋問の主尋問を行い、首謀者は証人自身であり被告人は従犯(協力者)であるとの証言を得ることができました。
判決言い渡し、執行猶予の逆転判決
証人尋問と被告質問を終えると、最後に、検察官は「論告求刑」、弁護人は「弁論要旨」というそれぞれ主張・考えを述べて結審となります。
検察官の論告求刑の内容は従来通りの主張を維持したもので、被告人は首謀者であり実刑を科すべきだとの内容でした。
通常、結審から2週間後に判決言い渡しとなります。
判決言い渡しは、被告人は脅迫の首謀者ではなく従犯(協力者)であり、首謀者は他の共犯であるとの認定となりました。
結果、検察官の実刑サイン(検察官が実刑を科すべきだと主張すること)にもかかわらず、本件は執行猶予付き有罪判決となりました。
今回の執行猶予判決について、検察官控訴はありませんでした。
3.刑事裁判は泉総合法律事務所にお任せください
今回の案件では、弁護を担当している共犯者の言い分と客観的証拠との関係から、共犯者間の罪の押し付け合いは「ある」と判断できました。
それを立証して裁判所に納得してもらうことは難しい事案でしたが、分離された公判で従犯と主張し執行猶予判決を先に取り付けた共犯者が、自らの保身(執行猶予判決)を得ることができたことから、真実を述べる気になったことで、首謀者ではないとの被告人の主張が裁判所に認められて、被告人の執行猶予判決を得ることができました。
泉総合法律事務所は、在籍しているどの弁護士も様々な刑事事件に取り組んでおりますので、刑事事件に関与して逮捕されたり起訴されたりした場合には、是非ともご相談・ご依頼ください。