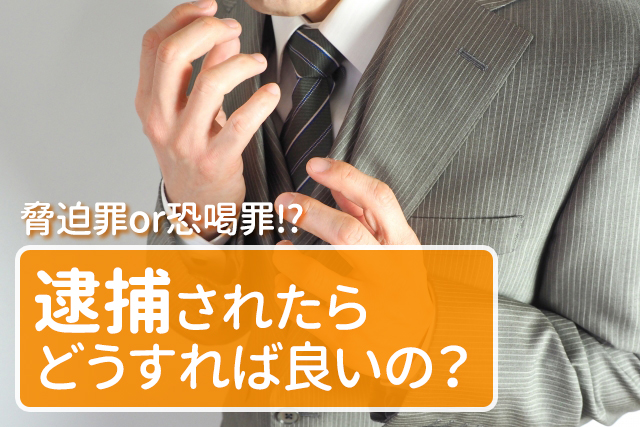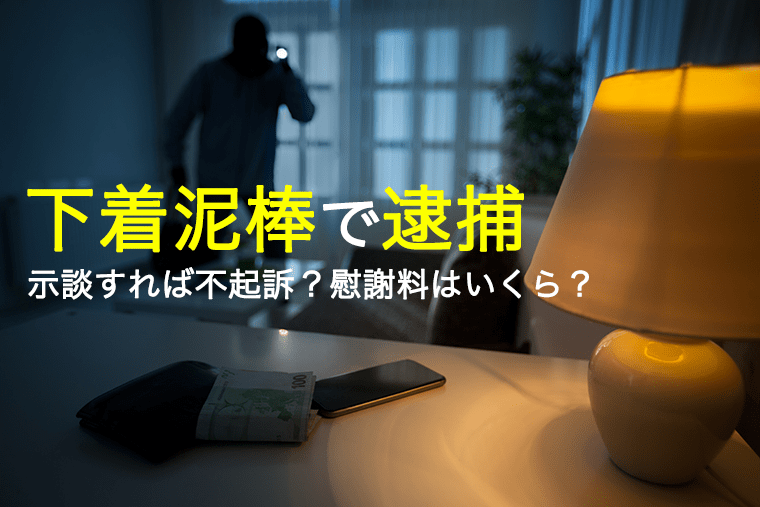事後強盗罪とは?窃盗罪・強盗罪との違い
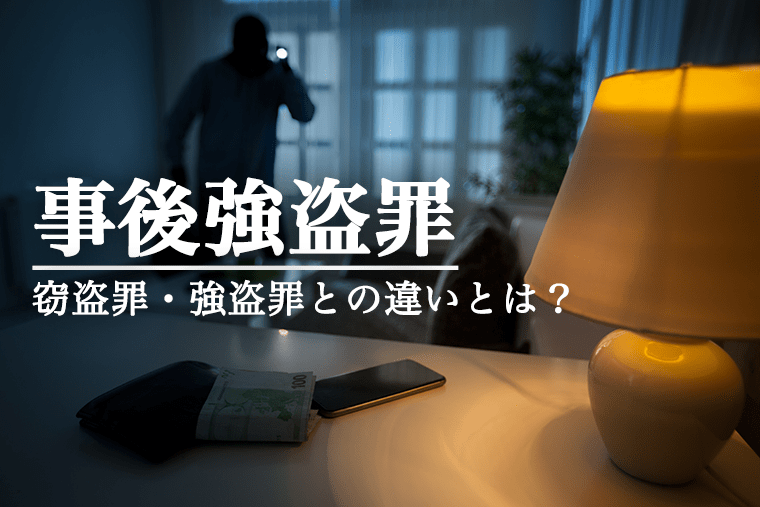
「強盗罪」という言葉は聞き慣れていても、「事後強盗」という用語は聞き慣れないという方が多いと思います。
事後強盗罪は、窃盗罪よりも非常に重い刑罰が定められている刑事犯罪です。事後強盗罪を犯してしまったならば、早めに弁護士に相談をして刑事弁護を依頼しましょう。
この記事では、事後強盗罪について、その成立要件や窃盗罪・強盗罪との違いについて解説します。
1.事後強盗罪とは?
事後強盗罪(刑法238条)は、窃盗犯が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき、強盗として論ずることとしたものです。
事後強盗罪に当たれば、5年以上の有期懲役刑に処せられます。
事後強盗罪の本質は、「窃盗の現場で生じた被害者等による犯人の追跡・追及(又はその可能性)を、窃盗犯人が暴行・脅迫を用いて回避すること」にあると考えられています。
例えば、スーパーで万引きをした窃盗犯がこれを発見した店員に追いかけられた際、逃亡のためにその店員を押して転倒させた場合には、事後強盗罪が成立します。
2.窃盗罪、強盗罪の違い
「被害者の意思に反して財物の占有を奪取する」という点では、事後強盗罪・窃盗罪・強盗罪は共通しています。
事後強盗罪は暴行・脅迫を3つの目的(財物を取り返されることを防ぐ目的、逮捕を免れる目的、罪証を隠滅する目的)の達成のために行われることが要件である一方、強盗罪は「暴行・脅迫を財物奪取の手段として要求している」という点において、事後強盗罪と強盗罪には違いがあります。
また、窃盗罪は「暴行・脅迫」が要件とされていないのが大きな違いです。
例えば、暴行・脅迫をせずに隠れて商品を万引きする行為は窃盗罪になりますが、店員を刃物で脅してレジのお金を奪ったならばこれは強盗罪です。
強盗罪(236条)の刑罰は、事後強盗罪と同様、5年以上の有期懲役となっています。
事後強盗罪及び強盗罪には罰金刑はありませんので、いずれも窃盗罪と比べ相当に重い犯罪ということになります。

[参考記事]
強盗と窃盗の違い|恐喝罪・強盗致傷罪についても解説
3.事後強盗罪の成立要件
(1) 主体
事後強盗罪の主体は窃盗犯人、すなわち、窃盗の実行に着手した者をいいます。
また、事後強盗罪は未遂犯も処罰されます(243条参照)。
例えば、犯人が財物を得られなかった場合(盗もうとしたところを発見されて何も盗らずに逃亡した場合)に店員に追いかけられたとして、逮捕を免れ又は罪証を隠滅するためにその店員に暴行を加えると、事後強盗罪は未遂犯となります。
(2) 暴行・脅迫
①暴行・脅迫の程度
事後強盗罪における暴行・脅迫は、強盗罪と同様に、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものでなければならないと解されています。
被害者の反抗を抑圧するに足る程度のものであるか否かは、具体的状況の下における暴行・脅迫を客観的に考察して決すべきとされ(最判昭24.2.8刑集3・2・75)、その判断に当たっては、暴行・脅迫の内容のほか、犯行の時刻・場所、犯人及び被害者の数・年齢・性別・体格等を総合考慮しなければならないとされています。
しかし、被害者が現実に反抗を抑圧されたことは必要ではないとされています(最判昭23.11.18刑集2・12・1614)。
被害者の反抗を抑圧するに足る程度の暴行・脅迫が加えられれば、たとえ被害者が強靭な精神力を持っており、反抗が抑圧されなかったとしても、事後強盗罪が成立するということです。
②暴行・脅迫の相手
暴行・脅迫の相手方については、窃盗の被害者に限らず、追跡してくる目撃者(大判昭8.6.5刑集12・648)や逮捕しようとする警察官(最判昭23.5.22刑集2・5・496)でも成立します。
しかし、あくまでも当該暴行・脅迫と窃盗犯人の目的との間に関連性が必要であると解されています。
したがって、当該窃盗事実と全く無関係な者に対する暴行・脅迫は、事後強盗罪を構成しないことになります。
(3) 窃盗との関連性
事後強盗罪の成立を認めるためには、窃盗犯人による暴行・脅迫は、窃盗の機会に行われる(窃盗行為と関連している)必要があります。
「窃盗の機会」とは、窃盗行為と暴行・脅迫が時間的・場所的接着性があり、暴行・脅迫時において、被害者等から容易に発見されて財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況が継続していたことをいうとされています。
ところで、窃盗の機会は以下に整理できるとされます。
①窃盗の現場から継続的に追跡されているケース
②窃盗の現場に犯人が舞い戻ったケース(いわゆる現場回帰型)
③窃盗の現場に犯人がとどまるケース
①のケースについては、窃盗の機会継続性は比較的容易に肯定されます。判例は、電車内で現行犯人として逮捕されたすりの犯人が、約5分後に到着した駅で連行されている際、逮捕した車掌に暴行を加えたときは、窃盗の機会に当たり事後強盗罪が成立するとしています(最決昭34.3.23刑集13・3・391)。
②のケースについては、窃盗犯人がいったん窃盗の現場を離れ、約1キロ離れた公園で約30分過ごし、その後再度窃盗をする目的で現場に引き返し侵入したところ家人に発見され、逮捕を免れるためにナイフで脅迫した行為は、窃盗の機会の継続中に行われたとはいえないとされます(最判平16.12.10刑集58・9・1047)。
③のケースについては、窃盗犯人が被害居宅の天井裏に潜み、犯行の約3時間後に駆け付けた警察官に暴行を加えたときは、窃盗の機会になされたと認められるとしています(最決平14.2.14刑集56・2・86)。
4.まとめ
軽い気持ちで窃盗・万引きをして見つかった場合には、気が動転してしまい、逃げるために誰かに怪我を負わせてしまうことがあるかもしれません。
これは(事後)強盗致傷罪に当てはまり、非常に重い罪になります。また、怪我を負わせない場合でも、事後強盗罪として重く処罰されます。
財産事件・暴行事件を起こしてしまったならば、実務経験が豊富な泉総合法律事務所の弁護士にお早めにご相談ください。