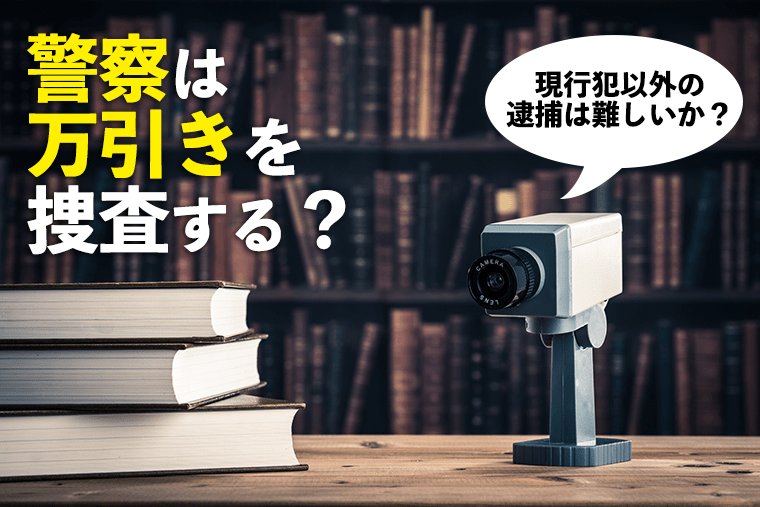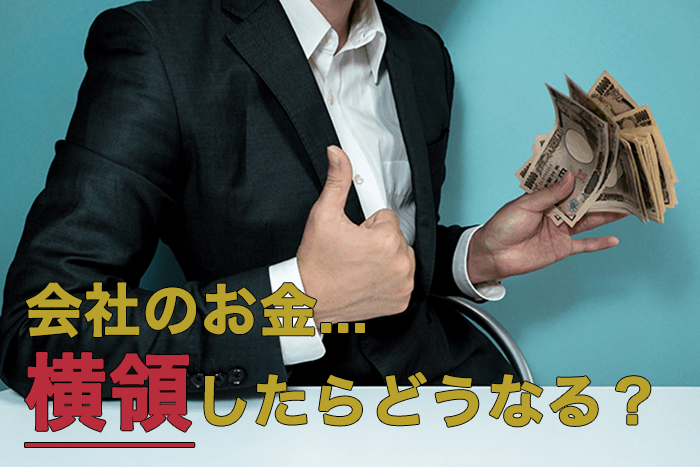万引きで強盗致傷罪に問われるケース

日本において、万引きは発生率が高い犯罪の1つです。軽い犯罪だから大丈夫、といって万引きをしてしまう方もいるかもしれません。
しかし、時に万引きは重大な結果を引き起こし、万引き犯人が厳しい刑罰を科される場合があります。
その例が、万引き犯が強盗致傷罪に問われるケースです。
この記事では、万引きで強盗致傷罪に問われるケースについて説明します。
1.万引きは「窃盗罪」
まずは、通常の万引き犯に成立する犯罪について確認しましょう。
万引き罪という犯罪は刑法に存在せず、万引き犯は窃盗罪で処罰されます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「窃取」とは、財物に対する他人の「占有」を侵害して、自己または第三者の占有下に移してしまう行為です。
「占有」とは、物に対する事実的な支配状態であり、店舗内の商品は、店舗の経営者や店長など、その店舗を管理している者が占有していると評価されます。
万引きは、お店にある商品を勝手に持ちだして自分の物にする行為ですので、店舗管理者の占有を侵害し、窃盗罪が成立します。
被害品が所有権の対象となる物であれば財産的価値の多寡は問いませんので、100円のおにぎりや水を盗った場合も、高価な宝石類を盗った場合も、等しく窃盗罪は成立します。
(もっとも、被害額は処罰内容や量刑の判断に影響します。)
2.万引きが「強盗」として扱われるケース
さて、上記の万引き犯に強盗罪が成立する、あるいは万引き犯が強盗として扱われるケースがあります。
そして、強盗犯が他人を負傷させた場合には、強盗致傷罪が成立します。
(1) 強盗罪
強盗罪は、暴行・脅迫を用いて他人の財物を盗った場合に成立します。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
窃盗罪との違いは、財物を取る手段として暴行・脅迫が用いられたか否かです。「強取」とは「強いて奪う」ことを意味するので、財物を取る手段として暴行・脅迫が用いられない限り、強盗罪が成立することはありません。
もっとも、ここでいう「暴行・脅迫」は相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることが要求されます。その程度に達しない場合、暴行・脅迫をしたからといって、必ず強盗罪が成立するわけではありません。
相手方の反抗を抑圧するに足りる程度か否かは、暴行脅迫の内容、被害者と犯人の性別、年齢、体格差、人数、凶器使用の有無、犯行時間、犯行場所などの諸事情を考慮して決します。
ケースバイケースですが、例えばナイフを用いて相手方を脅して財物を盗った場合には、一般論としては相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行として強盗罪が成立するでしょう。
他方で、相手を軽く叩いて注意を逸らし、その隙に乗じて財物を盗った場合には、犯行を抑圧する程度の暴行ではないので、強盗罪が成立するとは言えないでしょう。
(2) 事後強盗罪
財物を盗った後に暴行・脅迫を加えた場合でも、犯人が強盗として扱われることがあります。それが、事後強盗罪が成立する場合です。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
条文の「窃盗」とは、窃盗犯人、すなわち窃取行為に着手した者を指します。
事後強盗は、次の3つの場合に成立します。
①窃盗犯人が自己または第三者に移転した占有が取り返されることを防ぐ目的で暴行・脅迫をした場合
②窃盗犯人が逮捕を免れる目的で暴行・脅迫をした場合
③窃盗犯人が証拠を隠滅する目的で暴行・脅迫をした場合
(3) 強盗致傷罪
上記の強盗罪、事後強盗罪の犯人が人を負傷させた場合には、強盗致傷罪(傷害につき故意がある場合には強盗傷人罪)が成立します。
これらは、強盗行為が行われる機会に人の死傷という残虐な結果が生じやすいことから、生命身体の安全を保護することに重きをおいて規定された犯罪です。
この場合の強盗行為それ自体は、既遂か未遂かを問いませんので、強盗未遂犯(占有移転を完了せず、財物奪取に失敗した場合)が他人を負傷させた場合でも、強盗致傷罪が成立します。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
3.万引きと強盗致傷に関するよくある質問
-
万引きと強盗致傷に関するよくある質問
万引き犯は窃盗罪で処罰されます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。被害品の財産的価値の多寡は問われませんので、100円のおにぎりや水を盗った場合も、高価な宝石類を盗った場合も、等しく窃盗罪は成立します。
なお、刑法上の再犯に該当する者は、刑期の上限が2倍まで長くなります。
よって、窃盗罪の再犯なら最高で懲役20年の刑罰を科すことができます(犯行の内容や、示談の状況、被疑者の反省具合などにより、刑期が少なくて済む場合、罰金刑に留まる場合もあり得ます)。 -
万引き(窃盗)が強盗犯になるケースとは?
万引きで強盗罪が成立するケース
例えば、万引きをしようと商品を物色しているときに店員に声をかけられたので、店員に暴行を加えて商品を盗って逃げた場合には、強盗罪が成立する可能性があるでしょう。
この場合、物色段階では窃盗行為の着手とは評価されませんが、その後、店員に暴行を加えて商品を盗っているので強盗罪となります。
なお、強盗罪は暴行・脅迫が先行し、そして財物を盗る必要があるので、商品を盗った後に暴行・脅迫を加えた場合には「事後強盗罪」の話となります。
万引きで事後強盗罪が成立するケース
商品を盗った後に店員に呼び止められ盗った物を出すよう言われた際に、逃亡しよう考えて暴行を加えた場合が、事後強盗罪が成立する典型例です。
店員や駆け付けた第三者、警察官による現行犯逮捕を免れようと考えて暴行を加えた場合も同様に、事後強盗罪が成立します。
そして、上記の強盗罪、事後強盗罪の犯人が他人を負傷させた場合には、怪我をさせるつもりがなくとも強盗致傷罪(傷害につき故意がある場合には強盗傷人罪)が成立します。
4.まとめ
窃盗罪は最大で法定刑が懲役10年まであるので、皆さんがイメージするほど軽い犯罪ではありません。
また、強盗罪、強盗致傷罪まで成立してしまうと、両罪の法定刑を見れば分かるように、各段に重い刑罰が科される可能性があります。
被害者がいる犯罪では示談が重要です。示談が成立すれば、検察官が起訴を控えたり、裁判になった場合に量刑判断で有利に働いたりする可能性があります。
窃盗に比べれば確率は低くなりますが、強盗致傷罪のような重い犯罪でも、不起訴や執行猶予付き判決を得られる可能性は0ではありません。
そして、示談の成立が、そのための重要な要素であることに変わりはありません。
万引きをしてしまった方は、なるべく早く、刑事弁護の経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。