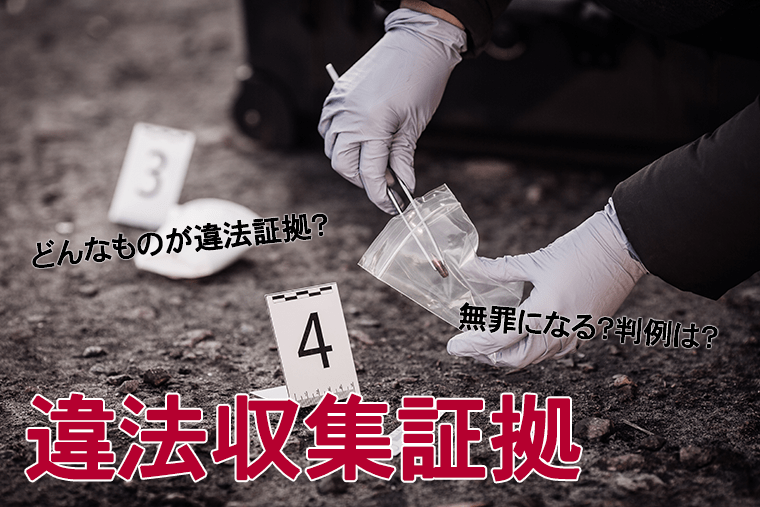証拠隠滅とは|罪になるか

自分が罪を犯してしまった場合、また身近な人が罪を犯してしまった場合、犯罪の証拠となるような物を隠したり壊したりしたいと考えるかもしれません。
しかし、証拠の隠滅等をすると、その行為自体に犯罪が成立する可能性があります。
この記事では、証拠隠滅が罪になる場合について成立します。
1.証拠隠滅をした場合に成立する犯罪
(1) 証拠隠滅等罪
証拠を隠滅等した場合には、証拠隠滅等罪が成立します。
刑法104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
証拠隠滅等罪は、①他人の刑事事件に関する証拠を②隠滅・偽造・変造、もしくは偽造・変造した証拠を使用した場合に成立します。
①他人の刑事事件に関する証拠
証拠には、犯罪の認定に関するものだけでなく犯人の情状に関するものも含まれます。
証拠というと物的証拠をイメージしますが、被害者や第三者という「証人」の供述は犯罪の認定資料となるので、証人それ自体も「人証」と呼ばれる証拠なのです(ただし、後述しますが、「供述」それ自体は証拠隠滅等罪の対象ではありません)。
したがって、証人を監禁などした場合も証拠隠滅等罪は成立します。
なお、対象となる証拠は「他人の」刑事事件に関する証拠に限られ、「自己の」刑事事件に関する証拠は含まれません。
これは、犯罪を犯した者が自分の犯罪の証拠隠滅をするのは心情的にやむをえず、証拠隠滅をしないことを期待することができないからです。
したがって、犯罪を犯した者が、その自分の犯罪の証拠となるもの(奪った被害品、犯行に使った凶器等)を隠滅等しても、証拠隠滅等罪は成立しません。
もっとも、他人を教唆して(そそのかして)、自己の刑事事件に関する証拠を隠滅等させた場合には、証拠を実際に隠滅等した者だけでなく、そそのかした者にも証拠隠滅等教唆罪が成立する可能性があります。
たとえ隠滅等の対象が自己の刑事事件に関する証拠であっても、他人を犯罪に巻き込む行為は、もはや心情的にやむを得ない行為とは言えないからです。
また、証拠は刑事事件に関するものに限られますから、民事事件の証拠となるものを隠滅等しても証拠隠滅等罪は成立しません。
②隠滅・偽造・変造
隠滅とは、証拠が明らかになるのを妨害したり、その証拠としての価値を減少させたりする行為をいいます。
証拠を隠したり、破壊したりするのが典型的な隠滅行為です。
偽造とは、新たに証拠を作成することをいいます。内容虚偽の被害届・上申書を作成した場合などです。
なお、参考人が、その取り調べにおいて供述をした場合、その供述をもとに供述調書が作成されます。
そこで、取調べで虚偽の供述をして参考人の供述調書が作成された場合にも証拠偽造罪が成立するか問題になりますが、この場合には、原則として証拠偽造罪は成立しないと考えられています(※最高裁平成28年3月31日決定)。
虚偽の供述は偽証罪(刑法169条)で処罰をするのが刑法の態度であり、単なる参考人に対し、刑罰をもって真実の供述義務を課すことは処罰範囲を拡大し過ぎる懸念があるからです。
変造とは、存在する証拠に手を加えることをいいます。
使用とは、偽造や変造した証拠を裁判所や捜査機関に提出することをいいます。
証拠隠滅等罪をした者が犯人の親族である場合には、その刑が免除されることがあります。これも親族関係から、心情的に無理からぬ場合があることを考慮したものです。もっとも、これは義務的なものではなく、裁判官の裁量により決定されます。
また、刑が免除されても有罪判決であることに変わりありませんので、前科がつきます。
刑法105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
証拠隠滅等罪の罰則は、3年以下の懲役刑、又は、30万円以下の罰金刑です。同罪の時効は3年となっています。
(2) 証拠隠滅に関するその他の犯罪
証拠が他人の物である場合、これを隠滅等すると器物損壊罪(刑法261条)が成立します。
また、証人を殺したり、監禁等したりした場合には、殺人罪(刑法199条)、逮捕・監禁罪(刑法220条)が成立します。
証拠隠滅等罪以外に犯罪が成立する場合には、観念的競合(刑法54条1項)となり、法定刑の上限・下限とも、もっとも重い方の刑罰で処断されることになります。
逮捕・監禁罪(3か月以上7年以下の懲役)や殺人罪(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)は証拠隠滅等罪よりも法定刑が上限・下限とも重いので、上限・下限とも、そちらの刑罰で処断されることになります。
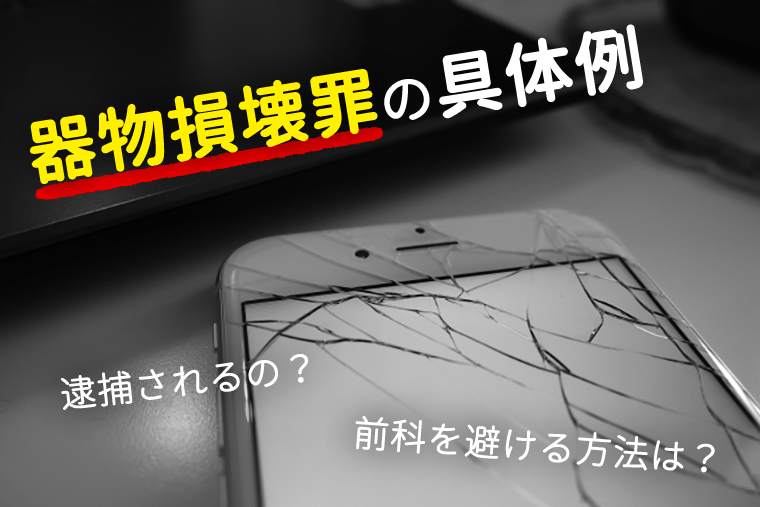
[参考記事]
器物損壊罪は親告罪!更なるトラブル回避・示談交渉は弁護士へ
2.証拠隠滅等罪を犯してしまったら
(1) 逮捕後の一般的な流れ
身近な人のためとはいえ、証拠隠滅等をする行為は犯罪です。したがって、これが発覚した場合には逮捕や勾留される可能性があります。
逮捕・勾留は最大で23日間続きます。その後起訴された場合には、更に身体拘束が継続する可能性があります。また、起訴された場合には有罪判決となる可能性が高く、有罪判決が出されたら前科がついてしまいます。
身体拘束からの早期釈放や不起訴処分を獲得するためには、弁護士の弁護活動が重要です。
弁護士は、すぐに身体拘束されている依頼者のもとに接見しに行き、取り調べに対するアドバイスをしたり、捜査機関に意見書を提出したりするなどします。
(2) 証拠隠滅等事件の弁護のポイント
①動機と人間関係
前述のとおり、刑法が自己の刑事事件の証拠を対象外とし、また親族による証拠隠滅等を刑の免除事由としているのは、いずれも心情的に無理からぬものがあり、強く非難できないからです。
この事情は、犯人自身や親族に限ったことではありません。証拠隠滅等は、多くの場合、刑事事件の犯人(本犯者)との親密な人間関係から、本犯者を助けたいという動機で行われます。
たとえ親族でなくとも、本犯者のため違法な行為に手を染めたことも、心情的に無理がない場合はいくらでもあります。
弁護士は行為の動機と、本犯者との人間関係から、隠滅等の行為も心情的に無理からぬ、強く非難できないものだという点に焦点をあてて、検察官に不起訴処分を求めていきます。
②隠滅された証拠の重要性
証拠隠滅等罪は国家の司法作用の適正を保護するものです。
もちろん、どのような証拠であれ、それを隠滅することは国家司法作用を害する危険があるとは言えます。
しかし現実的には、ひとくちに犯罪の証拠といっても、例えば交通機関のチケットのようにアリバイの成否に関するものや、DNA鑑定資料となる毛髪や煙草の吸い殻のように犯人との同一性にかかわる重要な証拠から、単なる反省文のような情状にかかわる証拠のように、その軽重は一律ではありません。
そこで弁護士は、本犯者の事件における当該証拠の位置づけ、重要性・不可欠性を検討し、その隠滅等行為が、必ずしも本犯者の刑事処罰に支障を生じさせる危険があったものではなく、処罰の必要に乏しいことを訴えて不起訴を求めます。
証拠隠滅等罪で逮捕・勾留された方は、早急に弁護士までご相談ください。