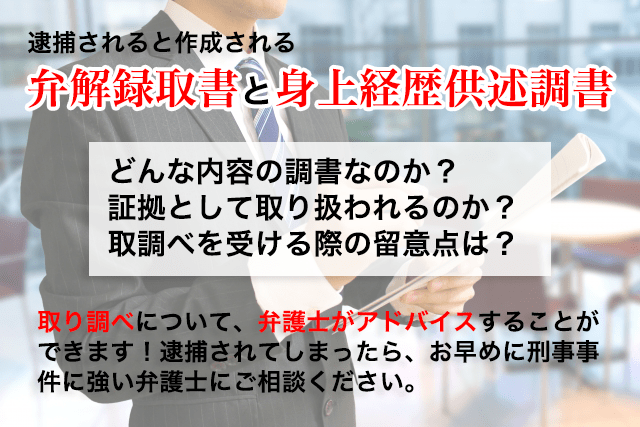民事裁判と刑事裁判の大きな違い

民事裁判と刑事裁判には、どのような違いがあるのでしょうか。
私たちが社会的活動を送る過程では、様々なトラブルに遭遇します。
万が一、裁判に巻き込まれた場合、それぞれの裁判について、その内容や違い・流れを知っておくのは重要なことです。
以下においては、民事裁判と刑事裁判について、取り扱う事件内容、当事者、裁判の進め方の違いなどについて、わかりやすく説明していきます。
1.取り扱う事件内容の違い
民事裁判では取り扱われる典型的な問題は、①私人と私人の間における金銭をめぐる問題、②私人と私人の身分関係をめぐる問題です。
例えば、借金の返還請求、交通事故の損害賠償請求、不動産の明渡請求などは、①の問題です。
この場合、私人には、個人だけでなく、株式会社などの「法人」等も含まれますし、国や地方自治体が私人と同様の立場で行った取引行為(例えば、市役所が業者から購入した備品代を支払わないといった場合)をめぐる問題も含まれます。
また、例えば、不要解雇を受けた労働者が雇用契約の有効性を確認する訴訟は、それ自体は金銭を請求する問題ではありませんが、究極的には解雇後の賃金など金銭問題の前提となる契約の問題ですから、①に含めて考えることができます。
他方、離婚訴訟や、父親に対する認知請求訴訟などが②の問題です。
これらの場合、私人と私人の立場は、法的には対等な関係です。上に述べた国や地方公共団体が当事者となっているケースでも、私人と同様の立場で経済取引を行っている以上、私人と対等な立場で民事裁判に服することになります。
このように、民事裁判で取り扱う問題は、法的に対等な私人と私人の権利義務に関する争いですから、国家機関としての裁判所は本来は無関係な問題です。
しかし、私人間の争いを放置すれば、紛争が激化し、私的な闘争にも発展しかねませんし、スムーズにトラブルを解決する制度がなければ社会は成り立ちません。
そこで、本来は無関係な私人間のトラブルに、裁判所という国家機関が介入し、紛争を解決してくれるというのが民事裁判制度なのです。
他方、刑事裁判が取り扱うのは、犯罪者に対して刑罰を与えるか否かという問題です。
犯罪者とは、国や地方自治体が定めた法律・条例の刑罰法規に違反した者を指し、法人も対象となる場合があります。例えば、窃盗、殺人、痴漢、各種薬物犯罪、過失や危険運転による交通事故、企業による法人税の脱税など様々です。
民事裁判で扱われるのが、対等な「私人と私人の争い」であったのに対し、犯罪者に刑罰を与えるのは「国家」ですから、刑事裁判は「国家対私人の争い」という大きな違いがあります。
2.当事者の違い
民事裁判は、私人と私人の争いなので、当事者の一方が「訴える方」となり、他方が「訴えられる方」となります。前者を「原告」、後者を「被告」と呼びます。
なお、民事裁判は弁護士を依頼せずに当事者本人だけで行うことも許されていますが、民事裁判を進めるには法律の専門知識が不可欠ですから、多くの場合、弁護士を訴訟代理人として選任することになります。
国家対私人の争いである刑事裁判では、国家が「訴える方(原告)」となり私人が「訴えられる方(被告)」となります。
具体的に国家の代表者として原告の役割を担うのが検察官であり、検察官が私人を訴える行為が起訴処分です。また、刑事裁判では被告を「被告人」と呼ぶのが正式名称です。
なお、刑事裁判においては、被告人は弁護人を選任する権利があります。経済的事情などで、自費で弁護人を選任できない場合などには、裁判所によって国選弁護人が選任されます。また、法定刑が一定以上の重い犯罪については弁護人がいなければ裁判を開くことはできません(必要的弁護事件)。

[参考記事]
刑事裁判で「弁護士なし」は可能?
3.裁判の進め方(流れ)の違い
民事裁判と刑事裁判は、裁判の流れ自体にも違いがあります。
(1) 民事裁判の場合
対等な私人と私人の争いである民事裁判では、訴えた原告と訴えられた被告が、交互に攻撃と防御を繰り返して訴訟を進めます。
スポーツで言えば、テニスや卓球に似ています。もちろん、審判役は裁判官です。
㈠ まず原告(訴訟代理人弁護士を含む)は、請求の趣旨及び請求の原因が記載された訴状と証拠となる書類を裁判所に提出します。
「請求の趣旨」とは、例えば「金1000万円を支払え」というように、原告が求める訴えの結論部分のことです。「請求の原因」とは、例えば、「原告は被告に、金1000万円を貸した」というように、請求の理由となる事実関係のことです。原告が被告にお金を貸した事実が存在することを立証する責任は原告自身にあります。
㈡ 訴状を受け取った被告(訴訟代理人弁護士を含む)は、訴状に記載されている原告の主張に対する被告の言い分を、答弁書に記載して、証拠となる書類と共に、裁判所に提出します。
例えば「借りた金1000万円は原告に返した」という反論が考えられます。借金を返済した事実が存在することを立証する責任は被告にあります。
このように民事裁判では、事実を立証する責任は、その内容に応じて、原告と被告に振り分けられています。
㈢ こうしてお互いの言い分を事前に書面で裁判所に提出しておき、第一回期日には、原・被告双方が法廷に出頭します。
法廷では、裁判官から当事者に対して、主張を明確にしてほしい点を指示したり、疑問点を確認されたり、証拠の開示を求めたりなどのやりとりが行われます。
当事者間でも、裁判官を介しながら、同様に、互いの主張内容に関して釈明を求めるなどのやりとりを行います。
答弁書に対して、原告に反論があれば、第2回期日までに原告準備書面として提出します。
第2回期日には、再び、第1回期日と同様のやりとりが行われ、被告に再反論があれば、第3回期日までに被告準備書面として提出します。このやりとりは、お互いの主張が尽きるまで繰り返されます。
こうして交互に主張と反論を行うので、テニスや卓球に似ているわけです。法廷でこのやりとりを繰り返すことを「口頭弁論」と呼びます。
このボールの打ち合いは、「言い分が違う点が何処なのか」を明確にしてゆくための作業と言えます。言い分が一致している事実については問題がないので、言い分が異なる点、すなわち争点をはっきりさせ、その部分についてだけ証拠調べを行えば決着がつくからです。
㈣ こうして、当事者間の争点が明らかになれば、その争点について判断するために、裁判所は書証の取調べ、証人尋問、当事者尋問等の証拠調べの手続を行います。
㈤ 裁判所が証拠調べを行った後、当事者の主張・立証が尽き、原告の請求が認められる、又は認められないとの心証を得たときは、口頭弁論を終結して判決を下します。
(2) 刑事裁判の場合
国家対私人の争いである刑事裁判では、刑罰権を持つ国家が一方的に私人を訴えることになり、その役割を担うのが検察官です。
しかも、刑事裁判では、被告人が立証に失敗した故に刑罰を受けるという事態を生じさせてはならず、「無罪推定の原則」が働くので、被告人が犯罪を犯したことを立証する責任は、すべて検察官にあります。
そこで、訴訟の進行としても、まず検察官が被告人の有罪を主張・立証し、それが終了した後、被告人(弁護側)の反論が行われるという順番になります。
したがって、民事裁判がテニスや卓球に似ているのに対し、刑事裁判は野球、それも一回表と一回裏しかない野球に似ています。もちろん、一回表は検察官の攻撃です。刑事裁判においても、審判役は裁判官です。
㈠ まず検察官が被疑者を被告人として起訴すると刑事裁判が開始されます。起訴は、公訴事実を記載した「起訴状」を裁判所に提出することで行われます。「公訴事実」とは、検察官が主張する、被告人が行った犯罪事実の記載です。刑事裁判は、この公訴事実の有無をめぐる攻防です。
㈡ 第1回公判期日の最初に行われるのが冒頭手続です。冒頭手続では、間違いなく被告人本人かどうかを確認する人定質問、起訴状の朗読、黙秘権等の権利告知、被告人及び弁護人の被告事件についての陳述がなされます。被告事件についての陳述とは、公訴事実を認めるか否かを主な内容とする答弁です。
㈢ 冒頭手続の次に、証拠調手続に入ります。
証拠調べ手続では、まず、検察官が冒頭陳述を行います。冒頭陳述とは、検察官が証拠により証明しようとする事実を明らかにするもので、公訴事実よりも具体的で詳細な内容を主張することになります。
また、事案によっては、より争点を明確にするために、被告人側も、冒頭陳述を行う場合があります(例えば、裁判員裁判では必要的な手続です)。
冒頭陳述後には、まず、検察官が書証、証拠物、証人などによって起訴事実を証明するための立証を行い、次いで、被告人側が証人などによって反証を行ったり、情状証人を含む情状立証を行ったりした後、最後に被告人質問を行うのが通例となっています。
㈣ 証拠調べが終わった後、検察官は、事件に対する事実面・法律面の意見を述べます。この中には、いわゆる刑の重さに関する意見「求刑」が含まれます。
それに対して弁護人は、被告人の立場から見た事件に対する事実面、法律面の意見を述べます。最後に、被告人が事件についての意見を述べます。
㈤ こうして結審した後、指定された判決期日に、裁判所が判決の言渡しをします。起訴事実が立証され、刑罰法令に触れるときは有罪判決が言い渡され、起訴事実が罪とならないとき又は犯罪の証明がないときは無罪判決が言い渡されます。

[参考記事]
刑事裁判の流れと仕組み。期間・費用まで徹底解説!
4.その他の違い
(1) 和解の有無
民事裁判の役割は私人間の「紛争の解決」です。
しかも、私人の権利義務は、多くの場合、権利義務を有する私人自身の意思で譲歩・放棄が自由ですから、真実はどうであろうと、当事者が納得して紛争が収まれば目的は達したことになります。
したがって、民事裁判が開始されても、お互いの主張を闘わせている段階、証拠調べが終わった段階、事案によっては結審後の段階であっても、随時、裁判官から和解の提案がなされ、実際、ほとんどの事件は裁判官を仲介役とした和解で決着がつきます。これを裁判上の和解と呼びます。
一方の刑事裁判では、国家の刑罰権を実現することが目的ですから、検察官と被告人(弁護人を含みます)との間で、判決に代わる和解の制度はありません。
もっとも、検察官は有罪判決が見込める事案であっても、諸般の事情を考慮して、不起訴処分とする権限があります。
例えば、弁護士を介して被害者との示談を成立させれば、検察官により不起訴が相当と判断され、刑事裁判に至らないで事件を終結させることができます。
民事事件では、弁護士を介して、提訴前に当事者が和解し、無用な民事裁判を回避するケースが多いですが、刑事事件における示談による不起訴処分も同様の役割があると言えます。
また、贈収賄、詐欺、恐喝、横領、薬物取引等の特定の犯罪に係る事件については、平成30年6月に、協議・合意制度(司法取引)が導入されました。
この制度は、組織的な犯罪等の上位者・背後者の関与を含む全容の解明を容易にするため、検察官が、これら特定の犯罪について、弁護人の同意を条件に、被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人が他人の犯罪事実を明らかにするための供述等をし、検察官が不起訴や特定の求刑等をする旨の合意ができる制度です。
(2) 立証の度合い
民事裁判でも、裁判官が事実を認定するためには、その事実が存在することにつき「確信」に達していなくてはならないと説かれています。
しかし、これには異論もあり、実際の民事裁判では、刑事裁判に比べて、当事者がクリアすべき立証の基準は低く、「証拠の優越」、すなわちある事実についての証拠の重み・証明力が「他方よりも上回っている」程度でも足りるケースが珍しくありません。
しかし、刑事裁判では、前述のとおり、被告人の無罪が推定されるので、検察官は証拠に基づいて、被告人が犯人であると「合理的な疑い」を差し挟む余地がないところまで(すなわち、被告人が犯人であることは絶対に間違いないといえるところまで)立証しなければならず、この点は異論がありません。
5.おわりに
民事裁判と刑事裁判の手続の違いについてしっかりと理解をしておくことで、万が一裁判に巻き込まれたケースで適切な対応をとることができます。
特に、刑事事件を取り扱う刑事裁判では、起訴された被告人が身体を拘束されている場合もあり、スピーディに審理される必要がありますから、裁判手続についての理解が事件の早期解決につながるかも知れません。
もし、刑事事件を犯してしまった、家族が刑事事件で逮捕されてしまったという場合は、法律のプロである弁護士に相談して刑事弁護をしてもらうのが一番です。
どうぞ泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。