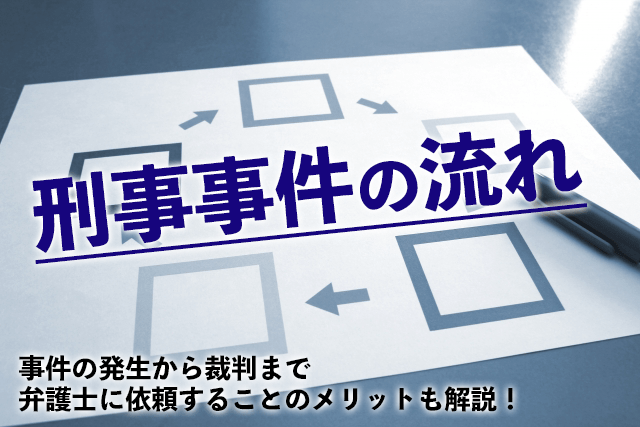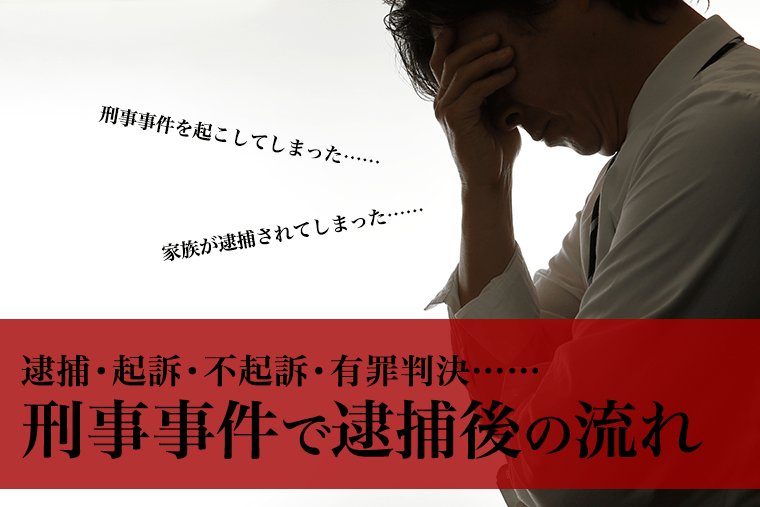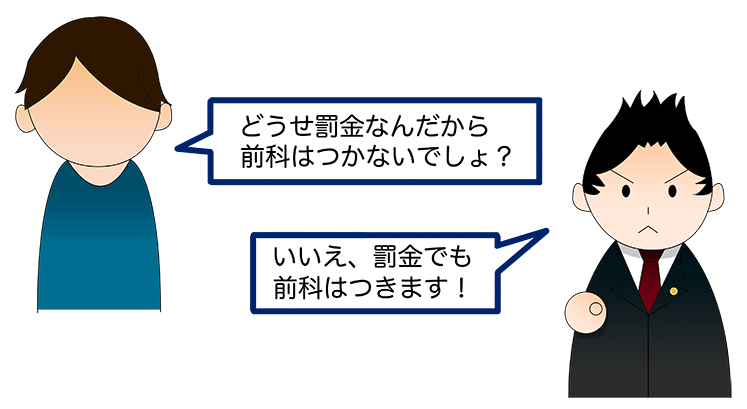「処分保留で釈放」とは?起訴・再逮捕の可能性

勾留満期に釈放された時、警察官や検察官から「処分は保留だ」などと言われることがあります。
被疑者からすれば、「釈放されたのだから疑いは晴れた」「許された」という思いを持つかもしれません。
この認識は正しいのでしょうか?「処分を保留」とは具体的にどういう事なのでしょうか?
この記事では「処分保留で釈放」の意味や、その後どうなる可能性があるのか、何か対策を取ることができるのか等について解説します。
1.処分保留の「処分」とは?
犯罪を行ったと疑われる者を刑事裁判にかけることを「起訴」と呼びます。
起訴する権限を有しているのは検察官だけです。ある犯罪の捜査が開始され、証拠を収集した後に、検察官が被疑者を起訴するか否を決めます。
これを「終局処分」と呼び、「起訴処分」と「不起訴処分」に分かれます。
処分保留の「処分」とは、この「起訴処分」と「不起訴処分」のことであり、「処分保留」とは、検察官が起訴するか否かの判断を棚上げすることを指します。
被疑者を逮捕・勾留した場合には、検察官は、勾留請求の日から10日間(勾留延長が認められた場合には通常最大20日間)のうちに、①起訴処分とするか、それとも、②身柄を解放するかのどちらかを選択しなくてはなりません(刑訴法208条)。
勾留期間内に起訴・不起訴の処分をすることが義務づけられているわけではないのです。
そして、検察官が②起訴処分とせずに身柄を解放する場合、(ア)不起訴処分としたうえで釈放すること、又は、(イ)終局処分を決めないまま釈放することのどちらかを選択することになります。「処分保留で釈放」とは、(イ)のケースを指します。
よって、検察官が起訴・不起訴の判断を先送りにしている場合ですから、釈放後に起訴される可能性はおおいにあります。
処分保留で釈放された後、すなわち身柄拘束がなくなって以降は、公訴時効が完成しない限り、いつまでに起訴しなくてはならないという期限はありません。
したがって、釈放された1週間後に起訴される場合もあれば、数年後に起訴される場合もあり、事案によるとしか言えません。これは不起訴処分の決定についても同じです。
被疑者が起訴処分を受ければ、裁判所から起訴状の謄本が送達されますから、起訴されたことを知ることができます(刑訴法271条1項)。
他方、不起訴処分を受けた場合は、起訴状はありませんが、被疑者が検察官に請求した場合には、検察官は速やかに不起訴処分をした旨を告げなくてはならないとされています(刑訴法259条)。
2.処分を保留する理由
上の説明から明らかなとおり、検察官が処分を保留する理由は、勾留満期の段階で、「起訴処分」とも「不起訴処分」とも判断する決め手がないからです。
(1) 起訴できない理由
実務では、起訴処分は、被疑事実につき、的確な証拠に基づき有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って行います。
勾留満期時点でこの見込みが得られていなければ、起訴処分とはできません。
(2) 不起訴とできない理由
他方、勾留満期の段階で、有罪判決の見込みがない場合でも、ただちに不起訴処分を下すことになるわけではありません。
不起訴処分となる理由は様々であり、勾留満期時点で不起訴処分の理由が明確でないなら、処分を下すことはできないからです。
例えば、不起訴処分の理由のひとつである「嫌疑なし」は、被疑者が犯罪の行為者でないことが明白なときや犯罪の成否を認定するべき証拠のないことが明白な場合です。
勾留満期の段階において、人違いや犯罪の証拠がどこにも存在しないことがハッキリしていないなら、直ちに嫌疑なしと断定することはできず、処分保留として捜査を続けることになります。
また、同じく不起訴処分の理由のひとつである「証拠不十分」は、犯罪の成立を認定するべき証拠が足りない場合です。
犯罪を推認させる証拠はあるものの、勾留満期の段階において裁判官をして確信に至らせるまでの証拠は揃っておらず、既に捜査は尽くしたので、これ以上の捜査をしても追加の証拠が出てくる見込みもないという場合です。
そこで逆に、まだ捜査が尽くされたとは言えない状況であり、捜査を継続すれば追加の証拠を得られる可能性が高い場合には、直ちに「証拠不十分」として不起訴とすることはできず、処分保留としてさらに証拠を探すことになります。
また、勾留満期の段階で有罪判決の見込みがある場合でも、必ず起訴処分となるわけではありません。検察官は、示談の成立など、諸般の事情を考慮して、訴追を必要としないと判断した場合には、不起訴処分とすることもできるからです。これを「起訴猶予」と呼びます(248条)。
そこで例えば、弁護人による示談交渉が功を奏して、勾留満期には間に合わないものの近日中に示談が成立する蓋然性が高いという場合、勾留満期の段階では処分保留としておき、弁護人からの示談成立の報告を待って起訴猶予による不起訴処分とするケースもあります。
3.再逮捕の可能性はあるのか?
(1) 再逮捕・再勾留は原則禁止
身体拘束の長期化による人権侵害を防止するため、逮捕と勾留には、それぞれ期間制限が設けられています。
もしも、同一の犯罪事実について、複数回の逮捕・勾留を認めると、期間を制限した意味がなくなります。
そこで、同一の犯罪事実については、逮捕・勾留は1回しか許されないことが原則とされています。これを「逮捕勾留の一回性原則」と呼びます。
(2) 再逮捕・再勾留禁止の例外
しかし、この原則は例外を一切許さないものではありません。
刑事訴訟法には再逮捕を予定した明文規定(刑訴法199条3項、刑事訴訟規則142条1項8号)があります。
他方、再勾留には明文の規定はないものの、勾留は逮捕から引き続いて身柄を拘束する手続ですから、当然に再勾留も予定していると理解されています。
ただし、再逮捕・再勾留は、あくまでも原則禁止ですから、無制限に例外が認められるものではありません。
①不当な蒸し返しでない場合
新証拠の発見や、新たに逃亡や証拠隠滅のおそれが生じるなどの新事情が生じ、逮捕の不当な蒸し返しではない場合であって、はじめて再逮捕・再勾留が許されます(東京高裁昭和48年10月16日判決・刑事裁判月報5巻10号1378頁)。
②同時処理が不可能な場合
逮捕・勾留が1回しか許されない「同一の犯罪事実」とは、「実体法上の一罪」に含まれる事実を指します。実体法とは、例えば刑法のように「何が犯罪に該当する行為か」を定めた法律のことで、「実体法上の一罪」とは、その刑罰法が一罪として扱っている範囲を意味します。
例えば、空き巣狙いは、住居侵入罪と窃盗罪に該当しますが、刑法では、これを牽連犯として一罪と扱います(刑法54条1項)。これを科刑上一罪と呼び、実体法上の一罪です。
したがって、空き巣狙いの被疑事実を住居侵入罪と窃盗罪の2つ分け、住居侵入罪で逮捕した後に窃盗罪で再逮捕することは認められません。
刑事手続は、犯罪者に対する国家の刑罰権を実現するための手続であり、一罪、すなわち1個の刑罰権に対しては、1回の刑事手続で対応するべきです。
換言すれば、「実体法上の一罪」の範囲にある事実については、検察官は同時に処理する義務があることになります。これを「同時処理の義務」と呼びます。
ただ、たとえ実体法上の一罪でも、現実に同時処理が不可能であった場合には再逮捕再勾留が許されます。
例えば、常習賭博罪(刑法186条1項)は賭博行為を反復する習癖のある者が行う賭博行為を重く処罰するものですが、習癖として行われた複数回の賭博行為は個々の行為が一罪となるのではなく、まとめて一罪と扱われます。これを包括一罪と呼び、実体法上の一罪のひとつです。
ただ、常習の被疑者が賭博罪で逮捕・勾留され、処分保留で釈放された後に、また賭博行為を行って逮捕されたというケースでは、勾留満期の段階で検察官が同時に処理することは不可能でした。
したがって、この場合は、例外として、後の賭博行為での逮捕・勾留は許されます。
4.処分保留で釈放後の捜査への対応
処分保留は捜査の継続を意味しますから、釈放後も、必要に応じて警察・検察から呼び出される可能性があります。
呼び出しは、任意の出頭を求めるものであり、これに応じる義務はありません。同一事実で再逮捕はできないことが原則ですから、出頭要請に応じなくとも再逮捕されることはありません。
ただ、無視されれば、当然に捜査機関の担当者は怒って捜査に注力する可能性があります。したがって、出頭要請に応じるか否かは慎重な判断が必要です。
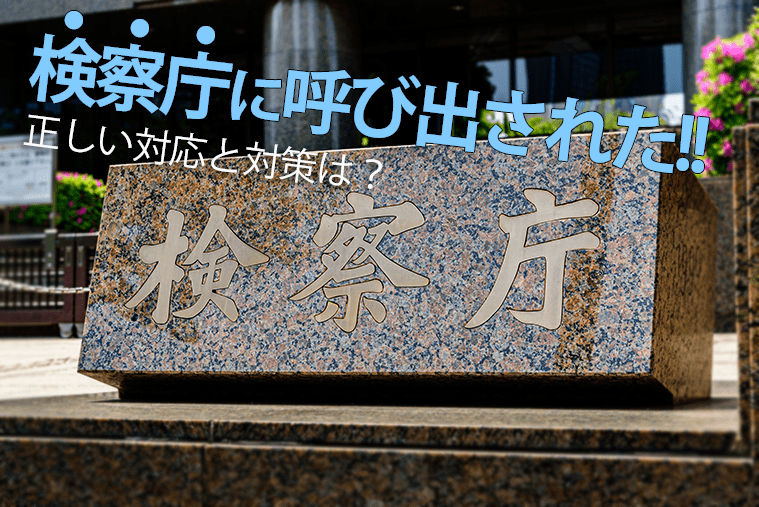
[参考記事]
検察庁に呼び出された場合の正しい対応と対策
また、処分保留で釈放されても、起訴の危険性がなくなったわけではありません。最終的な不起訴を勝ちとるために十分な対策を講じるべきです。
具体的には、犯罪が事実であり、被害者との示談が成立していない場合は、早急に示談をまとめることに全力を傾けるべきです。
否認事件や、犯罪が事実であっても事実の一部に争いがある場合は、被疑者側に有利な証拠の収集・保全が重要です。
仮に再逮捕・再勾留されても、弁護士は検察官に勾留請求や勾留延長請求をさせないよう、また裁判官に勾留決定や勾留延長決定をさせないよう説得する活動を行い、決定に対しては準抗告という不服申立手段で争います。
仮に、この段階での活動が功を奏さず、再逮捕・再勾留からの身柄開放が実現しなくても、このような活動を十分にしておくことは重要です。
起訴されたとしても、公判において、再逮捕・再勾留が違法であり、その期間中に得られた供述調書などの証拠は、裁判の証拠として利用することはできないと主張して闘うことが可能となるからです。
5.刑事弁護は泉総合法律事務所へ
処分保留で釈放された場合、安心せず速やかに対処する必要があります。刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。