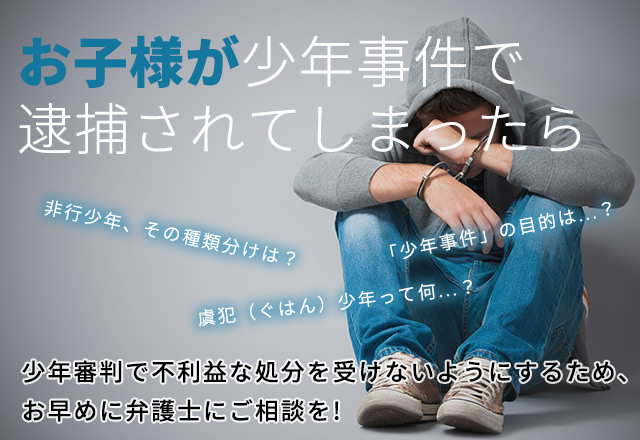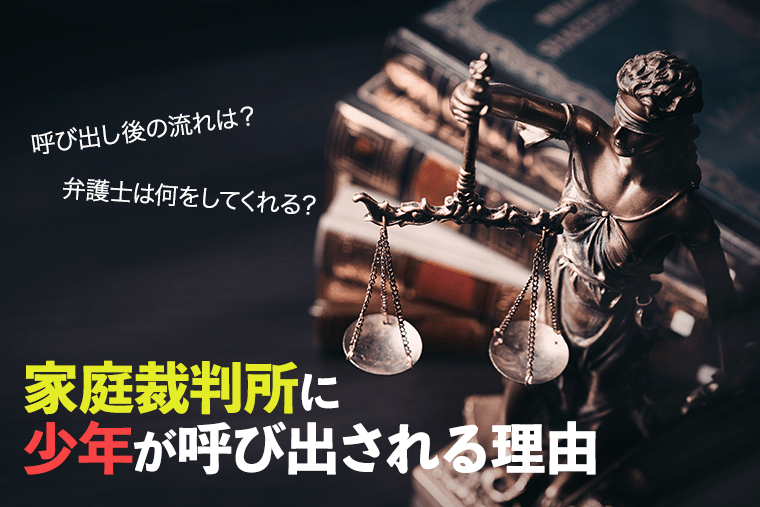刑法と少年法の違いとは?目的、定義、刑罰
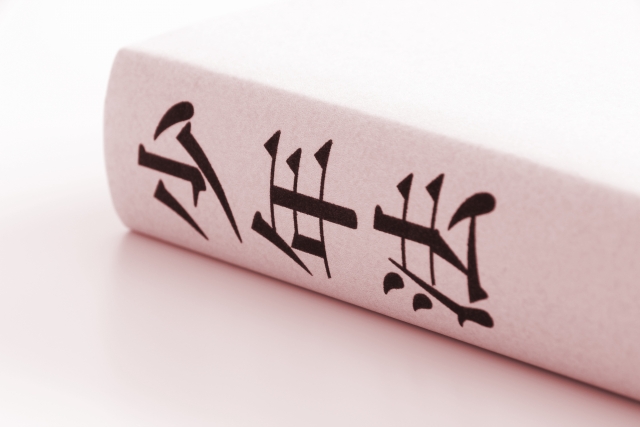
犯罪は、成人が犯す場合があれば、20歳未満の少年が犯す場合もあります。
「少年法」の存在があることからご存知かと思いますが、人が犯罪を犯した場合、成人と少年では適用される法律や処罰に違いが出ます。
この記事では、20歳未満の少年を持つ親御様で、お子様が実際に刑事犯罪を起こしてしまい、「親としてどうすれば良いか分からない」「どのような刑罰を受けるのか、子どもの将来がどうなるのか等が不安」という方に向けて、刑法と少年法とを対比しながら、親として正しい対応方法も解説していきます。
1.刑法と少年法の違い
(1) 施行の目的
刑法は、法律としては古く、目的規定はありません。
しかし、適正手続を保障した憲法31条に則って、「罪刑法定主義の実体法的実現」が目的であると理解することができます。罪刑法定主義とは、とある行為を犯罪として処罰するためには、法律によってその行為の内容や科される刑罰を予め規定しておかなければならないという原則です。
一方の少年法は、1条において、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする」と規定しています。
少年の健全な育成という文言から、少年法は、少年が行った過去の犯罪ないし非行に対する応報として少年を処罰するのではなく、その少年が将来二度と犯罪ないし非行を行わないように、その少年を改善教育することが目的であると理解することができます。
上記の違いから規定対象にも違いが出ており、刑法は犯罪と刑罰を規定していますが、少年法は非行(3条1項)と保護処分(24条1項)について規定しています。
(2) 規定対象者の違い(適用年齢)
刑法は、満14歳以上の者を対象とし(同法41条)、14歳未満の者の行為を不可罰としています。
少年法は、原則として20歳未満の者を対象とします(同法2条1項)。しかし、例外的に20歳以上の者に対しても適用される場合があります。
他方、14歳に満たない触法少年及び虞犯少年については、いわゆる児童福祉機関等による先議制度が取られていますから、これらの機関からの送致がなければ家庭裁判所の審判の対象になりません。
なお、令和2年には少年法が改正され、少年のうち18歳以上の者は特定少年とされ、その物が犯罪を犯した場合には、以前より厳しい処分が科される可能性が高くなりました。
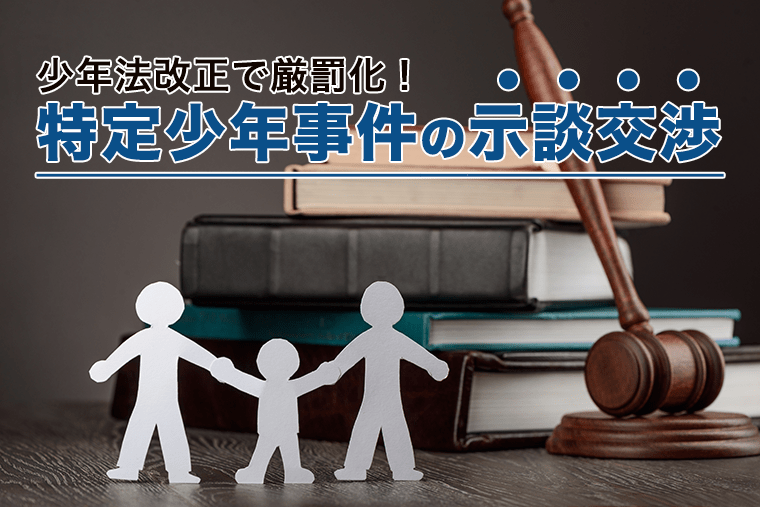
[参考記事]
少年法改正で厳罰化|特定少年事件の示談交渉
(3) 刑罰・処分の違い
刑法は、刑罰として「死刑」「懲役」「禁錮」「罰金」「拘留」「科料」「没収」の7種類を規定しています。
また、処遇の特殊なものとして、部分執行猶予制度(同法27条の2)等があります。
一方の少年法は、次のようなものを規定しています。
- 検察官送致決定(逆送決定)
家庭裁判所は、その少年に対して保護処分ではなく、刑罰を科すのが相当であると判断した場合には、決定により、事件を検察官に送致しなければならないとされています(同法20条)。
- 不処分決定
家庭裁判所は、調査・審判の結果、少年が非行事実を行ったことが認定できない場合や、非行事実は認定できるものの少年に保護処分を行うまでの要保護性が認められない場合には、不処分決定をしなければなりません(同法23条2項)。 - 保護処分決定
家庭裁判所は、調査・審判の結果、要保護性が認められる場合には、少年を保護処分に付する決定をしなければなりません(同法24条1項)。保護処分は、「保護観察」「児童自立支援施設又は児童養護施設への送致」「少年院送致」の3種類です。
なお、逆送決定は、少年から保護処分による改善教育を受ける利益を奪うという性格を持つものですから、それがなし得る場合が、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件に限定されています。したがって、罰金のみが法定刑として定められているような軽い犯罪については逆送決定はできません。
しかし、実務では少年が保護処分によってはもはや改善の見込みがない場合(保護不能)のほか、保護不能ではないものの事案の性質や社会への影響等から保護処分で対処するのが不相当な場合(保護不適)も、逆送決定が認められるとされています。
つまり、少年事件でも事件の罪質及び情状に照らして刑事処分が相当と認められるということです(同法20条1項)。
さらに、行為時点で16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪(殺人、傷害致死、危険運転致死、保護責任者遺棄致死、強盗致死など)の事件については、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときを除いて、逆送決定をしなければならないものとされています。これが、原則逆送制度と呼ばれるものです。
なお、逆送決定があっても、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認めるときは、裁判所は事件を家庭裁判所に移送しなければなりません。
これは、逆送決定に基づき刑事裁判に付された少年についても、その後に要保護性の変化が生じ得ることや、そもそも、可塑性に富む少年の事件については、少年を巡る状況の変化に応じて手続・処分の選択を変更できることが望ましいという観点から、再度、少年保護手続の枠内での処理に戻すことを認めるものです。
2.刑事事件の公判手続と少年審判手続の違い
成人が刑事犯罪を起こすと、事案によっては刑事裁判で刑事責任を問われることがあります。これが「公判手続」です。
一方、少年事件では少年をこれを保護する処遇を決める「少年審判」の手続きが行われることが通例です(例外として成人と同様の刑事裁判で刑事責任を問われることもあります)。
例えば、成人が窃盗を犯した場合、検察官は捜査の結果を踏まえ、成人を不起訴処分(起訴猶予)するか公訴提起するかを決めます。公訴提起は、簡易裁判所か地方裁判所になされ、裁判結果(判決結果)としては、罰金・執行猶予付・保護観察付執行猶予・実刑のいずれかが考えられます。
一方、少年が窃盗を犯した場合では、捜査機関は(犯罪の嫌疑がある限り)家庭裁判所に事件を送致しなければなりません(少年法41条42条・全件送致主義)。
家庭裁判所は、送致された窃盗事件につき、調査の結果、少年に要保護性(将来再び非行を行う危険性があること)が認められない場合には、審判不開始で手続を終了します。
少年に要保護性が認められる場合には、家庭裁判所は、保護観察・児童自立支援施設又は児童養護施設への送致・少年院送致のいずれかの保護処分に付す決定をします。
窃盗のような比較的軽微な犯罪ではなく、少年が、殺人、傷害致死、危険運転致死、保護責任者遺棄致死、強盗致死などの重い罪を犯した場合、原則逆送制度の導入により、少年も成人と同じ刑事裁判を受けることになります。
家庭裁判所が刑事処分相当として事件を検察官に送致し、これを受けて公訴が提起されれば、少年も公判手続において裁判されることになります。
刑事事件の公判手続は、裁判の公開が原則となっています(憲法83条)が、少年審判手続は非公開で行われます(少年法22条2項)。
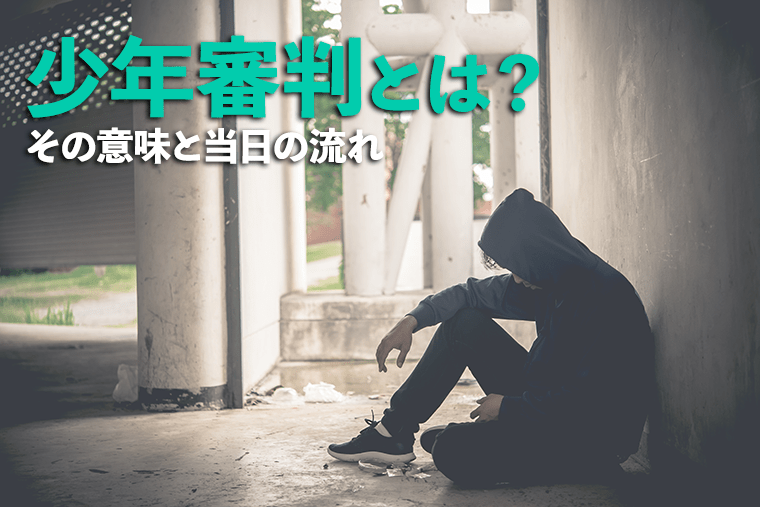
[参考記事]
少年審判を分かりやすく解説|その意味と当日の流れ
3.泉総合法律事務所は少年事件の経験も豊富
以上のように、成人が犯罪を犯した場合と少年が犯罪を犯した場合では様々な面で違いがあります。
そこで、少年事件に精通した弁護士のアドバイスに従い、家族とともに少年の更生を目指す必要があります。
少年が事件を起こしてしまった場合には、少年事件の経験豊富な弁護士に相談しましょう。
泉総合法律事務所は、これまで様々な刑事事件弁護活動を行なっており、少年事件についても同じく豊富な経験がございます。
初回相談は無料となっておりますので、少年事件でお困りの方はぜひ一度泉総合法律事務所にご相談ください。