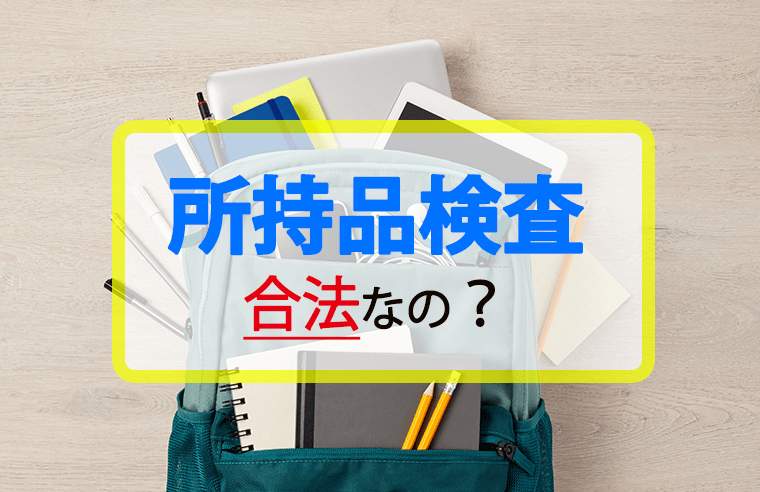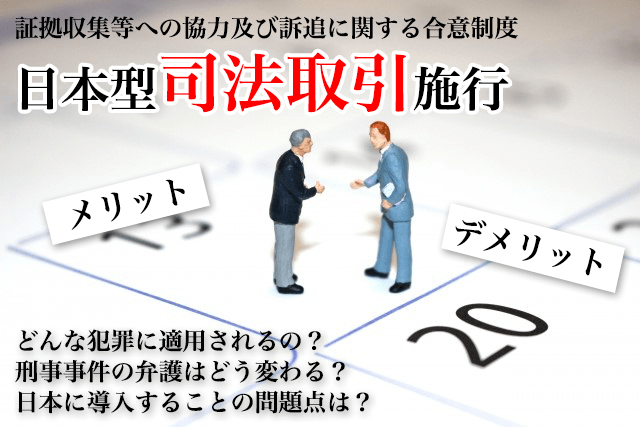裁判員裁判について分かりやすく解説|目的・メリットなど
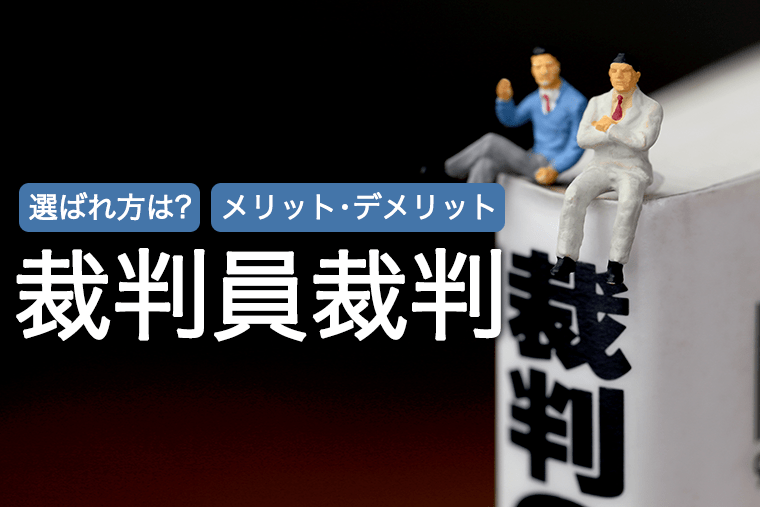
裁判員制度は、国民が刑事裁判に参加し、被告人の有罪・無罪をはじめ量刑をも決める裁判制度のことを指します。
2009年5月から導入され、これまでに多くの事件が裁判員裁判にて裁かれてきました。
今回はこの裁判員裁判(裁判員制度)について詳しく解説します。
1.裁判員裁判の目的と意義
裁判員制度は、「刑事訴訟事件の一部を対象に、広く一般の国民が、裁判官と共に、責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度」として、2009年5月に施行されました。
国民の関心の高い重大事犯につき、裁判官3人と裁判員6人で構成される合議体によって裁判が行われます。
国民が裁判の過程に参加することによって、「司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資すること」を目的としています(裁判員法1条)。
裁判員となった国民は刑事裁判に参加し、被告人の有罪・無罪を判断します。
(※刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見によるとされています(裁判員法67条2項)。)
従来から、司法制度自体が国民生活から切り離されたものであり、国民感覚とは異なる判決内容もあるとの批判があったことから、国民参加の裁判員裁判を導入することで、より身近な司法制度を築き、司法への信頼を高めようとしているのです。
なお、法曹三者(裁判官・弁護士・検察官)は、裁判員の負担を軽減するとともに、裁判員が事件の実体について十分理解し、適切な判断ができるようにするために、審理を迅速で分かりやすいものにしなければならないとされています(裁判員法51条)。
特に、「検察官及び弁護人は、裁判員が審理の内容を踏まえて自らの意見を形成できるよう、裁判員に分かりやすい立証及び弁論を行うように努めなければならない」のです(裁判員規42条)。
そして裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たせるように、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなどの配慮をしなければなりません(裁判員法66条5項)。
裁判員制度の導入によって、国民にとって分かりやすい裁判が実現されることも期待されているのです。
2.裁判員裁判の対象事件
裁判員裁判は、刑事裁判のうち地方裁判所で行われるものが対象であり、控訴審・上告審・少年審判は対象となりません。また、裁判の長期化が見込まれる事件は最初に省かれ、通常の裁判員裁判は5日程度(長期化したもので11日間)で終了します。
具体的に、裁判員裁判の事件の対象は、以下の通りです。
- 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に関する事件
- 複数の裁判官によって審理等が行われる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関する事件
罪名としては、殺人罪、強盗致死傷罪、強姦致死傷罪、強制わいせつ致死傷罪、現住建造物放火罪、覚せい剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法違反(営利目的輸入などに限られます)、保護責任者遺棄致死罪、危険運転致死罪、身代金目的誘拐罪、通貨偽造・同行使などが挙げられます。
3.裁判員の選ばれ方|辞退・無視できる?
裁判員は、満20歳以上の選挙権のある国民であれば誰しも選ばれる可能性があります。
選び方としては、まず毎年11月頃に翌年の裁判員候補者がくじで選ばれ、裁判員候補者名簿が作成されます。
名簿が作られたら、各人に通知と調査票を送付し、裁判員に就くことができない理由(就職禁止事由や不適格事由や欠格事由などの客観的な辞退事由)がないかを調査します。いずれかの事由に当たる場合は、候補者から省かれます。
裁判員制度の対象となる事件が決まったら、候補者名簿の中から新たにくじを行い、当該裁判員事件の候補者を選びます。
その後、原則裁判の6週間前までに、くじで選ばれた裁判員候補者に質問票を同封した選任手続期日のお知らせ(呼出状)が送られます。
質問票により、辞退が認められる人は呼出しが取り消されます。
例えば、事件と利害関係がある場合や、仕事や介護・学校などは辞退が認められる理由となります。
しかし、実際に辞退が認められるのは、法律に定めた以下のような辞退事由がある場合のみです。
- 70歳以上の人
- 地方公共団体の議会の議員(会期中に限る)
- 学生
- 5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人
- 3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出席した人(辞退が認められた人を除く)
- 一定のやむを得ない理由がある場合(重い病気又はケガ、重大な災害で被害を受け生活再建が必要、妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない、妻・娘の出産の入退院に付き添う必要があるなど)
なお、裁判員候補者として呼び出しを受けたにも関わらずこれを無視した場合には、10万円以下の過料に処される可能性もあります(裁判員法112条)。
もっとも、質問表を返送しないからといって刑事罰ではない過料と別に処罰されることはありません。
選任手続きを経て、最終的には、事件ごとに裁判員6人が選ばれます。
4.裁判員裁判のメリットとデメリット
次に、裁判員裁判のメリットとデメリットについて考えてみます。
(1) 裁判員裁判のメリット
裁判員裁判のメリットとしては、以下の3点がよく挙げられています。
- 一般感覚を取り入れた裁判が実現する
- 国民が司法制度を身近に感じられる
- 国民に理解しやすいように司法関係者が裁判制度を運用する
- 迅速な裁判の実行化
裁判員裁判は、直接国民が司法制度に参加することにより、一般感覚から離れた判決を防ぐことができるという利点があります。
具体的には、裁判員は証人に尋問し、被告人に質問するなどの権限を有しており(裁判員法56条ないし59条)、評議の際には、裁判官と同じ1票を持ちます(裁判員法66条2項)。
これまで国民から司法が切り離されているという批判がありましたが、この問題の改善が期待できるでしょう。
(※一方で、法令の解釈に係る判断、訴訟手続に関する判断、その他裁判員の関与する判断以外の判断については、構成裁判官だけの合議で判断されます(裁判員法6条2項)。)
裁判員が理解しやすくするために、裁判官・検察官・弁護士がわかりやすい裁判を展開するように工夫することもメリットです。
裁判は法曹関係者のみが理解できる内容であるべきではなく、国民の誰もが理解できる内容にすべきだからです。
裁判員裁判は、公判前整理手続きが行われることで争点の明確化、迅速な裁判の実行化が図られています。
裁判の長期化には批判も多かったですが、裁判員裁判の導入により迅速な裁判を実現できるのもメリットです。もっとも、裁判の準備に時間がかかり判決までの時間が伸びてしまうとの批判もあります。
(2) 裁判員裁判のデメリット
裁判員裁判には、残念ながら以下のようなデメリットも指摘されています。
- 裁判員の精神面の負担
- 公判期間が短い
裁判員裁判で取り扱われる事件は重大事件ばかりです。被告人に死刑や無期懲役が科せられることがあるため、一人の人生を変えてしまうという重責が伴います。
判決内容によっては「被告人、被害者のどちらからも恨まれるのでは?」という精神的ストレスを抱える人もいます。
また、悲惨な証拠内容が含まれると、裁判員が精神的に強い衝撃を受けることがあり、その心のケアも課題となっています。実際の公判では、裁判員の精神的な負担が大きくならないように凄惨な事件現場の写真について色彩を変えたりイラスト化されるといったことがなされています。
更に、裁判員裁判は裁判員の負担を軽減するため、5日間程度で終了します。迅速な裁判が行われるのは良いことですが「人の一生を左右する事情を裁くには短すぎる」という意見もあります。
5.裁判員制度の問題点
最後に、実際に運用が始まってからの裁判員制度の問題点について簡単に解説します。
(1) 辞退率の高さ
裁判員裁判で候補者となった場合、原則として辞退は認められません。しかし、実際に運用していくと辞退率の高さが問題となっています。
裁判員候補者になった場合、非正規で仕事を休むことが経済的に難しい、審理期間の長期化から参加が難しくなった、介護で手を離せないなどの理由で辞退をする人は増加しています。
運用当初の2010年には53%の辞退者でしたが、2020年には 66.3%と上昇しています(もっとも、近年は改善の兆しがあります)。
辞退率を下げるために、裁判所は呼び出し状や調査票の再通知などの工夫を行なっていますが、その他にも職場での理解を促す対策等も必要と考えられています。
(2) 守秘義務が解除できない
裁判員には、どのような過程を経て評議に至ったかという評議の秘密や、被告人のプライバシーに関わる事情など裁判員の職務上知り得た秘密を口外しないよう守秘義務が科されます。
とは言え、裁判員制度をより良く運用していくためには、実際に裁判員になった方の意見が重要です。裁判員裁判を経験したときに難しく感じたことや改善した方が良い点などは意見として収集していくべきですが、評議内容に関わると誰に対しても話せなくなってしまいます。
話して良いことと話してはいけないこととの境界線も曖昧であり、裁判員制度を検証するためにも、必要な限度において守秘義務の解除が必要ではないのかという問題が指摘されています。
6.裁判員に選ばれたらできる限り参加しよう
裁判員制度が始まった際は、「参加したくない」という意見が多かったのですが、実際に裁判員になった方の意見としては90%以上が「良い経験だった」と回答しています。
司法を身近に感じる機会になることは国民にとっても利点といえるでしょう。
皆さんも裁判員に選ばれたら、可能な範囲でご参加ください。
また、裁判員裁判の弁護活動についても、泉総合法律事務所の弁護士にどうぞお任せください。
→裁判員裁判の弁護活動について