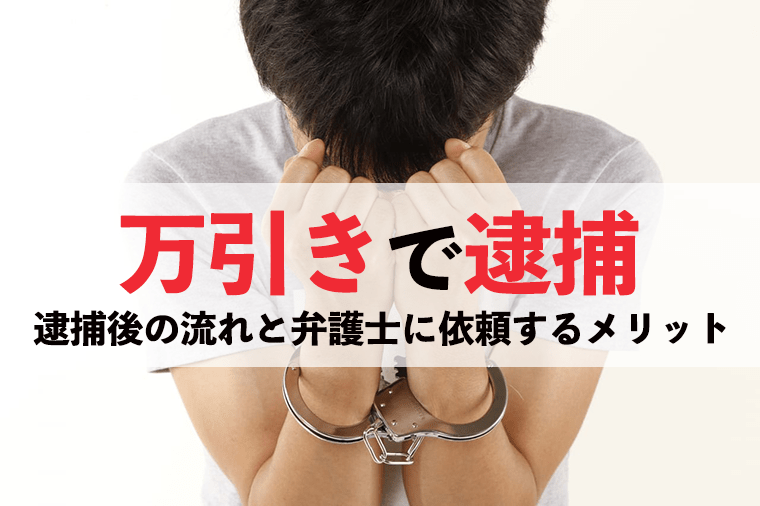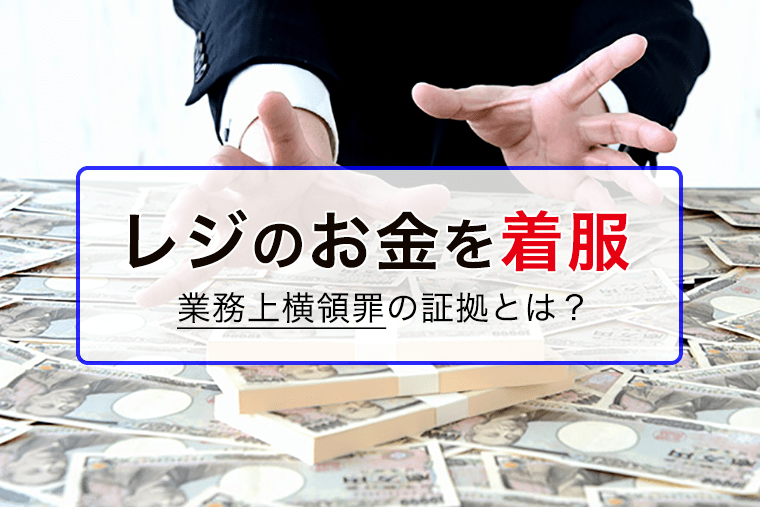窃盗罪、万引きの罪の重さ(罰金額・懲役)は被害金額で決まる?

衝動的に行うことも容易な犯罪である万引きは、被疑者の罪悪感も少ない場合が多いです。
「万引きは軽い犯罪だ」「見つかっても注意されるだけで終わるだろう」と思っている方はいらっしゃいませんか?
しかし、例え100円の商品でも、店員の目を盗んで窃盗行為をしたらそれは立派な犯罪となります。繰り返していると窃盗罪で逮捕・起訴され、実刑判決が下されてしまう可能性もあります。
ここでは、窃盗罪、特に万引きに焦点を当てて、万引きを行った場合どのような刑罰となるのか、罪の重さ(刑罰の重さ)はどう決まるのか、逮捕・起訴を免れるためにはどんな弁護活動が必要になるのかを説明していきます。
1.窃盗罪の刑罰
簡単に言うと、「勝手に他人の占有物を盗った」場合には窃盗罪になります。
刑法235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
ひとくちに「窃盗」と言っても、いろいろな態様があります。空き巣やスリ、ひったくり、下着・自転車泥棒、車上荒らしなども窃盗にあたります。
「万引き」も言葉は軽く聞こえるかもしれませんが、これも立派な窃盗罪です。
法定刑を見れば分かるように、窃盗罪には懲役刑があります。窃盗罪を犯した者には厳しい刑罰が科される可能性があります。
窃盗罪の成立には故意(占有を侵害する事実の認識)が要求されるだけでなく、これに加えて「不法領得の意思」も要求されます。不法領得の意思とは、「権利者を排除して、他人のものを自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思」をいいます(判例)。
例えば、他人の占有物を壊したり、隠したりするためだけの目的で占有を侵害した場合には、不法領得の意思が否定され、窃盗罪は成立しないでしょう。この場合には、毀棄隠匿罪が成立します。
(1) 微罪処分
万引きの場合、多くは数百円〜数千円の商品を盗ったという事件でしょう。
このように被害が少額で、前歴や前科がなく万引きをしたことを認め、商品を買い取るなど弁償を行った場合、まず考えられるのは「微罪処分」という扱いです。
仮に窃盗で現行犯逮捕されても、事件が正式な形で検察庁に送られることなく、警察限りで刑事手続が終了する取扱です。この場合には起訴されないので、刑罰が科されることはありません。
2014年犯罪白書によれば、2013年における窃盗で検挙され微罪処分となった人員の74.2%が万引き犯だったということです。
微罪処分に関して詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
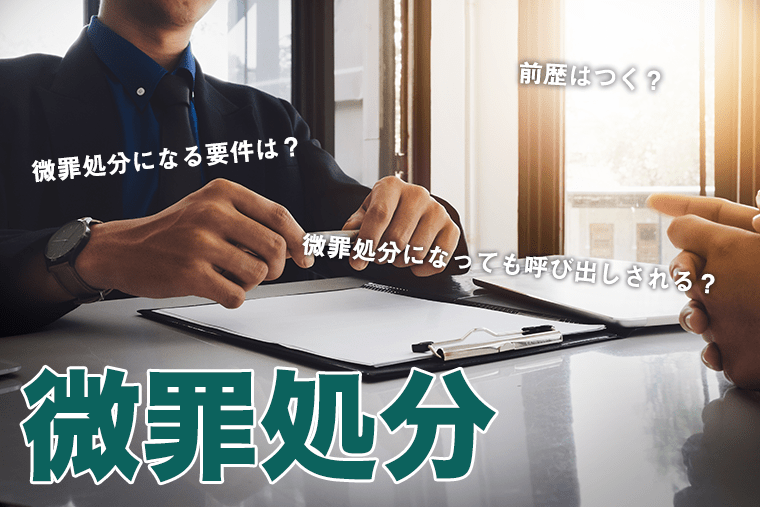
[参考記事]
微罪処分になる要件とは?呼び出しはあるのか、前歴はつくか
(2) 罰金(略式起訴)
微罪処分とならず事件が検察庁に送致されても、必ず公開の法廷での正式裁判にかけられるわけではありません。
検察官が、罰金刑が相当であると判断し、簡易な裁判手続での処理に被疑者が同意すれば、裁判所が書類上の手続だけで罰金刑を下す「略式手続(略式裁判)」となる場合があります。
検察官が裁判所に「略式手続」を求めることが「略式起訴」です。
2021年の統計では、窃盗罪で起訴された人員総数2万9,428人のうち、正式起訴(公判請求)された者が2万3,764人(約80%)、略式起訴された者が5,664人(約20%)となっています(※検察統計 2021年「8 罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」)。
罰金の金額は、次表のとおり30万円から50万円がボリュームゾーンです。
| 総数 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | |
| 公判請求(第一審) | 649 | 2 | 20 | 233 | 359 | 35 | 0 | 0 |
| 略式手続 | 5651 | 0 | 470 | 2210 | 2636 | 335 | 2 | 0 |
※令和2年版犯罪白書「2-3-3-4表・第一審における罰金・科料科刑状況(罪名罰)」から抜粋

[参考記事]
略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
(3) 懲役(正式裁判)
万引きの場合、前科がない人であれば罰金でとどまることがほとんどです。
しかし、盗んだ物がブランド品等数十万円する高額窃盗であった場合などには、万引きであっても罰金では済まず、正式な裁判を受けなければならなくなるかもしれません(※いくらからが高額窃盗にあたるかという明確な基準はありません)。
また、少額商品の万引きであっても、それを何度も繰り返して罰金刑を数回受けている人、つまり前科が複数ある人の場合には、いずれは必ず正式な裁判になります。
泉総合法律事務所の弁護経験では、万引きの額が少額でも、罰金刑を2回ないし3回受けた上で再度万引きを行ってしまった場合には正式裁判を受けることになる可能性が高いです。
平成26年の犯罪白書によれば、平成25年において、窃盗で検挙された成人人員のうち、20.6%が「同一罪名有前科者」すなわち、窃盗による前科を有する者だったとされています(※)。
※平成26年「6-2-1-13図 窃盗 同一罪名有前科者の成人検挙人員・同一罪名有前科者率の推移(主な手口別)」
(4) 執行猶予
初めて正式な裁判を受けた際の判決には、被害額の少ない万引きであれば執行猶予がつくことがほとんどでしょう。
しかし、それも通常は一度だけです。
万引きの有罪判決を受けて、その執行猶予中に万引きの再犯を行ってしまえば、被害額が少額であっても起訴される可能性が高いです。
そして、執行猶予中に犯罪を起こし起訴された場合には、特別に酌量するべき事情がない限り、再度の執行猶予を付けられないとの法律の定めがあります。
再度の執行猶予が認められずに有罪判決を受けたときは、前回の執行猶予付き判決は執行猶予取消しとなります。例えば、前回も今回も懲役刑の場合は、前回の懲役刑と今回の懲役刑と合わせた期間、刑務所に服役することになります。
また万引きの前科前歴が積み重なると「常習者」と判断され、「常習累犯窃盗罪」という3年以上20年以下の懲役刑が科される特別の法律(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条,刑法12条)に違反するものとして起訴される危険性があります。
万引きも窃盗というれっきとした犯罪であり、刑務所に入らなければならなくなる可能性もある重大な犯罪であるということを覚えておきましょう。
2.窃盗・万引きの量刑(罪の重さ)の決まり方
では、窃盗(万引き)で罪に問われた場合、処罰はどのように決まるのでしょうか。
窃盗罪の起訴・不起訴の処分、裁判での刑の重さが決められる際に、最も重視される要素の一つは被害状況です。
窃盗罪の被害状況とは、「①被害額がいくらだったのか」と、「②その被害額は弁償などで回復しているのか」という2点を意味します。被害者の財産権がどれだけの損害を受け、どれだけの損害が失われたままなのかという点が重視されるのです。
万引きであっても、高額商品であるほど起訴されて重い刑罰を受ける可能性が高くなり、低額な商品ではそれらの可能性は低くなります。
また、被害品が返還されたり、被疑者が商品を買い取ったり、被害弁償したりすることで、被害者の経済的な損失が補てんされていれば、重い刑罰を受けたりする可能性は低くなります。
ただし、起訴・不起訴の判断や刑の量定は、被害状況だけで決まるわけではありません。
犯行の動機・目的、計画性の有無、初犯か否か(同種前科・同種前歴の有無)、犯行態様、犯行後の行動、反省の情況、被害者の処罰感情など、様々な諸事情が総合考慮されるのです。
例えば、次のような場合は、被疑者に不利な事情として考慮されます。
- 犯行の動機・目的が転売目的
- 複数人で見張り役、目隠し役、実行役を分担するなど、態様が計画的で悪質
- 万引きの前科や前歴がある
- 店内で店員に発見されたが犯行を認めずに走って逃亡
- 被害品の返還も弁償もない
- 被害者である店舗側が厳重な処罰を強く希望している
3.窃盗罪の処罰を軽くする方法
検察官に事件が送致された場合でも、被害者に対する「示談」が成立すれば、不起訴処分となり前科を回避できる可能性があります。
示談交渉がうまくいくかどうかは被害店舗の性格によっても異なってきます。
一般的に、スーパーやコンビニですと、会社の方針で窃盗犯との示談には応じないところが少なくありません。
しかし、示談ができずとも、商品の買い取りに応じてもらうことで不起訴になることもあり得ます。
とはいえ、買い取りしたからと言って必ず不起訴になる保証があるわけではないので、万引きをして警察沙汰になってしまった場合には、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
仮に弁護士が示談を取り付けることができなくとも、泉総合法律事務所では、検察官に意見書を提出するなどして、不起訴を勝ち取ることを目指した弁護活動を行います。
一度逮捕された後も常習者として、もしくは執行猶予中に依存的に万引きを繰り返してしまう方は「クレプトマニア」という精神疾患の一種の可能性が高いといえます。このような場合、早期にクレプトマニアの治療を行っているクリニックや病院で診断を受けることをおすすめします。
最近は裁判所もクレプトマニアの実態に強い関心を持つようになっており、刑罰よりも治療が再犯防止につながると考え始めているようです。
参考:クレプトマニア(窃盗癖)特徴とは?診断基準・治療法と万引きの弁護
4.窃盗・万引きの刑事弁護は泉総合へ
以上のように、万引きをしてしまった方は一刻も早く弁護士に相談する必要があります。
泉総合法律事務所では、万引き事件の被疑者の弁護活動を多数行なっております。
窃盗などの刑事事件を起こして逮捕されてしまった方や、クレプトマニアの症状でお困りの家族の方は、前科をつけないためにも刑事事件に強い泉総合法律事務所の無料相談を是非ご利用ください。