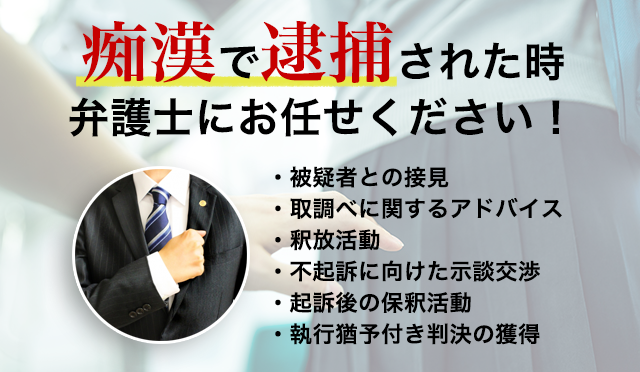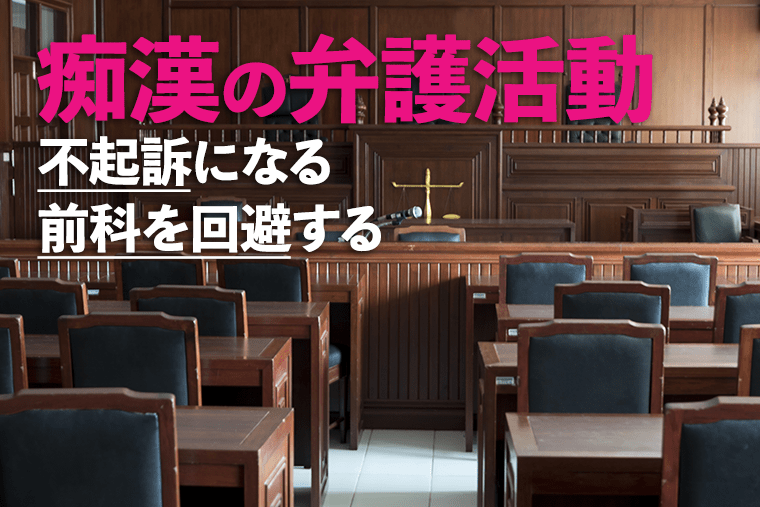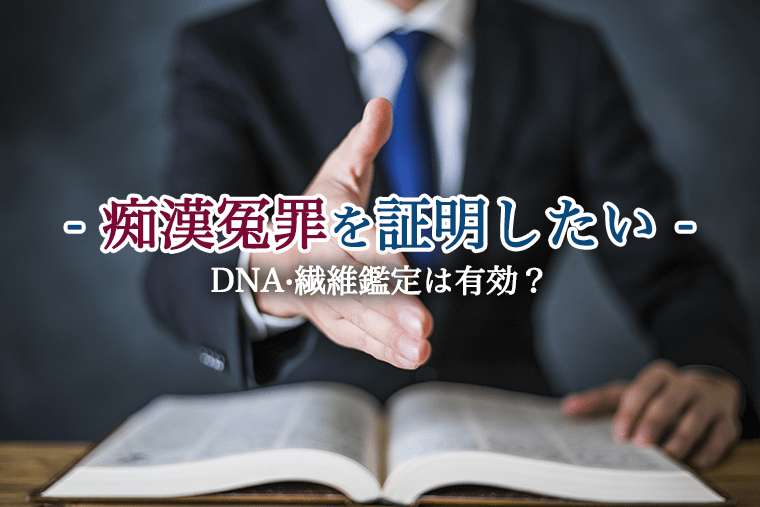痴漢で在宅事件・在宅捜査になった場合にとるべき対応

痴漢事件を犯してしまったときでも、身柄を拘束されずに在宅での捜査となることがあります。
在宅事件となれば、勤務先や学校に通うこともでき、普段通りの生活を維持することができます。
しかし、「在宅事件」となったことで、以降、身体拘束や起訴されることはないと予想して安心しきってはいけません。
在宅事件となった場合であっても、その後の状況の如何によっては、逮捕・勾留されたり、起訴されてしまうこともあります。
そのため、在宅事件における刑事手続きの内容や流れについてしっかり理解しておく必要があります。
この記事では、身柄事件、在宅事件の流れ、痴漢で在宅事件となった際にとるべき対応について解説します。
1.逮捕(身柄事件)と在宅捜査(在宅事件)の違い
捜査によって犯罪の被疑者が特定された場合でも、被疑者の身柄を拘束(逮捕)して捜査を進める場合(身柄事件)と、身柄を拘束せずに被疑者を在宅させたまま捜査を進める場合(在宅事件)とがあります。
どちらも刑事裁判の証拠を集める捜査という点では変わりありません。
(1) 身柄事件の流れ
警察官は逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と事件書類を検察官に送致する必要があります(送検)。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ってから24時間かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求します。請求しないならば釈放しなくてはなりません。
勾留請求を受けた裁判所は、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合には、被疑者の身柄を勾留する決定をします。

[参考記事]
逮捕後の勾留の要件とは?勾留の必要性を否定して釈放を目指す
身柄の勾留は、勾留請求の日から最大20日間です。この間に起訴されなければ釈放されます。
起訴された場合には、保釈が認められない限り、引き続き刑事被告人として身柄を拘束されます。
(2) 在宅事件の流れ
最初から逮捕せずに捜査を進めるケースや、当初逮捕・勾留をしたが途中で身柄を解放して捜査を継続する場合が在宅事件です。被疑者は在宅で通常の生活をしながら、捜査機関の呼び出しに応じて出頭し、取調べを受けることになります。
在宅事件となるのは、被疑者に逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れがないときです。例えば、次のような場合です。
- 軽微な犯罪
- 犯罪事実を認めている
- 家庭、職業がしっかりしている
- 家族や上司などが身元引受人となっている
- 共犯者がいない
- 初犯である・余罪はない
- 犯行様態が悪質でない
- 示談が成立している
なお、上記は犯人が明らかな場合を前提としています。
そもそも痴漢行為の証拠が乏しく、被疑者に痴漢事件の嫌疑があるとまで言えないときは、逮捕も勾留も認められませんから、当然に在宅事件となります(もちろん、在宅捜査によって証拠収集が進み、嫌疑が深まれば、その段階で逮捕される可能性はあります)。
在宅事件の場合、必要があれば捜査機関から呼び出しがかかります。
呼び出しの回数や在宅捜査が続けられる期間は事案によります。在宅事件の場合には、後に述べる通り、時間制限がありませんから、すぐに捜査が終わり処分決定となる場合もあれば、捜査機関から処分についてなかなか連絡がこない場合もあるでしょう。
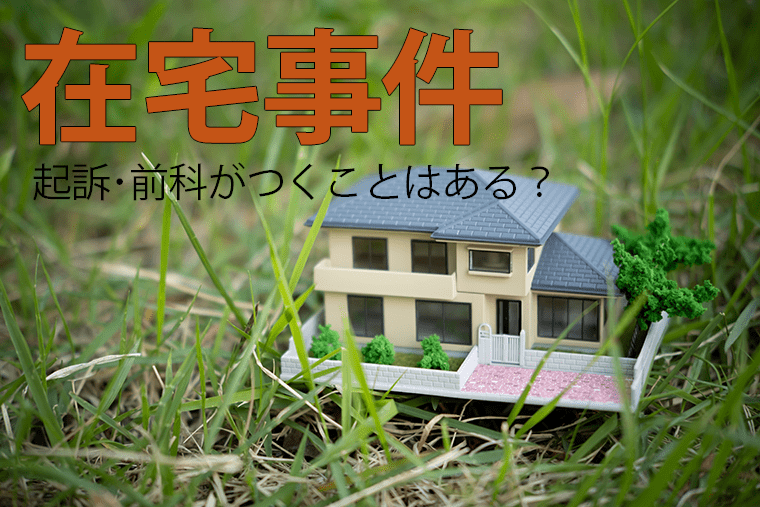
[参考記事]
在宅事件の流れ|起訴・前科がつくことはあるのか
ニュース番組などで、有名人が書類送検されたことを耳にすることがあります。
書類送検とは、被疑者の身柄を拘束せずに、事件(書類)だけを検察官に送致することをいいます。
書類送検された事件が起訴相当となったときには、在宅事件のまま起訴されます(在宅起訴)。この場合、悪質とまで言えない痴漢事件で、初犯などの場合には通常の公開法廷での刑事裁判ではなく、書類上の手続だけである略式手続での罰金刑が科されることが一般的です。
略式手続について、詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。
参考:略式起訴・略式裁判で知っておくべきこと|不起訴との違い
2.在宅事件のメリット・デメリット
身柄事件と比較した場合の在宅事件のメリット・デメリットについて、以下で確認しておきましょう。
(1) 在宅事件のメリット
在宅事件のメリットをまとめると次の通りになります。
- 身柄を拘束されないので、肉体的・経済的・精神的な負担が少ない
- 普段通り通勤・通学できる(解雇・退学のリスクがなくなる)
- 身柄事件に比べて不起訴となる可能性が高い
在宅事件の最も大きなメリットは、やはり「身柄を拘束されない」ことに尽きます。
身柄事件となれば、起訴・不起訴が決まるまで最大で23日間通勤・通学が不可能となり、欠勤・欠席の理由を説明できなければ、勤務先や学校から不利益な処分(解雇・減給・退学など)を科される危険性があり、事実上、日常生活に多大な影響を受けてしまいます。在宅事件では、その心配はありません。
また、在宅事件では、身柄を拘束されていないので、自らの手で信頼できる弁護士を探すことも可能となります。
(2) 在宅事件のデメリット
実は、在宅事件はメリットばかりではなくデメリットもあります。
在宅事件の一番のデメリットは、「捜査期間の定めがない」ことです。
身柄事件では、検察官は逮捕後最長23日以内に「起訴・不起訴」を判断しなければなりません。この期間中に検察官が起訴しないときには、被疑者を釈放しなければなりません(もちろん、処分保留として釈放し、その後、在宅事件として捜査を継続し、最終的に起訴することも可能です)。
しかし、在宅事件では、公訴時効以外は何も期間制限が定められていません。そのため、捜査が長期化する可能性があります。
起訴の有無について被疑者に連絡がくるまで数ヶ月、1年以上かかることも珍しくなく、被疑者としては今後どの程度の期間が経てば自分の処遇が決まるのかについて予想できない場合が多いです。そのため、身柄事件に比べ長期間「起訴されるかどうかわからない」状態に置かれることになります。
また、在宅事件では、「起訴前の国選弁護人選任」の制度がありません。そのため、私選弁護人を選任しなければ、示談や検察官との交渉に必要な弁護活動を行ってもらえません。
この後に説明するように、「在宅事件となった」ことに安心しきって私選弁護人を選任せず、在宅捜査中に当然なしておくべき弁護活動を依頼しなかったために、最終的に起訴され、有罪となるケースもあり得ます。
3.痴漢で在宅捜査となった場合の注意点
(1) 警察・検察官の呼び出しにはきちんと対応する
在宅事件の取扱いとなるのは、多くの場合、「逃亡」や「証拠隠滅」によって捜査に支障を来さないと判断されたからです。したがって、警察署や検察庁への呼び出しや電話があったときには、きちんと対応しなければなりません。
犯罪事実を認めている在宅事件における各捜査機関からの呼び出しは1~2回ずつのことが多いですが、事件によってはそれ以上に及ぶ場合もあります。
出頭要請に応じないなど、警察や検察官に対し不誠実・非協力的な態度をとると、証拠隠滅、逃亡の危険を疑われて、逮捕される危険もあります。
(2) 在宅期間中の行動に気をつける
先述のように、在宅事件では、捜査が数ヶ月~1年以上におよぶことも珍しくありません。
捜査機関は、期間制限のために、集中した捜査を必要とする身柄事件の処理を優先しますから、どうしても在宅事件の捜査は「時間のある時に」まわされます。また、検察・警察の忙しさや、被害者の対応(例えば被害者がなかなか事情聴取に応じないなど)によっても、時間がかかることがあるからです。
長く時間がかかっているからといって、「有罪になってしまうのではないか」と不安に煽られ姿を隠すこと、示談を急ごうと自分で被害者に直接コンタクトをとろうとすることは絶対にいけません。
前者は逃亡に他なりませんし、後者は証人威迫や御礼参りの意図を疑われ、いずれも自ら逮捕される理由を提供してしまう危険があるからです。
4.「不起訴」となるために在宅事件ですべきこと
痴漢事件を起こしたときに最も重要なのは「不起訴処分」にしてもらい、前科をつけないことです。起訴されてしまえば、罰金刑や執行猶予付きの判決でも前科がついてしまうからです。
身柄を拘束されずに済んだということで、安心しきってはいけません。「在宅事件=不起訴」というわけではないからです。
では、在宅事件で不起訴となるためには、どうすれば良いのでしょうか?
痴漢行為の有無を争わない場合には、被害者との示談を成立させることが重要です。
示談は、示談金の支払いと引き換えに、被害者が加害者を許すという合意です。示談金によって被害の賠償が行われ、被害者が処罰を望まなくなったことが明らかになり、加害者を刑事裁判にかける必要性が低下したと評価されるのです。
さらに、性犯罪では、被害者のプライバシー保護の観点から、起訴・不起訴にあたって被害者の意向を尊重する運用がとられるので、示談に応じた被害者の意向に反した起訴はなされないことが通例です。
このように検察官は、示談の成否を起訴の判断において非常に重視するので、示談が成立すれば、不起訴となる可能性が格段に高まります。
初犯であれば、示談成立によってほとんどのケースで起訴を回避できるでしょう。
逆に、在宅事件になったと安心して、示談に向けての努力を疎かにすれば、「示談が成立してない」「示談を成立させるための努力すらしておらず、真摯な反省が疑われる」ということで、かえって検察官の心証を悪化させてしまい、起訴されてしまうこともありえます。
せっかく在宅事件となったのに、そのような残念な結果を招かぬよう、早期に刑事事件の被害者と示談をまとめるためには、在宅事件であっても、早期に弁護士に示談交渉を依頼することが必須です。

[参考記事]
痴漢で逮捕された場合の示談交渉は弁護士へ依頼
5.痴漢で在宅事件となっても泉総合法律事務所へ相談を
身柄を拘束されずに在宅事件となれば、どうしても安心してしまいがちです。普段通りの生活を行えるようになれば、仕事や学校の都合で、事件の対応が後回しとなってしまうこともあるでしょう。
しかし、在宅事件だからといって不起訴が確定したわけではありません。
在宅事件では、捜査期間中にきちんと対応して示談を成立させれば、高い確率で不起訴とすることができます。
在宅事件だからと気を抜いてしまうことなく、できるだけ早く、刑事事件に詳しい泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。