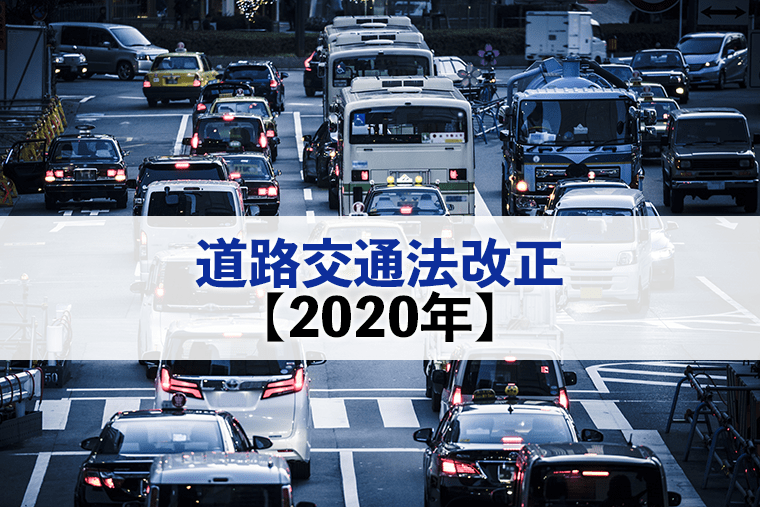当て逃げで罰金がつくと前科です!対策方法と弁護士への依頼
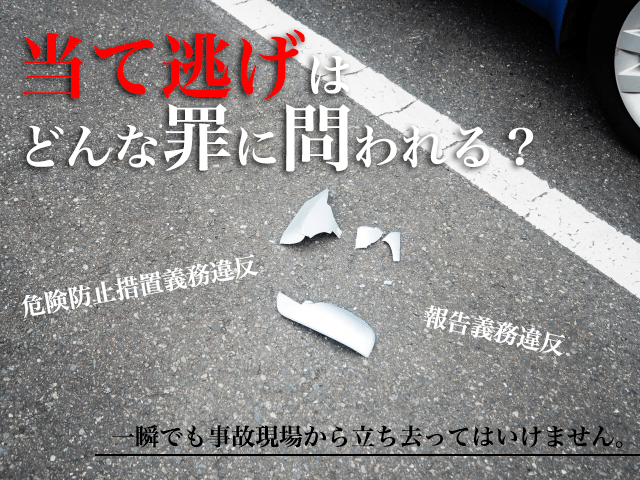
「当て逃げ」は、「ひき逃げ(轢き逃げ)」と比べると、軽く考えられることが多いです。
「物損事故なら届け出なくても大事にはならない」「誰も怪我をしていないのだから、たいしたことではない」などと考えて、警察に届け出ないケースも多々あります。
しかし、当て逃げも「道路交通法違反」の違法行為であり、検挙されれば刑罰も適用されます。
今回は、当て逃げ行為をした場合の刑罰や、望ましい対処方法(示談のポイント)について解説します。
1.当て逃げの罪
当て逃げは、車を運転していて他の車両や施設などの物を損傷したにも関わらず、危険防止措置・警察への報告をせずに走り去ってしまう行為です。
では、当て逃げは何罪に当たり、どのような罰則(罰金)になるのでしょうか?
(1) 危険防止措置義務違反と報告義務違反
車両の運転者は、運転していて交通事故を起こしたとき、必ず現場に停車して周辺に発生している危険を除去すべき義務を負います。
この義務のことを「危険防止措置義務」と言います(道路交通法72条1項前段)。
具体的には、道路上に散らばったものを片付けたり、車を路肩に寄せて交通の邪魔にならないようにしたり、発煙筒や三角表示板を置いて後続車に事故を知らせたりしなければなりません。
また、交通事故を起こした当事者は、必ず速やかに警察に連絡する義務も負います(道路交通法72条1項後段、警察への報告義務)。
以上の危険防止措置義務と報告義務は、人身事故でも物損事故でも、交通事故の当事者(車両の運転者や他の乗務員)に課される道路交通法上の義務です。
そこで、交通事故で物損被害を引き起こしておきながら、危険防止措置もせず警察への届出もせずに逃げてしまう行為は、道路交通法違反の違法行為となります。
上記のように、当て逃げは、物損事故を起こして危険防止措置や警察への報告をせず、そのまま立ち去ってしまったケースです。
これに対してひき逃げは、人身事故を起こして被害者を救護せず、危険防止措置や警察への報告もせずに事故現場を立ち去ってしまったケースです。
当て逃げとひき逃げの違いは、「物損事故」か「人身事故」かという点です。
ひき逃げで加害者が被害者を救護しなかった場合、救護義務違反という重大な犯罪となり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が適用されます。なお、被害者の死傷が、その運転者の運転に起因していない場合でも、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑となります。つまり、たとえ「もらい事故」でも、救護義務に違反すれば犯罪となるのです。
もっとも救護義務違反が成立するためには、人の死傷という結果を認識していることが必要ですので、単なる物損事故だとしか認識せず、人の死傷があったとの認識を欠いているときは、救護義務違反は成立しません。ただし、人の死傷があったと確定的に認識している必要はなく、「もしかしたら、人が怪我をしたかもしれない」という未必的な認識があれば足りるとするのが判例です(※最高裁昭和47年3月28日判決)
【参考】ひき逃げの罪-必ず後日に検挙されて逮捕される?弁護士必須の重大事件
一瞬でも事故現場から立ち去ってはいけない
「交通事故後現場から立ち去っても、すぐに戻ってきたら当て逃げにならない」と考えている方がいらっしゃいます。
また、弁護士が「事故後何分以内に現場に戻ってきたら、当て逃げにならないのですか?」と質問されることもあります。
しかし、現実には「何分以内に戻ってくれば良い」というものではありません。
道路交通法72条1項は、「交通事故があつたときは(中略)直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない(後略)」と定めており、「直ちに」とは「即時」を意味しますから、少しでも現場を離れれば違反となるのです。
したがって、いったん事故現場から立ち去ってしまったら、たとえ1分後に速やかに戻ってきたとしても「当て逃げ」となります。もちろん「ひき逃げ」も同じです。
また、人身事故における救護義務違反と同様に、物損事故における危険防止措置義務違反・報告義務違反が成立するには、物損、すなわち物の損壊という結果が生じたことの認識が必要ですから、車が物に当たったけれど、壊れてはいないと認識していた場合は危険防止措置義務違反・報告義務違反は問われません。ただし、物が壊れたかも知れないという未必的な認識があれば別です。
さらに、危険防止措置義務・報告義務は、「交通事故があつたとき」に課される義務であり、その事故が運転者の故意過失に基づくことを要求していませんから、運転者に何らの責任もない「もらい事故」であっても、これらの義務に違反すれば犯罪となります(※弁護士高山俊吉「入門・交通行政処分への対処法」(現代人文社)88頁)。
したがって、自分に非があるか否かに関係なく、他人の車や物を損傷してしまった、あるいは、もしかしたら物が壊れたかなと思ったら、すぐに車を停止して危険防止措置を行い、警察に通報することが重要です。
(2) 刑罰(懲役・罰金)
では、実際に当て逃げをすると、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?
先述の通り、当て逃げで成立する犯罪は、道路交通法上の危険防止措置義務違反と警察への報告義務違反です。
危険防止措置義務違反の罰則(道路交通法117条の5第1項)
1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑報告義務違反の罰則(道路交通法119条1項10号)
3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑
危険防止措置義務違反と報告義務違反は「観念的競合(1つの行為によって2つ以上の罪に該当する場合)」(刑法54条1項)という関係になるため、重い方の危険防止措置義務違反の刑罰によって裁かれることになります(※前出の最高裁昭和47年3月28日判決同旨)。
以上より、当て逃げで適用される刑罰は「1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」となります。
実は、当て逃げでは器物損壊罪は成立しません。何故なら、器物損壊罪は「故意犯」だからです。
故意犯というのは、「故意」がないと成立しない犯罪です。つまり、わざと物を壊した場合でない限り、器物損壊罪にはならないのです。
交通事故事案では、加害者は通常「過失」によって事故を起こしているので、物を壊したことに関しては故意が認められず、器物損壊罪が成立することはありません。
ただし、積極的に相手を困らせてやろうと思い、わざと車を当てて物を壊して逃げた場合には、道路交通法違反と共に、器物損壊罪が成立します。器物損壊罪は親告罪なので、被害者が刑事告訴をすると、加害者は道路交通法違反だけではなく、器物損壊罪によっても処罰されることとなります。
(3) 当て逃げによる点数(加点)
免許の点数とは、道路交通法違反や交通事故によって加算される行政罰としての点数のことです(刑事罰とは別)。
日本の免許制度では、違法行為があると免許の点数を加算していき、一定の点数に達すると免許が停止されたり免許を取り消されたりします。
交通事故を起こしたとき、通常の物損事故であれば運転免許の点数は加算されません。
しかし、当て逃げをすると7点が加算されます。うち2点が安全運転義務違反、5点が危険防止措置義務違反です。
合計7点が加算されると、前歴がない方の場合であっても30日間の免許停止処分となります。
物損事故では、きちんと報告さえしていたら免許の点数は加算されないのですから、当然当て逃げなどすべきではありません。
2.当て逃げの対象となる「物」の定義
一般的に「当て逃げ」というと、「相手の車両」を壊した場合だと思われていることが多いです。
しかし、当て逃げ被害の対象は車両だけにはとどまりません。交通事故では、「人」以外の損害は基本的にすべて「物損」として取り扱われます。
たとえば、以下のような物を壊したり損傷させたりした場合にも物損事故となります。
車両・積荷・ガードレール・建物・街路樹・ペット
法律上、動物は「物」と同じ扱いになるので、犬や猫を轢いてしまった時、その動物が他人のペットであれば当て逃げとなってしまいます。
これらは、たとえ警察に検挙されなくても、被害者に対する民事賠償責任が発生します。
3.当て逃げの加害者になってしまったら
とは言うものの、物損事故を起こした後、気が動転して逃げしてしまう場合があるかもしれません。
一度逃げてしまった場合には、どのように対応するのが良いのでしょうか?
(1) 警察に届け出る
まずは、当て逃げしたことを自分から警察に申告しましょう。
当て逃げしてしまった場合、現行犯で逮捕されるケースは少ないです。
しかし、すぐには警察に見つからなくても、数か月が経過した後などに後日逮捕されたり、任意同行を求められたりする可能性があります。
事故が発覚していない段階で出頭すると、「自首」が成立して処分を軽くしてもらうことができます。
また、たとえ自首が成立しないケースであっても、加害者自らが出頭したら、情状で不起訴になる可能性が高くなるでしょう。
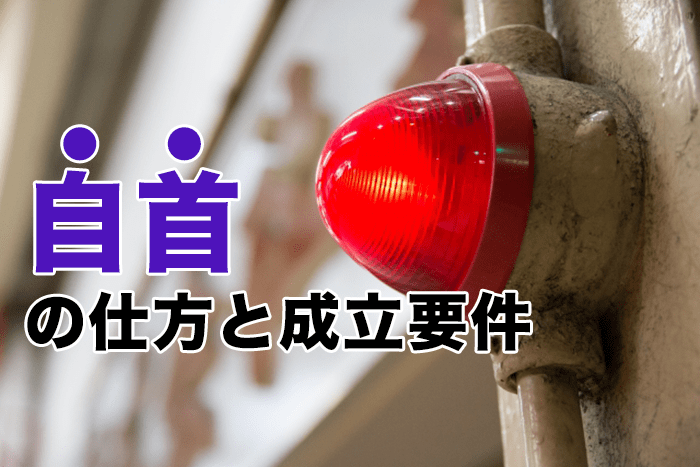
[参考記事]
自首の仕方と成立要件|出頭との違いとは?
また、交通事故後、早期に物損事故を警察に届け出ると、自動車安全運転センターで交通事故証明書を発行してもらえる可能性があります。
交通事故証明書を保険会社に提出すれば、対物賠償責任保険を利用できます。
通常、任意保険の対物賠償責任保険に加入している場合には、被害者への物損被害の賠償金は保険会社から支払ってもらうことができます。
しかし、当て逃げして警察に届出をしなかった場合、交通事故証明書が発行されず、交通事故が起こった事実を証明できなくなってしまう可能性があります。そうなると、自動車保険を使うことができないので、被害者への損害賠償金を加害者が自腹で支払わなければなりません。
また、保険会社が示談交渉を代行してくれないので、自分自身で被害者と話し合いをする必要があり、トラブルが大きくなりやすいです。
一方、きちんと届出をしたら、保険会社が示談交渉に対応し、賠償金の支払いも行ってくれます。
(2) 示談で起訴を免れる?
当て逃げの場合、検挙されても公判請求(法廷での正式裁判を求められること)されることは少なく、多くの場合には略式起訴となり罰金刑が適用されます。
しかし、罰金刑であっても前科がつきます。
ですから、略式起訴であっても避けたいところです。
被害者のいる犯罪では、起訴・不起訴に大きな影響を与えるのは、被害者との示談を成立させることです。
しかし、危険防止措置義務や報告義務を定めた道路交通法は、「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」(同法第1条)と規定されており、社会全体における交通の安全・円滑という社会的な法益を守るものです。
それゆえ、当て逃げによる危険防止措置義務違反や報告義務違反には被害者という者が観念できず、あえて言えば、社会全体が被害者ということになります。
したがって、当て逃げによる危険防止措置義務や報告義務では被害者との示談ということは考えられません。
他方、当て逃げで壊された車の所有者など、物損の被害者に対しては、民事上の損害賠償責任がありますので、この面では示談交渉を行うことになります。対物賠償保険等に加入していれば、保険会社が示談代行を行ってくれます。
4.当て逃げをしたらお早めに弁護士へ相談を
当て逃げは道路交通法違反の犯罪行為となりますし、放っておくと逮捕されて前科がついてしまう可能性もあります。決して軽く考えてはいけません。
お一人で対応することが難しい場合には、泉総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士までお早めにご相談下さい。
当て逃げをしてしまったという方の中には、飲酒運転や無免許運転が原因という方がいらっしゃるかもしれませんが、泉総合法律事務所ではそのような案件にも対応しております。
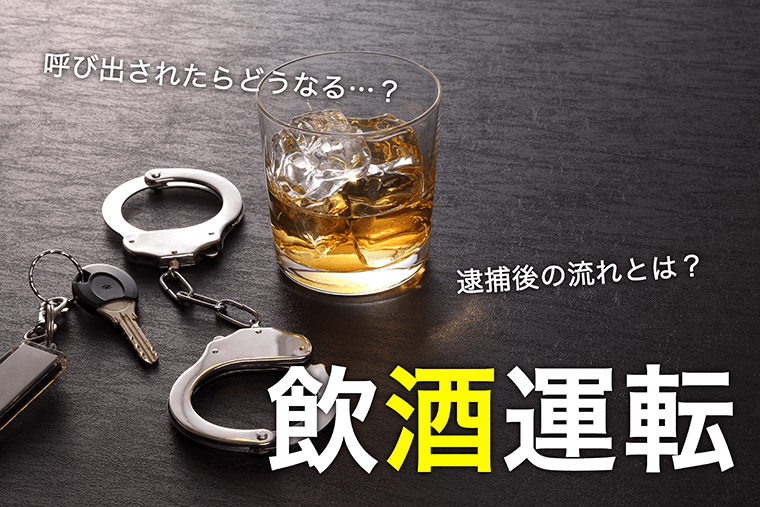
[参考記事]
飲酒運転で呼び出し!?逮捕後の流れ

[参考記事]
無免許運転をした場合、逮捕・懲役になってしまうのでしょうか?