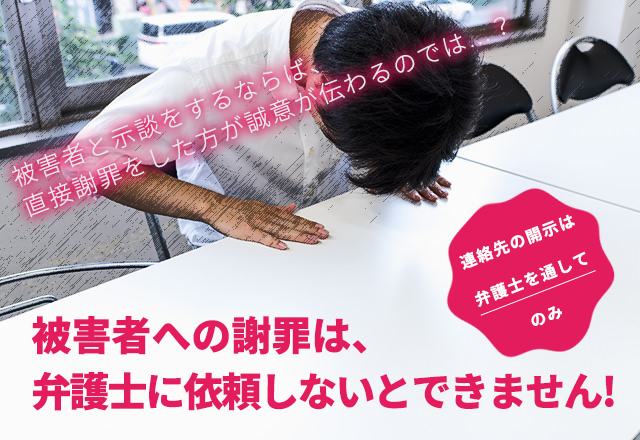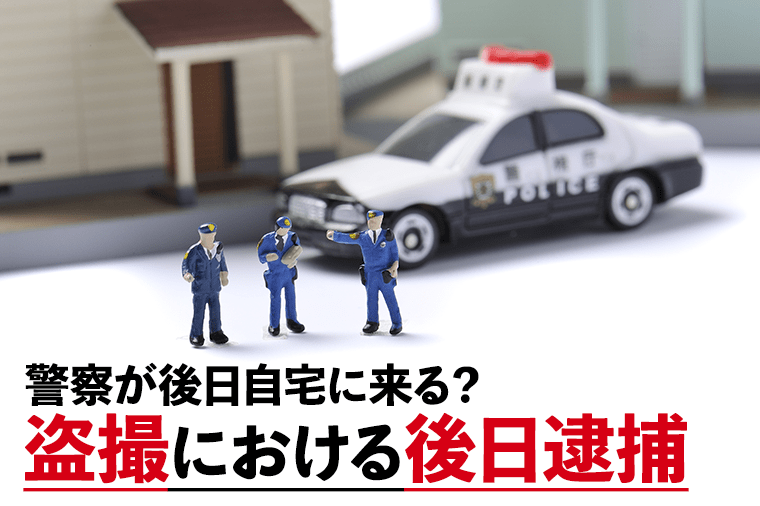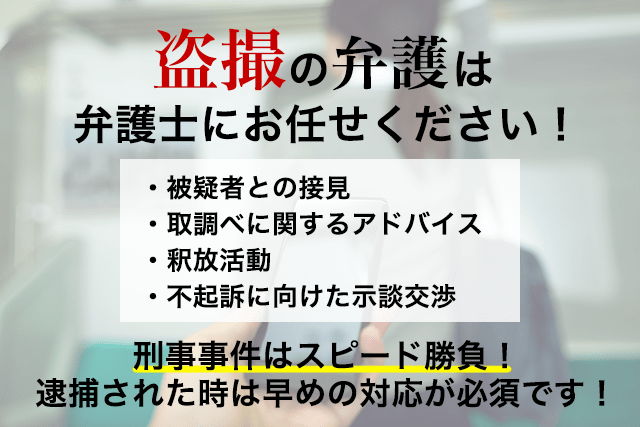盗撮事件で懲役刑(実刑)・執行猶予になる可能性はある?

盗撮は軽微な犯罪と思われがちで、「注意されて終わり」「罰金を支払えば釈放される」などと考えている方も多いでしょう。
しかし、盗撮の被疑者(被告人)にも懲役刑が科される可能性や、執行猶予判決となる可能性はあります。
特に、盗撮を複数回行っている場合や、執行猶予中の場合には実刑となるリスクが一気に高まるでしょう。
今回は、盗撮事件で逮捕され懲役刑(実刑)になるケースや、執行猶予判決がされるケースについて解説していきます。
1.盗撮事件に適用される法律
まず、盗撮事件の法律上の刑罰(刑期)を見ていきましょう。
「盗撮」という言葉は刑法典上には存在せず、盗撮行為それ自体は刑法で処罰される犯罪ではありません。しかし、刑法以外で盗撮行為を処罰する法令があります。
盗撮行為の態様や盗撮に伴う行為、犯行が行われた地域によって、適用される法令が異なります。
(1) 迷惑防止条例違反
駅構内などの公共の場所、電車内などの公共の乗物内で、通常衣服で隠されている部位を写真機などで撮影する行為などについては、各都道府県において制定されている迷惑防止条例が適用されます。
東京都では、以下の内容になっております。
【盗撮行為等が禁止対象となる場所】
・住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所 (5条1項2号イ)
・公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(5条1項2号ロ)【禁止される行為】
・人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為(5条1項柱書、同2号)
法定刑……1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号)、常習犯は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項)
・人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影するために撮影機器を差し向け又は設置する行為(5条1項柱書、同2号)
法定刑……6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号)、常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項)
盗撮を犯す人は「軽い気持ちでやってしまった」というケースもありますが、上記の通り懲役刑もある重い犯罪であることを肝に銘じるべきです。
(2) 軽犯罪法違反
規制場所が公共の場所・公共の乗物に限定されている自治体においては、被害者の住居内を盗撮しても迷惑防止条例違反とはなりません。
しかし、盗撮行為には、通常、他人の住居などを覗き見る行為を伴いますので、次の軽犯罪法が適用されることになります。
のぞき見 軽犯罪法1条23号
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
拘留は、1日以上30日未満の日数の間、刑事施設に留置するという刑罰です。これは懲役刑とは異なり、施設内での労働を強制されることはありません。
科料は1000円以上1万円未満の金銭の支払いです。罰金刑に似たものと考えて良いでしょう。
ただし、拘留も科料も刑罰ですから、前科となってしまう点では懲役刑や罰金刑と変わりはありません。
このように、軽犯罪法違反だけなら懲役刑はありません。
しかし、盗撮行為に伴い、人の家やその敷地に入り込んだならば、その侵入行為には住居侵入罪が適用されて懲役刑が選択されることもあります。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
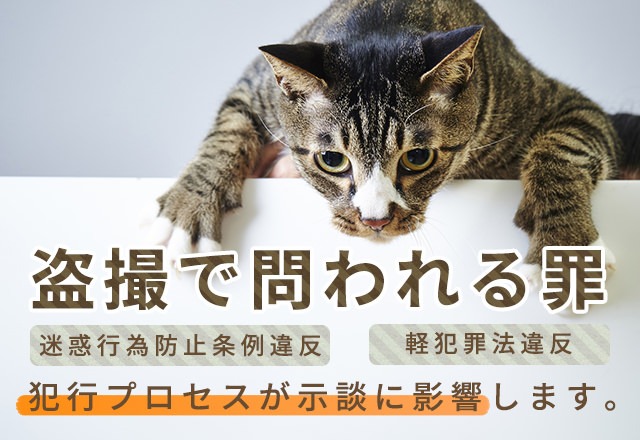
[参考記事]
軽犯罪法違反の盗撮|迷惑行為防止条例違反との違いと示談方法
2.盗撮で捕まり懲役刑になるケース
以下では、懲役刑が定められている迷惑防止条例違反の盗撮を念頭に置いて説明します。
盗撮で捕まったら、一体どのようなケースで懲役刑になる可能性があるのでしょうか。
(1) 初犯の場合、懲役刑の可能性は低い
初犯では、住居侵入行為を伴ったり、盗撮画像をネットで公開・販売していたりといった悪質性の高い事案でない限り、仮に起訴されてもせいぜい罰金刑であり、懲役刑が選択されることはないでしょう。
なお、罰金刑も回避するには被害者との示談を成立させることが重要です。
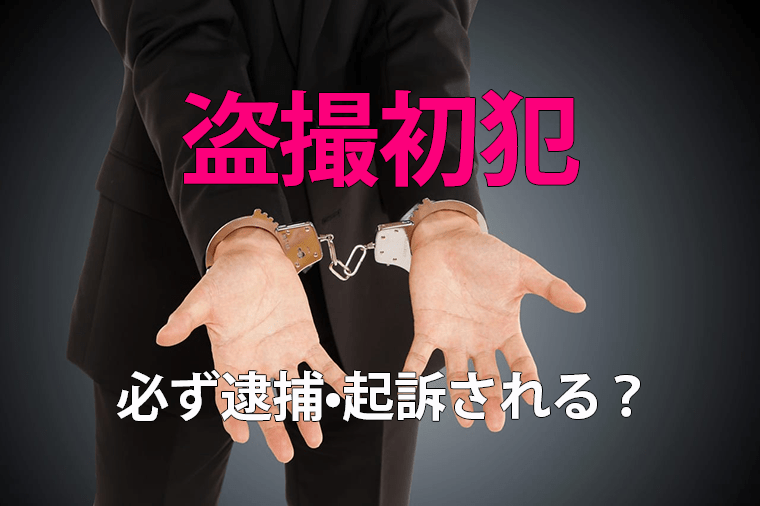
[参考記事]
盗撮で初犯の場合|逮捕・起訴される?
(2) 盗撮の前科・前歴があれば懲役刑の可能性
過去にも盗撮で立件されたことがある場合には、起訴されて懲役刑が選択される可能性もあり得るでしょう。
しかし、この場合でも必ず懲役刑になるというわけではありません。刑事弁護次第では起訴猶予となったり、起訴されても略式起訴(罰金刑)となったりする可能性が大いにあります。
(3) 執行猶予中なら実刑となる可能性が高い
過去に盗撮で執行猶予判決を受け、その執行猶予中に盗撮をした場合、起訴されたうえ執行猶予がつかず懲役刑となる可能性が高いでしょう。
極めて厳しい要件を満たして再度の執行猶予が付されるケースもなくはないですが、ほとんどの場合は実刑判決となって、前の懲役刑と合計した期間の服役をすることになるでしょう。
過去の執行猶予付判決が盗撮行為とは関連性のない異種の犯罪に対するものであった場合は、今回の盗撮行為で起訴されるか否か、起訴された場合に懲役刑が選択されるかはケースバイケースです。
しかし、執行猶予中の犯行であることは、不利な事情として斟酌されることは避けられません。
このようなケースでも、懲役刑を回避するために最も重要な方策が被害者との示談であることに変わりはありません。
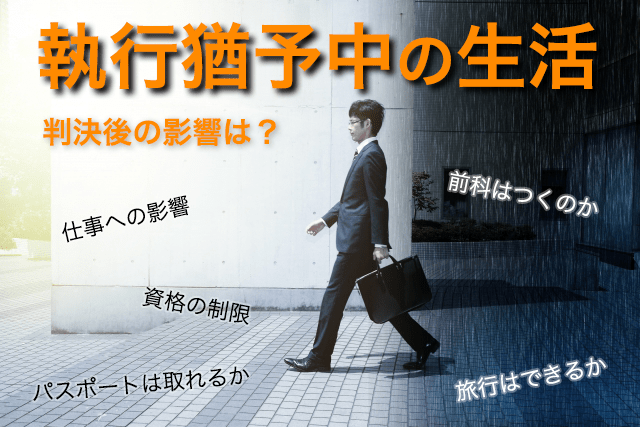
[参考記事]
執行猶予とは?執行猶予付き判決後の生活|前科、仕事、旅行
3.盗撮で実刑・前科を避ける方法
盗撮行為に対しては、懲役刑、罰金刑、拘留、科料という罰則が用意されています。いずれも刑罰であって、有罪判決が確定すれば前科となってしまいます。
ことに懲役刑は、長期間刑務所に拘禁されて強制的に労働させられる刑であり、本人はもとより家族など周囲に与える精神的・経済的な打撃は測り知れません。
懲役刑を避けるには、検察官に不起訴処分(起訴猶予)としてもらうか、最悪でも罰金刑となる略式起訴にとどめてもらう必要があります。
そのために最も重要なことは、被害者との示談を早期に成立させることです。
示談が成立したということは、被害者に示談金が支払われて精神的な被害が慰謝されたことを示します。
さらに、被害者が犯行を許して寛大な処分を望む旨を示談書に記載してもらえれば、被害者の処罰感情が消失したことも明らかとなります。
検察官は、このような事情を被疑者に有利な事情として考慮するので、示談書があることで起訴を控えてもらえる可能性が高まります。
起訴を避けるための示談は、検察官が起訴処分とするか否かの判断を下すまでの期間(逮捕されたときは、逮捕から最大23日)にする必要があります。
盗撮をしてしまった方やその家族は、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。弁護士は、事件ごとに適切なアドバイスや弁護活動、示談交渉を行ってくれます。

[参考記事]
弁護士に盗撮の示談交渉を依頼するメリットとは?逮捕後の流れ
4.盗撮と懲役刑に関するFAQ
-
盗撮の初犯は罰金・懲役刑となる?
盗撮の初犯の場合は、悪質性の高い事案でない限り、仮に起訴されても罰金刑であり、懲役刑が選択されることはないでしょう。
しかし、例え罰金刑であっても、有罪判決による刑罰を受けたことになるので「前科」がついてしまいます。
初犯であっても盗撮の被疑者が不起訴処分となり前科を避けるために最も有効な方法は、被害者との示談です。
-
盗撮で起訴されたら懲役刑になる?
起訴をされても必ず懲役刑になるというわけではありません。盗撮事件ならば、刑事弁護次第では起訴猶予となったり、略式起訴(罰金刑)に留まったりする可能性は大いにあります。
-
盗撮の懲役、刑期はどれくらい?
盗撮の場合、各都道府県の迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反(軽犯罪法第1条23号)、住居侵入罪(刑法130条)となるでしょう。
【東京都の迷惑防止条例】
・人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為(5条1項柱書、同2号)
法定刑……1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号)、常習犯は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項)
・人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影するために撮影機器を差し向け又は設置する行為(5条1項柱書、同2号)
法定刑……6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号)、常習犯は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項)【軽犯罪法1条23号 のぞき見】
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者【刑法130条 住居侵入罪】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
5.盗撮事件の弁護は泉総合法律事務所へ
盗撮は、被害者の心に深い傷を残すのみならず、盗撮をする人にとっても懲役刑などのリスクが十分にある犯罪行為です。
犯してしまった場合には、十分に反省をした上で適切に対処していくことが極めて重要です。
逮捕されてしまった場合に裁判官に勾留請求されてしまうと、長期の身体拘束が行われる可能性も出てきます。刑事事件は早めの弁護活動の開始がカギとなるのです。
盗撮事件を犯してしまった方、逮捕されてしまった方、起訴・実刑となるかどうか心配な方は、お早めに刑事事件弁護に強い泉総合法律事務所にご相談ください。